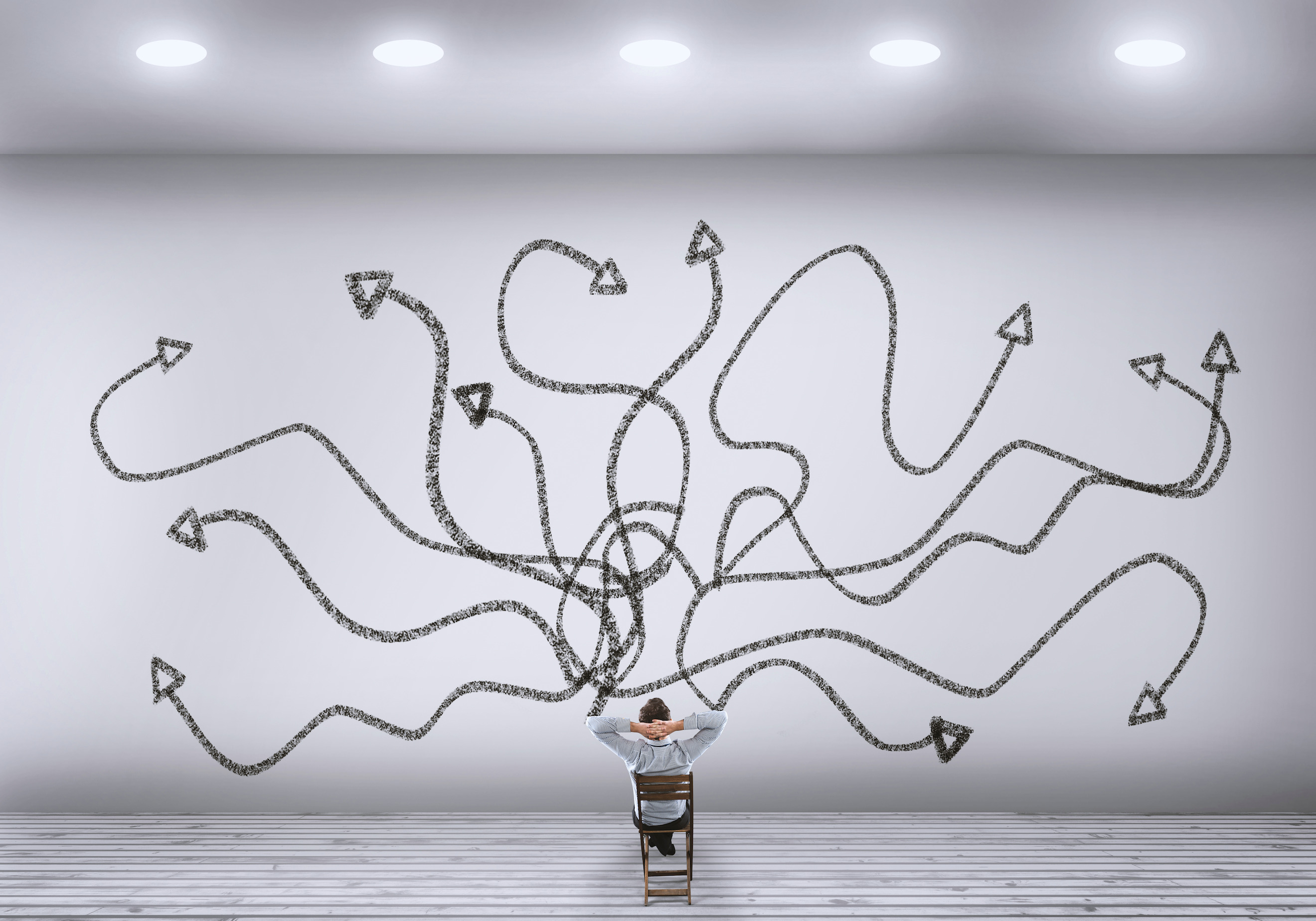金剛杖
埼玉県の特に北部の地域では、お葬式に参列する人達に「金剛杖」と呼ばれる杖を配り、それを持って参列してもらうという風習があります。
金剛杖というのは、修行僧などが持つ白木の杖で、これは弘法大師の諡号で知られる日本仏教においてとても重要な存在である、「空海」の化身であると考えられています。
この金剛杖を持って修行の道を行くということは、弘法大使と共に歩くということになるため、「同行二人」という呼び名のとても深い意味がある風習です。
地域によっては、納棺の際に副葬品として金剛杖を入れる地域もあります。
金剛杵
「金剛杖」に名前が似ているものに「金剛杵」というものがあります。
読みは「こんごうしょ」ですので、金剛杖を「こんごうじょう」と読んだ場合にはとても似たものになります。
金剛杵も日本仏教で頻繁に目にする道具の一つで、執金剛神の仏像や絵などで手に持っている姿が最も有名でしょう。
杖と杵では形も大きく違うため、一度違いを理解してしまえば間違えることは無いですが、字はとても似ているため、もしこれらの物を初めて購入したりする場合には、念のため確認をするようにしましょう。
男性の参列者は額に三角の白い布
埼玉県の北部の地域では、男性の参列者は額に三角の白い布をつける風習もあります。
白い布は故人の着る死装束と同じ意味があるため、部分的にではありますが参列者も故人と同じ格好になることになります。
故人と同じ格好をしてお葬式に参列することで、あの世の手前までお見送りするという意味があります。
このような風習は埼玉県以外でも全国各地で行われていて、女性もこのような白い衣装を着ける地域もありますが、埼玉県では着けないことがほとんどです。
この布の呼び方も全国各地で違いがありますが、埼玉県では「かんむり」と呼ばれています。
紅白の水引の香典袋
埼玉県の秩父などの地域では通夜の時に香典をわたす際、一般的な白黒の水引きではなく紅白の水引を掛けてわたすことがあります。
紅白は祝い事などで使う印象がありますが、そういった意味でこの色を選ぶわけではありません。
入院中のお見舞いに行けなかったことにお詫びをしながら、遅くなってしまいましたが受け取ってください、といった意味でわたします。
こういった意味でわたす際には、香典袋の表書きは「お見舞い」になります。
お見舞いのお金をわたすことは珍しくありませんが、香典としてわたすのか、香典とは別にお見舞を包んでわたすのかには考え方に差がありますので、どちらにすべきか迷うようでしたら、その地域の葬儀社などに聞いてみると良いでしょう。