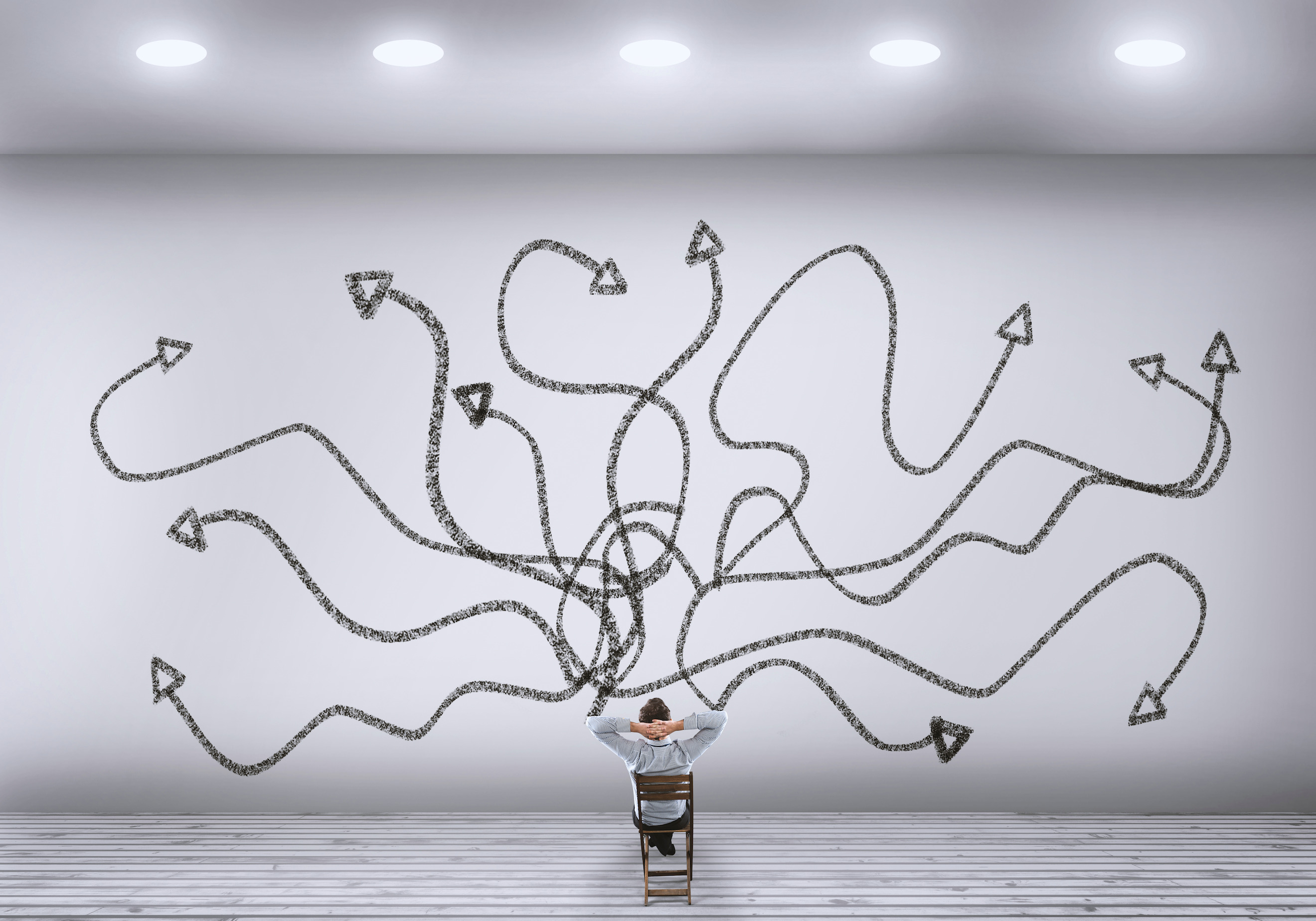旅とは、民俗学者の神崎宣武(かんざきのりたけ、1944〜)が言うように、「居住地を離れて、遠方の土地を訪ねる行為」だ。2019(令和元)年12月から2023(令和5)年5月まで続いた、新型コロナウィルス感染拡大による、「自粛」「隔離」等々で、日本国内のみならず、海外においても、自由気ままな旅行をコロナ禍前のように楽しむことができなくなっていた。もちろん、今ではそのようなことはないが、最近では、「2025年7月5日に日本を大災害が起きる」と、たつき諒(1954〜)の漫画、『私が見た未来』(1999/2021年)に描かれた「予言」に影響されて、主に中華圏からの観光客が減っているという報道がなされた。

高まる旅行熱 旅とは居住地を離れて遠方を訪ねる行為
今日の「旅」は、「仕事」「研究調査」「友達に会う/友達と交流する」「恋人と楽しい時を持つ」「新婚旅行」「リフレッシュ」「実家に帰省」「家族と共に過ごす」「遠距離介護」等々、人それぞれの目的によって「当たり前」のように世界中でなされている。それは交通網の発達のみならず、インターネットで「行きたいところ」の情報を検索した後、新幹線や飛行機、そして宿泊先やレストランなどの予約や変更・キャンセルが容易かつ、時に割安に利用できるようになったことで、ますます、いわゆる「旅行熱」が高まっているのだ。
作家でプロデューサーの長倉顕太(ながくらけんた、1973〜)は『移動する人はうまくいく』(2024年)の中で、「『移動』こそあなたの能力を開花させ、人生を変えることになる。移動しまくることで、今までの当たり前が当たり前じゃないことに気づくことになる」、「他人と違う視点が手に入るから他人と違う人生になる…(略)…私たちの脳はいつも同じ場所にいると、何も考えなくなり、何も感じられなくなる」など、必ずしも「旅」をすることとはイコールではないものの、「旅」に含まれる「移動すること」の効用を詳しく記している。
旅という言葉の語源 「よそで使う火」
しかし「旅」という言葉の語源、「たべ(「たぶ(与ふ)」の尊敬語)」、そして「たび(他火)」、すなわち「よそで使う火(自宅ではなく、誰かの家で一宿一飯の施しを受ける。或いは自ら火を起こして食事をすること)」から勘案すると、「お祭り気分」「癒し」「気分転換」「今までの固定観念打破」等、今日の「旅」のポジティヴなイメージと、必ずしも重なるものではなかった。時に「苦行」。そして「死」と隣り合わせでもあった。それは全国を経巡る修行僧にとってだけではなく、日本古代史研究家の坂江渉(1959〜)が指摘するように、日本において、鉄道や車などの移動手段が発達する前、殊に古代においては、人が旅する「道」は、陸路水路を問わず、人・モノ・情報が行き交うところであるがゆえに、「貧困・病・死」の問題が集約的に現れる場でもあった。
『日本書紀』に見る「行き倒れ」の悲劇
坂江の指摘によると、古くは『日本書紀』(720年)第25巻 孝徳天皇(596〜654)の大化2(646)年3月22日の詔(みことのり)である「薄葬(はくそう)令」の中に、「行き倒れ」の事例が記載されている。ひとりの役人が都から離れた地方での仕事を終え、帰郷の際に急病のため、そのまま路頭で亡くなってしまった。すると、その道のそばに住む人々が、「どうして私の家の前で、旅人が死んでしまったのか!」と、役人と行動を共にしていた仲間を押しとどめ、無理やりお祓いをさせる。こうなると、仮に兄が旅先で亡くなっても、その弟は兄の遺体を引き取ろうとしない、という。
また、『日本三代実録』(901年)第43巻 陽成天皇(869〜949)の元慶7(883)年正月26日の詔では、渤海国(現・中国東北部〜朝鮮半島北部)からの使節団が訪れるため、山城(現・京都府南部)・近江(現・滋賀県)・加賀(現・日本海側南西部の福井県、岐阜県)・越前(現・石川県南部)国などに、官舎や道・橋の修理のみならず、路傍の死骸の埋葬も命じていた。
松尾芭蕉の最後の句 「旅に病んで 夢は枯野をかけ廻る」
時代は一気に下るが、俳聖・松尾芭蕉(1644〜1694)が「最後の句」とされる、
「旅に病んで 夢は枯野をかけ廻る」
を詠んだ。この歌意を現在の我々が知るすべはないにせよ、芭蕉は、
1.今、旅先で病の床についているが、夢の中では枯野を自由闊達に駆け巡っている。快癒の際はまた再び、旅に出よう!
2.夢の中では枯野を駆け巡っていたが、自分はもう、旅を続けることができず、このまま死んでしまうのか。辛い…
1と2、いずれかの思いを抱いていたのではないだろうか。特に2の場合、1970〜92(昭和45〜平成4)年に放送された、日本のテレビ時代劇を代表する『大江戸捜査網』シリーズの要とも言える、「隠密同心 心得の条」、
我が命 我が物と思わず
武門の儀 あくまで陰にて
己の器量伏し ご下命如何にても果すべし
なお 死して屍拾う者なし
死して屍拾う者なし
の最後のくだりは、隠密同心のひとりが仮にどこかで亡くなってしまったとしても、誰もその遺体を手厚く葬ることはない。身元不明の行き倒れ人として、そのまま放置される、という意味だ。このことを、芭蕉も強く意識していたのではないだろうか。もちろん、芭蕉自身が「そうされる」ということに限らず、長い旅路の途中で、行き倒れなのか、何かの事件に巻き込まれたのか。腐敗するがままになっている遺体を、芭蕉は何度も何度も目にしていたのではないか。「枯野」という言葉はもちろん、草木も生えない凍てついた冬の野原を表すものであろうが、街道筋などで、さまざまな経験を積み、いろいろなことを見聞きしていたであろう、あるひとりの人間が捨て置かれたままだというのに、誰も気にせず通り過ぎていく。その荒涼たる「現実」をも意味しているように思えてならない。
もちろん江戸幕府は、旅人の身の安全を守るための対策を講じていた。例えば元禄2(1689)年に、行き倒れの旅人を救助するための触書(ふれがき)を出した。それは、2日の範囲で、病で倒れた村人の居住地の村へ連絡せよ、というものだった。享保18(1733)年には、連絡の範囲を全国に広げることが定められた。そして明和4(1767)年、病に倒れた旅人の取り扱いについてのお触れも出された。だからといって、旅人の「不安」がなくなるものではなかったことは、言うまでもない。
江戸時代の「行き倒れ」事例 神戸村の尼僧の死
芭蕉の生涯とは重ならないが、「似たようなもの」だった、「大きく変わるところはなかった」と推察される事例を挙げる。文政12(1829)年〜天保2(1831)年、天保7(1836)〜8(1837)年の、摂津國八部郡神戸村(現・兵庫県神戸市)における「行き倒れ」の人々への対応を精査した歴史学者の石橋知之(1993〜)によると、例えば、文政12年11月に、ひとりの若い尼が、村人の家の裏納屋で倒れていた。尼は何を言っているのか判然とせず、見るからに、何らかの病気にかかっている様子だったため、その村人はすぐに村役人に報告した。尼は介抱され、薬を施されたものの、その日のうちに亡くなった。不幸中の幸いだろうか。尼の身元はすぐに判明した。実は11年前に、この村から家出した者だったのだ。親族から遺体引き取りの申し出があったものの、村役人はすぐにそれを了承しなかった。死亡から3日後、尼の遺体は「仮埋め」を命じられた。それから更に4日後、大津の代官所から遺体の「片付(かたづけ)」が認められ、身内の者が葬儀を行なったという。
ということは、時に、「認められない」場合もあるということだ。男女が心中を行い、共に亡くなってしまった場合であれば、その遺体は遺族に渡されない。地域の代官所から「取捨(とりすて)」が命じられ、遺体は「そのまま」にされる。この措置は、通行手形などを持たず、身元不明の「行き倒れ」の旅人や、地域を徘徊しているような、今でいう「ホームレス」の場合もまた同様に、「取捨」が命じられたという。この尼に関して言えば、自分の「ふるさと」に戻ったところで倒れたこと。それに加え神戸村そのものも、他の農村地帯とは違い、交易で開けた「港町」だった。それに加え、村が四国遍路など、参詣・巡礼目的の旅人が多々通る街道沿いに位置していたことから、村役人と代官所との連携が強い地域だった。こうしたことから、尼は無事に身内の元に戻ることができ、弔いの儀式を済ませることができたのだ。
現代の行き倒れ 「行旅死亡人」
では、現在の日本では、どうなっているのか。病気・行き倒れ・自殺した人で、名前や住所などの身元が判明せず、引き取り人不明の亡くなった人を意味する、「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」という法律用語がある。明治32(1899)年に定められた「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律の第7条が今日まで引き継がれている形で、その人が亡くなった場所・地域を管轄する自治体が火葬を行う。その後、国の『官報』に亡くなった人の身体的特徴・発見時の状況・所持品などが公示され、引き取り手を待つことになる。遺骨はその自治体の倉庫、或いは自治体から委託・依頼された地域の墓地・納骨堂・斎場・寺院・遺品整理業者などで保管される。ちなみにこの法律における「死亡人」は必ずしも「旅」の途中で亡くなった人とは限らず、時に「自宅」における「孤独死」もあるという。「人はいつか死ぬ」のは自明の理ではあるが、行き倒れて誰にも看取られず、時に何年、何十年も「死んだまま」になってしまうことをあえて、「選択」したい人はいるのだろうか。
旅と仕事がセットになったリゾートバイトのリスク
「リゾートバイト」、或いはその省略語「リゾバ」という言葉がいつの間にか存在し、当たり前に使われている。成り立ちは「リゾート」と「アルバイト」を足したもので、日本全国のリゾート地に住み込みで働くアルバイトのことだ。昨今では「身軽」な立場の「若者」ばかりでなく、65歳以上の「経験豊富」な「シニア」もまた、リゾートバイトに積極的に応募し、働いているという。
業務としては主に、ホテル・旅館などでのフロント業務や調理、ベッドメイクや建物清掃などの裏方仕事、土産物屋での接客、農園で作物の収穫…などが挙げられる。しかしその「場所」が「地味」「堅実」「自分の地元でよく知っている」ところではなく、休みの日や仕事の合間に、温泉、スキー、スキューバダイビング、登山、ツーリング…などが楽しめる、主に北海道・沖縄・長野・熱海・下田・伊豆などが有名だ。それゆえ、仕事の内容そのものは「自分の地元」でいくらでも探すことができるものであっても「場所」が「リゾート地」であるがゆえに、「非日常」「ハレ」「お祭り気分」を満喫できるところが最大の魅力だ。
加えて、住み込みであることから、朝昼晩の食事が無料であるのはもちろんのこと、毎月の家賃、そして光熱費の心配もない。コインランドリーやWi-Fiも使い放題。温泉で有名なところであれば、サウナや絶景の露天風呂で仕事の疲れを癒すこともできる…。
こうした「夢のような」場所で働くことは、必ずしも「いいこと」ばかりではない。リスクとして、以下のものが挙げられる。
① 募集時の待遇面での「いい話」や、「キラキラした」仕事とは全く異なる、「汚れ仕事」をさせられる。或いは、残業代が全くつかなかったり、週休0休だったりする、いわゆる「ブラックバイト」だったと判明すること。
② 寮やアルバイト先そのものが夜は全く人通りがなく、しかも「都会」のように監視カメラがあまり設置されていないことから、安全面に問題や不安があること。
③ 誰が「犯人」かが判然としない、物損・盗難事故の頻発。
④ 「その場限り」と割り切ってしまい、「普段」「日常」のように遠慮しない物言いによる、「いじめ」「誹謗中傷」などの人間関係トラブルが起こりやすいこと。
⑤ 従業員同士で借金を返さないこと。または「儲け話」や「宗教」などのしつこい勧誘。
⑥ 「ハレ」の気分が昂じ、刹那主義に陥りやすかったり、「いつも」のように冷静な判断ができなかったりすることから生じる、従業員同士や雇用主、或いは地元住民との恋愛トラブルの発生。
リゾートバイトの悲劇
殊に⑥だが、裁判が今年の6月19日に始まったばかりであるので、「真実」が解明されたとは言えないものの、相模湾の南方に連なる伊豆諸島の最北部に位置し、東京都港区の竹芝(たけしば)桟橋からおよそ100キロの位置に所在する伊豆大島で、「リゾートバイト」であちこちを転々としていた女性が行方不明になっていた。その後、女性と不倫関係にあったとされる、埼玉県から移ってきた畳店経営者の男性によって、昨年の9月9〜10月23日の間に、女性の遺体が損壊・遺棄されるという事件が起こった。
このようなことになったのは、女性が「リゾートバイト」に従事していたから、または「あちこち渡り歩く女性」だったからなのか。それとも、男女の恋愛感情の「盛り上がり」やその「破綻」は、「場所」や「状況」には一切関係ない。そう考えると、こうした事件は「珍しいことではない」のか。ただ言えることは、「お祭り気分」の「伊豆大島」において、ちょっとした「いいこと」がふたりにとって「運命」となり、逆にそれが醒めた時は相手に「消えてもらいたい」ほどの「地獄」になってしまった、ということだ。
多くの「場所」と「出会い」 旅の効用
人それぞれ、時代や国によって、「旅」の意味合いは違ってくるものの、かつて17世紀末から19世紀までのイギリス貴族は、成人前の子弟に見識を広めさせるために、「グランドツアー」と称する、フランスやイタリア、ギリシャなどへ、それまで学んできた哲学・美術・文学・歴史などの「総仕上げ」としての長期旅行を「通過儀礼」として行わせていた。西洋美術史・思想史研究家の岡田温司(1954年〜)によると、哲学者ジョン・ロック(1632〜1704)の『教育論』(1693年)で、「旅」が若い青年貴族たちに冒険心や勇気・決断力や礼儀作法を養う絶好の機会として推奨していたという。
北海道出身で、利尻島、徳之島、八丈島、そして静岡県の下田などで「リゾートバイト」をしていたという被害者女性の骨が数点、発見されたという、伊豆大島南端の「砂(さ)の浜」だが、芭蕉が夢の中でかけ廻った、茶色く枯れしぼんだ草木が広がる「枯野」ではなく、伊豆大島「名物」の、およそ2万年前に何度も起こったとされる大噴火の影響による、火山灰や火山砂、砕けた溶岩が集積した真っ黒な、日差し眩しい砂浜だった。彼女にとって、「そこ」は最良の「場所」だったのか。もしも「日常」ではない、「リゾート地」で人生が終わったことが、本意ではなかったとしたら…「いろいろあって」、あちこちを転々としていた彼女には、かつてのイギリス貴族が抱いた思いとは違っても、もっといろいろな「場所」で「リゾートバイト」や「思い出づくり」。そしてそこで多くの人々との「出会い」や「交わり」を経験し、堪能して欲しかった。
参考資料
■東京学芸大学地理学会30周年記念出版専門委員会(編)『東京百科事典』1982年 財団法人国土地理協会
■唐木裕志『他火と歴史的景観 ―讃岐の古道―』1993年 他火の会
■福永重樹「ごあいさつ」目黒区美術館(編)『旅へのあこがれ 画家たちのグランド・ツアー』1997年(2頁)目黒区美術館
■小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守(編)『新編 日本古典文学全集 4 日本書紀(3)』1998年 小学館
■山田敦雄「画家たちの残したもの」目黒区美術館(編)『旅へのあこがれ 画家たちのグランド・ツアー』1997年(37-39頁)目黒区美術館
■神崎宣武「旅」福田アジオ・新谷尚紀・湯川洋司・神田より子・中込睦子・渡邊欣雄(編)『日本民俗大辞典』下巻 2000年(59頁)吉川弘文館
■黒板勝美(編)『新訂増補 國史大系 第4巻(オンデマンド版) 日本三代實録』2007年 吉川弘文館
■岸田秀樹「近世都市大坂における自殺対策(後編) ―千日墓所の死亡埋葬記録に基づいて―」『藍野学院紀要』第22巻 2008年(89-104頁)学校法人藍野学院
■岡田温司『グランドツアー 18世紀イタリアへの旅』2010年 岩波書店
■「大江戸捜査網とは」『テレビ東京』2015年
■「中世貴族も旅したヨーロッパの美しい街 25選 貴族の若者が周遊した街は、今もトップクラスの観光都市」『NATIONAL GEOGRAPHIC』2018年4月28日
■中島俊郎『英国流 旅の作法 グランド・ツアーから庭園文化まで』2020年 講談社
■安居正浩「『旅に病んで夢は枯野をかけ廻る』は辞世句か」『芭蕉会議』2010年10月2日
■石橋知之「摂津国神戸村における『行き倒れ』」藤本清二郎・竹永三男(編)『「行倒れ」の歴史的研究 ―移動する弱者とその救済―』2021年(159-182頁)公益社団法人部落問題研究所
■坂江渉「古代の『在路飢病者』と地域社会」藤本清二郎・竹永三男(編)『「行倒れ」の歴史的研究 ―移動する弱者とその救済―』2021年(37-48頁)公益社団法人部落問題研究所
■藤本清二郎「総論 『行倒れ』―移動する弱者とその救済―」藤本清二郎・竹永三男(編)『「行倒れ」の歴史的研究 ―移動する弱者とその救済―』2021年(7-25頁)公益社団法人部落問題研究所
■「芭蕉終焉(ばしょうしゅうえん)の地」『大阪市』
■「伊豆半島は静岡県、なぜ伊豆諸島は東京都なのか…日本から切り離され『独立』していた時期も」『読売新聞オンライン』2023年6月20日
■大橋昭一「ザ・グランドツアーから現代的ツーリズムの生成へ −近代的ツーリズムの進展過程の研究−」『観光学』第28号 2023年3月20日(13-25頁)和歌山大学観光学会
■東琢磨「きんようぶんか:多額の現金を遺して死んだ身元不明の女性の謎を追う」『週刊金曜日』2023年2月24日号(54頁)株式会社金曜日
■長倉顕太『移動する人はうまくいく』2024年 すばる舎
■「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)」『e-Gov 法令検索』2024年4月1日
■伊豆大島ジオパーク推進委員会(編)『伊豆大島ジオパークMAP』2024年10月 伊豆大島ジオパーク推進委員会
■「<伊豆大島・ラウンジ嬢死体遺棄♯1>逮捕された男は妻子持ち“不倫関係”『女性は沖縄に旅行いくといってから行方不明になった』遺体の骨の一部が砂浜で発見」『集英社オンライン』2025年1月24日
■「<伊豆大島・ラウンジ嬢死体遺棄♯2>妻子を埼玉に残し島で女遊び『片っ端から女の子に声かけて…』チャラ男“ソータツ”の地元の評判は?」『集英社オンライン』2025年1月24日
■「<伊豆大島・ラウンジ嬢死体遺棄♯3>不倫の末、別恋人まで…チャラかった元暴走族男に被害女性は包丁を2本購入、手にガムテープでグルグル巻きにして家に乗り込む交際トラブル」『集英社オンライン』2025年1月24日
■「<伊豆大島・ラウンジ嬢を農機具でバラバラ遺体に…♯4>『(被害女性の)連絡先も知らない』『心配だな』と逮捕前に不倫チャラ男はシラばっくれていた」『集英社オンライン』2025年1月25日
■「伊豆大島『リゾートバイト人骨遺棄事件』は不倫関係のもつれだった『“自供なし”では厳しかった』2日間20時間以上にわたる取調室での攻防を」『デイリー新潮』2025年1月24日
■「<伊豆大島・ラウンジ嬢死体遺棄事件も発生>経験者が語る“リゾートバイト”トラブルの実態『ワンナイトや不倫も多発していて…』を」『集英社オンライン』2025年1月25日
■「伊豆大島『ラウンジ嬢死体遺棄事件』被害者が働いていた『リゾキャバ』と客の密接な関係性」『Asagei plus』2025年1月27日
■株式会社日本総合研究所「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業 報告書」『厚生労働省』2025年3月27日
■「《不倫相手を惨殺》『遺体を焼いてのこぎりで切断。袋に入れて海に捨てた』チャラすぎる伊豆大島のモテ男が溺れた“3股不倫”の代償」『文春オンライン』2025年4月27日
■「漫画が『予言』する大地震に不安増大、外国人客の訪日中止や延期相次ぐ」『CNN.co.jp』2025年5月20日
■「シニアが活躍する『リゾートバイト』時給1200円でも“衣・食・住無料”『まだまだ働きたい』シニアな働き方」『FNNプライムオンライン』2025年6月6日
■「リゾートバイトは危ない?危ないといわれる理由と対策を解説」『Alpha Resort』2024年11月19日/2025年6月9日
■「伊豆大島 女性遺体遺棄事件 交際相手が起訴内容を認める」『khb.東日本放送』2025年6月19日
■「囲炉裏って? 『旅は他火、炎の癒し効果』」『ささゆり庵』
■「越後佐渡ヒストリア〔第34話〕旅に病む人を送る『村送り状』安全安心だった江戸時代の庶民の旅」『新潟県立古文書館』
■「芭蕉データベース 旅に病で夢は枯野をかけ廻る」『山梨県立大学』
■「芭蕉年譜(PDF)」『江東区芭蕉記念館』
■宮本孝一「年表 新型コロナウィルス感染症対策(2019.12〜2023.5)(PDF)」『地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター』
■『リゾバ.com』