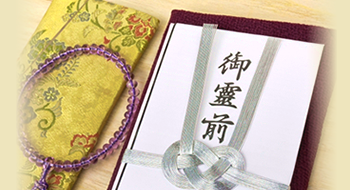数珠とは、手にかけて合掌したり、また、揉むようにして音を出して使用します。
数珠は元々、念仏の回数を記憶するためのものとして使われていましたので、「数珠」ではなく「念珠」とも呼ばれます。
数珠の珠の数は宗派により異なりはありますが、基本的には「煩悩の数」、つまり「108つの珠」をつないだものとなり、他には54、27、18など多くの種類があります。
数珠は持っているだけで功徳を積むことができ、魔除け、厄除けにもなると言われています。お守りとして常時持ち歩くのもよいでしょう。また、数珠は貸借するものではありません、ご自身の数珠を持たれたほうがよいでしょう。
本式数珠・略式数珠
数珠は宗派により仕立てが異なる「本式数珠(または本連数珠)」、これは正式なものなので珠の数も多く、輪を二重にして握る「二連珠」です。また、どの宗派でも使用できる「略式数珠(または片手数珠)」があり、これは数珠の形を保ってはいますが、携帯しやすいよう珠の数を減らし、その関係で一重のものが多く、「単念珠」とも呼ばれます。
※宗派によっては「単念珠」であっても「本連数珠」であるものもあります。
最近は略式数珠を持たれる方が多くなりました。身内や地域の特性を確認して、特にこだわりがなければ略式数珠を持たれましょう。それでも、やはりきちんとした数珠を持っておきたい、という方は、ご自身の宗派に合った本式数珠を持つのがよいでしょう。特に、身内の葬儀では「本連数珠」のほうが良いとされます。
普段の生活では宗派や数珠のことなどほぼ意識することはないと思いますが、いざ、葬儀・葬式、法事の際に慌てないため、また、ご自身を知るためにも、ご両親や親戚にご自分の宗派を訊き、数珠を持っておくようにしましょう。
※数珠が切れたら縁起が悪い? いえ、108の煩悩を表す数珠のㇶもが切れることは、むしろ縁起がいいと言われています。数珠が切れたら修理を依頼するか、新調するようにしましょう(お寺、仏壇仏具店、念珠専門店で購入できます。相場は1,000円以下のものから3万円以上するものまでさまざまです)。
※数珠は祝い事に贈ることもできます。成人式や結婚、節目の贈り物として贈るのもよいでしょう。
日本の仏教と宗派と数珠
日本の仏教には数多くの宗派が存在し、宗派によりご本尊、お経、作法、それぞれが違い、数珠の仕立てや持ち方にも違いがあります。
最澄が日本で最初に「日本天台宗」を開いて以降、平安時代から鎌倉時代にかけ、分裂しながら次々と新しい宗派が打ち立てられました。天台宗、浄土宗、真言宗、浄土真宗、日蓮宗、曹洞宗、臨済宗、等、これら各宗派により数珠の形は異なり、特には「珠の数」、「房」が異なります。
【真言宗】
真言宗では特に数珠を大事にするといわれ、在家用には主珠108つ、親珠2つ、四天珠4つ、梵天房が一般です。長い一連の数珠を二重にして持ち、その形状から「振分(ふりわけ)数珠」とも呼ばれています。密教では数珠を擦り鳴らし音を立てる特徴があり、修法の終わりを知らせる合図とし、また、数珠を擦ることは108の煩悩を擦り砕く、という意味があります。(男性用36.3cm、女性用24.2cmがあります)
1.両手の中指で数珠をかけます。
2.そのまま合掌します。
3.房は自然と垂らします。
【浄土真宗】
浄土真宗の数珠は、数取りができないよう房が「蓮如(れんにょ)結び」になっており、これは「煩悩具足(ぼんのうぐそく):そのままで救われる」という教義からです。数珠の形にこだわりはないものの、大切な法具として扱い「門徒数珠」とも呼ばれます。本来、一連の長い数珠を二重にして用いますが、男性は一連の数珠に紐房を付けたものが主流です(主珠108つ、親珠2つ、四天珠4つの構成)。
また、浄土真宗には「本願寺派(お西)」と「大谷派(お東)があり、数珠の持ち方も違います。
・本願寺派(お西):数珠を二重にし、合掌した手を掛け、房を下に垂らします。
・大谷派(お東):二重にした数珠を親指と人差し指の間ではさみ、房は左手側に垂らします。
※男性用の数珠は、基本、片手数珠の持ち方と同じです。
【日蓮宗】
日蓮宗では、数珠一つひとつに意味を与えた数珠曼荼羅があると説きます。数珠は「法華(ほっけ)数珠」とも呼ばれ、祈祷する際、木剣と数珠を組み合わせたものを打ち鳴らします。そのため黒檀や紫檀などの硬く丈夫な材質が主流でしたが、最近では水晶などのさまざまな素材があります。
1.数珠の輪を8の字にねじり、中指に掛けます。
2.右手に二本の房、左手に三本房がくるよう持ちます。
3.そのまま合掌します。
【浄土宗】
浄土宗の数珠は2つの輪を一つに繋いだような形状が特徴です。僧侶が儀式の際に使用する数珠は「荘厳数珠」と呼ばれ、水晶のみの108珠の数珠です。一般在家信徒が使用する数珠は「日課数珠」と呼ばれ、「私は一日に○○回念仏を唱えます」と誓約を立てて念仏を唱える回数を数える道具です。
1.2つある輪の親珠を揃えます。
2.合掌した手の親指に掛け、房は手前におろします。
※浄土宗内の宗派によっては、「房を外側におろす持ち方」をします)
【曹洞宗・臨済宗】
共に「禅宗」とも呼ばれます。禅宗では念仏やお題目を唱えず、自己と向かい合う座禅を重んじます。基本、主珠108つの一連数珠を用います。数珠は基本的に同じ形ですが、曹洞宗の場合には金属の輪が付き、臨済宗の数珠にはつきません。
1.数珠を二輪にし、左手に掛けます。
2.そのまま右手を合わせ、合掌します。
【天台宗】
天台宗の数珠は、扁平な平珠(みかんのような形)が特徴です。
主珠108つ、親珠1つ、四天珠4つで構成され、親珠から連なる房には20の平珠と10の丸珠が付いています。
1.数珠を人差し指と中指の間に掛けます。
2.そのまま合掌します。
【創価学会】
数珠の大きな特徴は、房が白房であることです。珠の数は108つです。
創価学会の数珠専門店で購入するか、学会員の方に相談されてご購入ください。
1.長い数珠を半分に折ります。
2.3つ房が右側、2つ房が左側に来るように手を掛け、合掌します。
数珠の気になる点
1.子ども用の数珠?
素材がガラス玉や、割れにくいアクリルで出来ているものが多くあり、珠の大きさや輪の長さも子どもの手に馴染むよう小さく出来ています。大人の数珠から見ればおもちゃのように見えるかもしれませんが、これは正式な数珠ですので、通夜、葬儀、葬式・告別式に使うことができます。
2.片手でもったほうがいい?
座っている時や移動している時、お焼香やお参りの時それぞれで持ち手が変わりますが、一般的に、座っている、移動している時は片手で持ちます。またお焼香、お参りの際には合掌するため両手で持ちます。(お焼香ではまず数珠を片手で持つか、手首にかけましょう。抹香を香炉にくべた後、両手で合掌となります)その他の持ち方に関しては上記宗派により違いますので、ご確認ください。
3.数珠や房の色、素材について基準は?
基本、好きな色、好きな素材を選ぶことができます。房は数珠の中でも目立つ存在、迷われることがあると思いますが「略式数珠」を購入される場合はご自身の好きな色を選んで問題ありません。また、房は付け替えが可能なので、年齢や好みで色を変えたいなと思われた時は、数珠専門店で付け替えをされるとよいでしょう。
数珠のマナーや作法は思いのほか目につくもので、信仰されている宗派を大切にしている方にとっては不快な思いをされる場合もあります。宗派によって形や作法が異なることを事前に知っておくことで無作法を回避することができ、特に、ご不幸の際には失礼に当たることのないよう、ご自身の宗派や数珠の持ち方をよく確認しておきましょう。