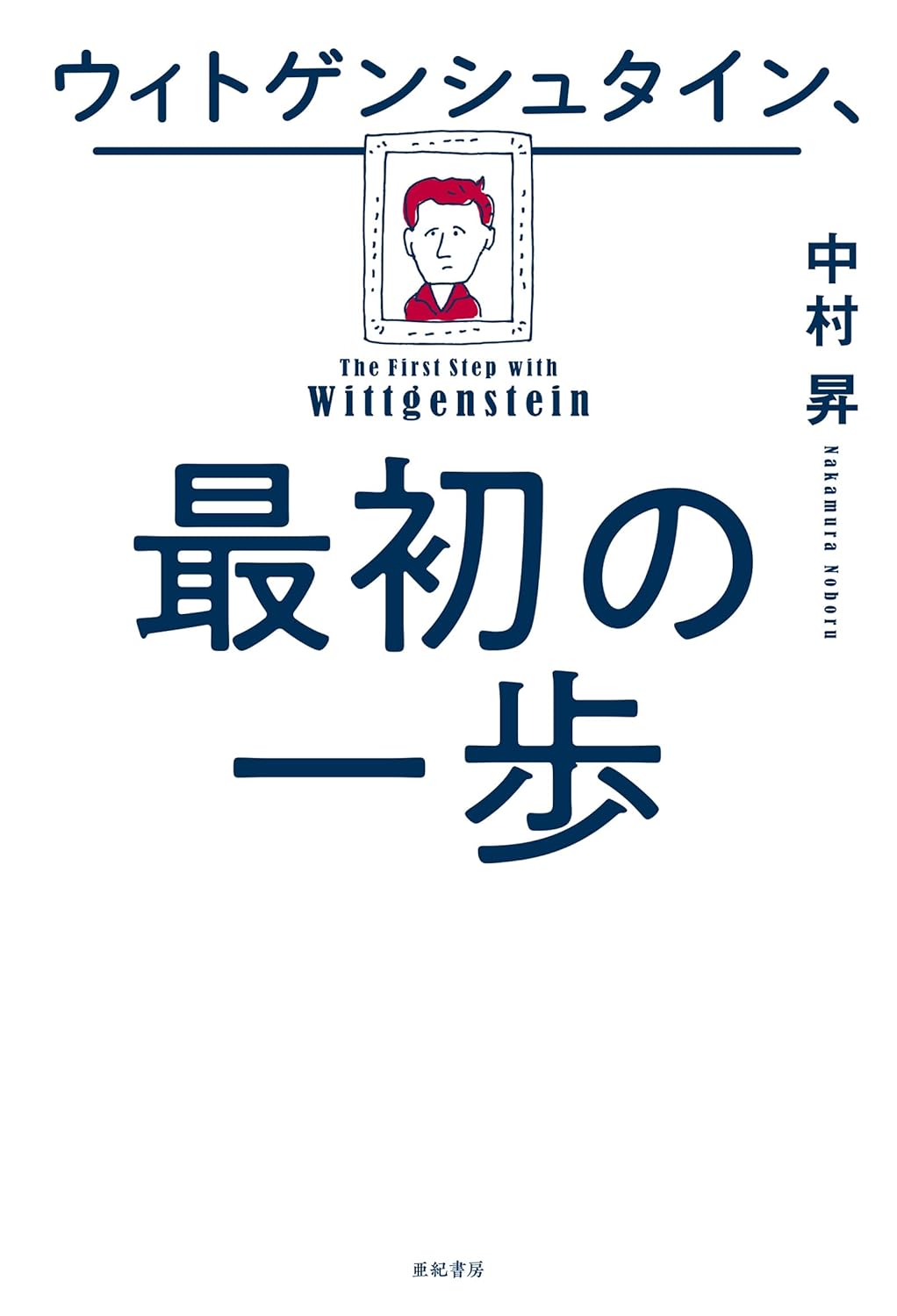当たり前だが私たちは語れるものしか語れない。しかし語っているつもりが、実は何も語っていないとしたらどうだろう。それが「死」「神」「善」などといった、人生の重大事だと思われてきたものに対しての言語だとしたら。「死」などというものは存在しないから語れないのだと、ある天才哲学者は言う。そして、語れないその先にあるものとは。
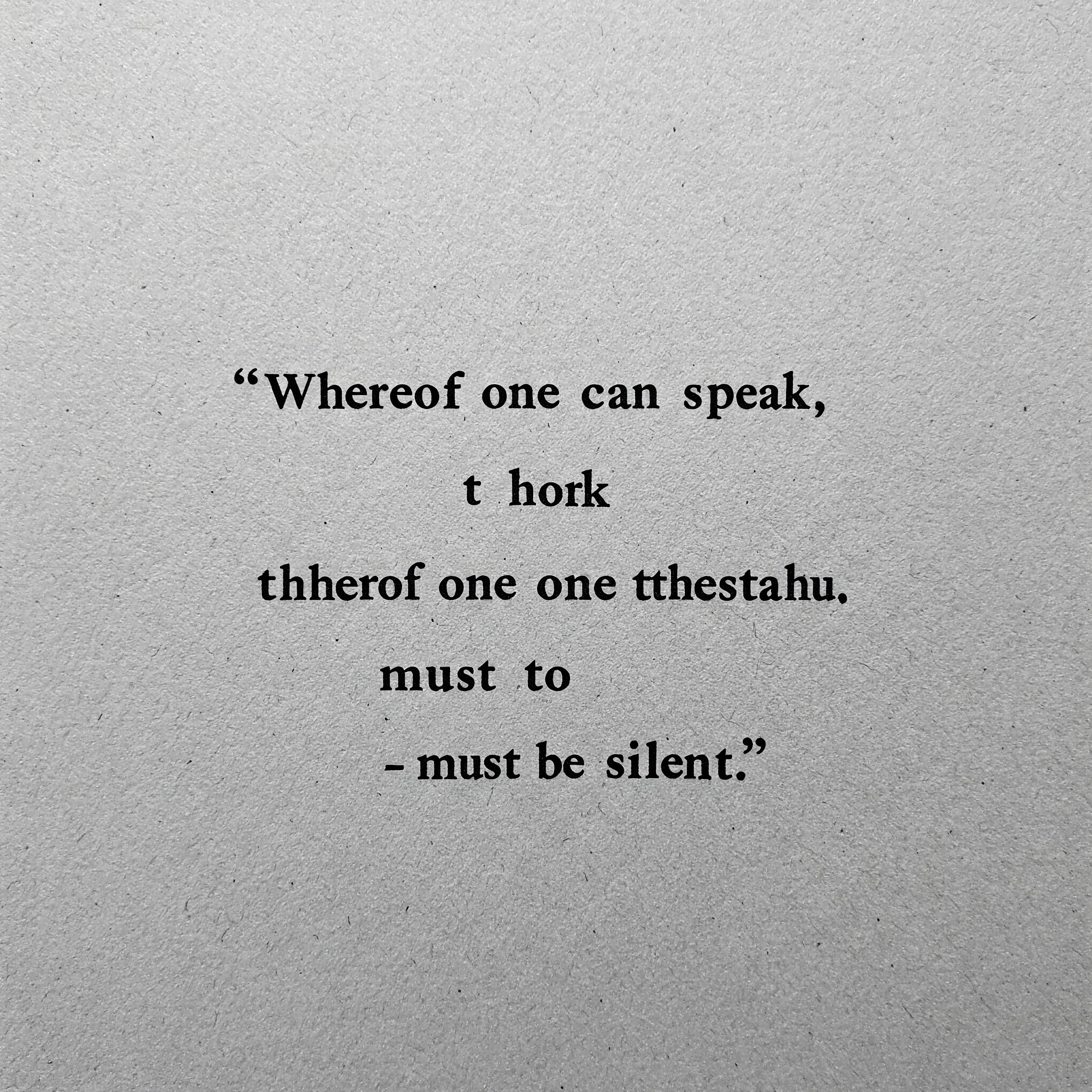
「語りえぬものについては沈黙しなければならない」
哲学・思想の歴史において最も偉大な人物は誰か。ソクラテス、プラトン、アリストテレス、デカルト、カント、ニーチェなど、哲学は知らなくても名前だけは聞いたことのあるはずのビッグネームが並ぶだろう。では哲学・思想の歴史において最も「頭が切れる」人物と問われれば「ウィトゲンシュタイン」と答える人は多いはずだ。ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(1889-1951)は「20世紀最大の哲学者」「哲学を終わらせた男」と呼ばれている。
ウィトゲンシュタインは言葉、言語について徹底的に精緻な思索、分析を行った。言葉は単なる伝達ツールではない。私たちは言葉で考える。考えるということは言葉で考えるということである。目の前のパソコンを「パソコン」という言葉を名付けて認識しなければ、例えば猫やインコにとっては、何かわけのわからない、それがあるだけである。そして「パソコン」という語からは、「このパソコンは四角い」「このパソコンは私のものである」などの文章が作られる。言葉は世界を写し取る像である。言葉で語れないものは、この世界には存在しない。
さらに言葉には真偽がある。「織田信長はボクサーである」は明らかな偽だが、文自体には意味がある。だから検証ができて、それが偽であることがわかる。だが、「今日は三角だ」という文は、そもそも文の意味がなく検証のしようがない。真でも偽でもなく無意味な文である。ここからウィトゲンシュタインは、最も世界を正確に写し取る言葉は(自然)科学であるとした。そしてまったく無意味な言葉として、哲学、宗教、倫理、道徳などを挙げた。主著「論理哲学論考」は有名なこの一文で締めくくられる。
「語りえぬものについては沈黙しなければならない」
語れることしか語れない。語りえぬものは語れない。「世界の内にいかなる価値も存在しない」のである。価値とは倫理や道徳、宗教的なものを指す。善悪や神の存在、死後の世界などは対象として実在しないので、言葉で写し取ることができない。ということは、それらを扱う哲学や思想は真偽以前にそもそも意味を成さない。私たちは語っているつもりで何も語っていないことになる。こうしてウィトゲンシュタインは哲学の息の根を止めたと言われた。
ここまで見ると科学に代表される検証可能なもの以外の、哲学や宗教といった分野はナンセンスなものとして追放するべしという結論になる。実際、この思想に強い影響を受け創設された「論理実証主義」という学派の人たちは科学的にナンセンスな言説は語りえぬもの=無意味であるとして反形而上学運動を起こした。だが彼らはウィトゲンシュタインの思想とは真逆の方向に進んだといえる。ウィトゲンシュタインは哲学や宗教そのものを無意味なものとして退けたのではない。哲学などについて「語る」ことが無意味だと言ったのだ。語れることを語りつくした、言語の限界。その先にあるもの、「語りえぬもの」こそが重要なのである。かの締めのフレーズの直前に置かれた文章はこれである。
「言い表せぬものが存在することは確かである。それは自らを示す。それは神秘的なものである」
ウィトゲンシュタインは言語の限界を突き詰め、その上で「語りえぬもの」が示されるとした。論理実証主義者はウィトゲンシュタインの手段を目的にしてしまったのである。ウィトゲンシュタインと仏教思想に親和性を指摘する学者もいるが、確かに言葉の限りを尽くしたその先に、言葉を超えた何かを示す手法は、仏教の悟りに近いものを感じる。
語れない「死」 経験なき概念の不在
この世界では語れることしか語れない。死生観で言えば、「死」を語ることはできない。私たちは死んだことがない。死んでいない以上、死を語ることはできない。語れないということは、「死」という言葉の対象は存在しない。つまり「死」は存在しない。ウィトゲンシュタインは「死は人生のできごとではない。人は死を経験しない」と公言した。
存在しないものに恐れる理由はない。確かに理屈だが、実際その理屈で死に向き合うことができる人がどれだけいるだろうか。彼のそれは虚勢ではなかった。第一次世界大戦、ウィトゲンシュタインは兵役を免れる資格(ヘルニア疾患)があるにも関わらず志願した。戦場では激戦を潜り抜け「勇敢褒章」を授与している。「論考」はその最中に執筆された。弾丸が飛び交う塹壕の中で書かれたなどという伝説もある。同じ大物とされる哲学者の従軍経験でも、気象観測員だったハイデガーやサルトルとは雲泥の差である。ウィトゲンシュタインにとって現世に「死」は存在しなかった。彼の目の前には「語りえぬもの」が示されていたのだろうか。
宗教と言葉の矛盾 無意味な神の存在論争
宗教・倫理などについて語ることは、言語の限界に逆らう無意味な行為である。宗教と言葉は相容れないものだ。神や霊が在るとか無いとかの議論は語っているつもりで何も語っていない、無駄な時間を費やすだけだ。ウィトゲンシュタインによるなら、有神論も無神論も、この世界ではその主張、つまり「神」の存在の肯定、否定、いずれの言明も無意味だからである。どちらかの側に立っても、ウィトゲンシュタインに「無意味だから黙っていなさい」で終わりにされる。黙った人の前に「語りえぬもの」が示されるかどうかはその人によるだろう。ウィトゲンシュタインの前にそれは明確に示されたのだった。
「語りえぬもの」といえば、中世最大の神学者トマス・アクィナス(1215-1274)のエピソードがある。彼はある日、いつものようにミサを捧げ、その日を境に一切の執筆、口述を止めてしまった。論考を執筆中だったトマスは「私にはできない。私がこれまで書いたものはすべてわらくずのように見えるからだ」と永遠に筆を置いたという。その翌年トマスは没した。トマスの身に何が起こったのかは現代に至るまで謎である。トマス・アクィナスといえば世界史上でも屈指の知識人である。膨大な「神学大全」を著した彼もまた言語の限界を突き抜け、「語りえぬもの」が示されたのかもしれない。
「言葉は神なりき」 言葉の力と限界
ウィトゲンシュタインは言葉とは何かを追究し、世界の謎、生死の謎、神の謎にまで迫った。まさに「言葉は神なりき」であるが、現代のネット時代は言葉の乱用、無駄な言葉の垂れ流しの時代でもある。ウィトゲンシュタインの哲学に触れ、言葉の意味を通じて「語りえぬもの」について考えてみるのはどうだろう。
なお、本稿はウィトゲンシュタインの前期思想にあたる「論理哲学論考」に依っている。後期思想についてもいずれ触れてみたい。
参考資料
■ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン著/藤本隆志・坂井秀寿訳「論理哲学論考」法政大学出版局(1995)
■ノーマン・マルコム著/板坂元訳「ウィトゲンシュタイン 天才哲学者の思い出」講談社(1986)
■星川啓慈「宗教者ウィトゲンシュタイン」法藏館(1990)
■星川啓慈「ウィトゲンシュタインと宗教哲学」ヨルダン社(1989)