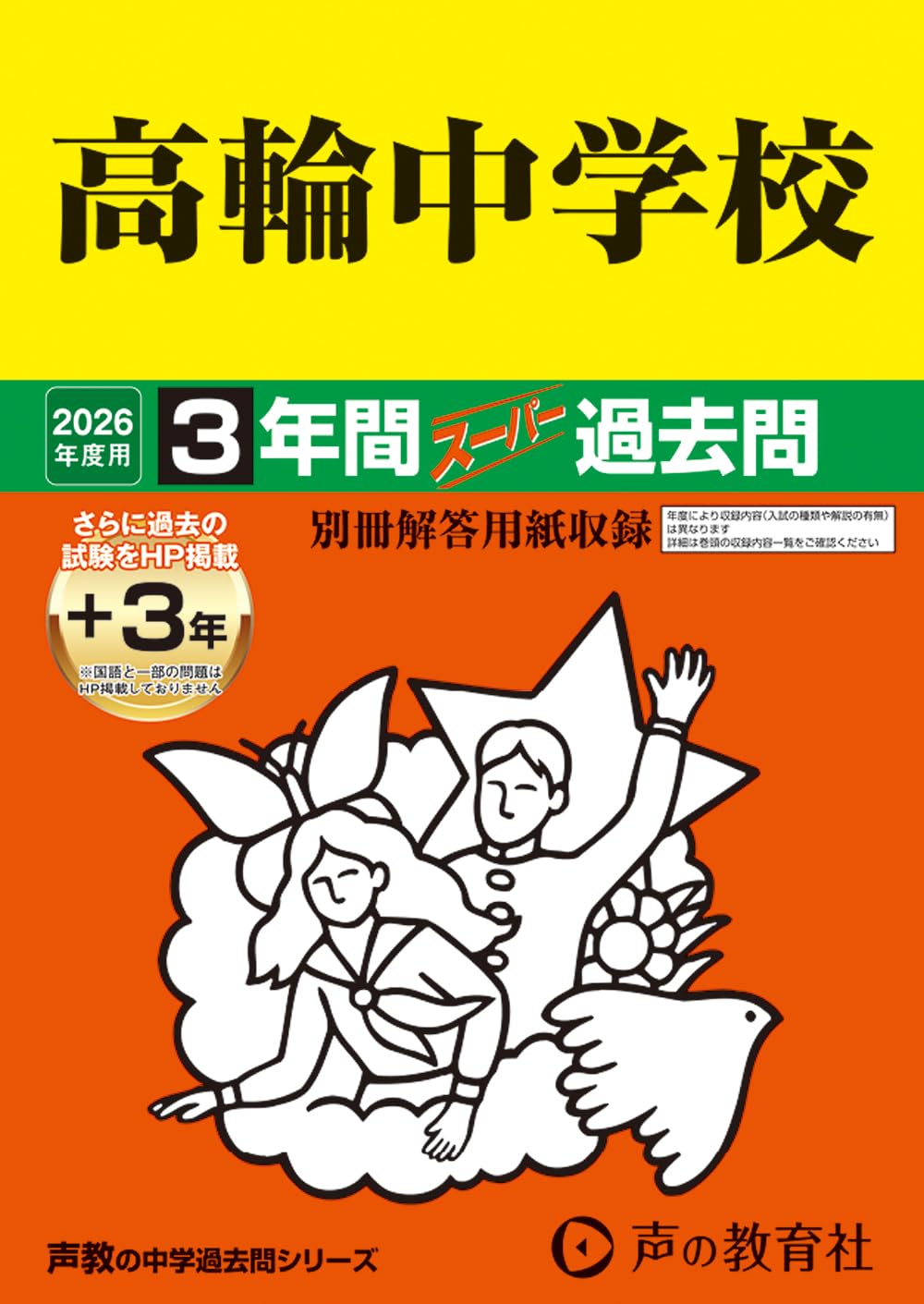東京都港区三田4丁目と高輪2丁目の間に、伊皿子(いさらご)坂という坂がある。「いさらご」という名前の由来にはいくつかの説がある。1つ目は、この辺りに住んでいた、江戸時代初期の承応2(1653)年に没したという、明代の中国人・王三官(おう・さんかん)のことを周囲の人々が「エビス(夷、外国人のこと)」と称していた。それが「インベイス」と転訛(てんか)した。それに漢字を当てると「伊皿子」になったと言われている。

伊皿子(いさらご)坂の由来の一つ「おおぼとけ」を深堀り
第2の説は、平安時代中期(9〜11世紀半ば)に成立した『更級日記』内の「竹芝寺」のくだりに、「はゝさう」という記述があるのだが、それが写本によっては「いいさらふ」となっており、そこから来たとも。第3の説は、北条家の分流である大仏(おさらぎ)流の北条貞直(さだなお、生年不詳〜1333年)がこの地に住んでいたため。第4の説は、かつてこの地に所在した高輪如来寺内に、高さ1丈(約3.3m)にも及んだ五智(ごち)如来像が5体並んで安置されていた。それらは「大佛(おおぼとけ)」と呼ばれ、江戸市中の人々が多く参詣に訪れていた。そして「おおぼとけ」そのものが「おさらぎ」とも称される。そしてそれが「いさらご」になった、とも言われている。
これらの説のうち、「伊皿子」のものと伝えられる墓が現在、高輪2丁目の高輪正源寺(しょうげんじ)脇にあることから、「伊皿子」は王三官の異称から来たという第1の説が有力だと考えられている。
だが今回は「通説」ではなく、最後の説、高輪の「おおぼとけ」について、考察してみたい。
「日常」と「非日常」が交錯する場所、高輪
伊皿子町は現在の三田4丁目近辺に充当する場所だが、かつては観月の名所で「月の岬」と称され、海と近接した、眺めのいい台地の一角に開拓された町だったという。しかも、「このあたり」は赤穂浪士の墓所で知られる泉岳寺(せんがくじ)や増上寺(ぞうじょうじ)などが所在する、江戸の「聖地」のひとつでもあった。これら今日でも知られる「聖地」或いは「宗教空間」は元々、江戸市中から遠い場所だった「はず」だが、江戸市域が拡大するにつれ、それらが「このあたり」に再び移転させられたという。それゆえ、「このあたり」には「日常」-すなわち、当時の日本の政治・経済の中心地であり、なおかつ一般市民の「生活の場」であった、町人・武士を合わせた人口がおよそ100万人と言われた江戸市中-とは異なる「風景」「空気」がある。その「非日常」性ゆえに、「聖地」そして「名所」化が進んだところだった。
そのような「場所」に所在した高輪如来寺は、寛永19〜20(1642〜43)年頃を描いたとされる『寛永江戸絵図』を見ると、先に登場する泉岳寺の南隣にあり、東海道沿いに建っていたことがわかる。明治40(1907)年に、現在の品川区西大井に移転するまで、5体の如来(五智如来)像こと「芝大ぼとけ」を参拝する人々で、大いに賑わっていたという。
「五智如来」の「五智」とは、密教における5種の知恵を指す。そしてそれらをひとつひとつ仏像に当てはめていったものだ。現在の如来寺では、中央に大日如来、いちばん左が北方世界の釈迦如来、その隣が西方世界の阿弥陀如来、大日如来の右が、南方世界の宝勝(ほうしょう)如来、いちばん右が東方世界の薬師如来が並んでいる。江戸期においては、大日如来は太陽の功徳、薬師如来は医薬の功徳、宝勝如来には福徳財宝・五穀豊穣、阿弥陀如来には往生極楽の功徳など、現世利益を願う多くの人々から尊崇を集めていた。
「芝大ぼとけ」の生みの親 木食聖・但唱
この「大ぼとけ」をつくり、芝に如来寺を開いた人物は、但唱(たんしょう。1579か81〜1641)という「木食聖(もくじきひじり)」だ。「木食」とは、その名の通り、肉類や五穀(米・麦・キビ・アワ・豆など)を断ち、木の実や草などしか口にせず、ひたすら読経三昧の修行を続けることを指す。一説には当時、木食を行うことは「不老長寿」に有効であるとか、「死後再生する」などと信じられていた、とも言われている。
そして「聖」とは、古くは平安時代末期(1068〜1192)の後白河法皇(1127〜1192)編の歌謡集『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』(1180年頃成立)で以下のように歌われた(ゆぎょう)僧のことだ。
聖のこのむもの 木の節 鹿角 鹿の皮 蓑笠 錫杖(しゃくじょう) 木欒子(もくれんじ。寺院によく植えられている落葉低木もくげんじのこと) 火打笴(ひうちけ。火打石などを入れておく箱のこと) 岩屋の苔の衣
また、『梁塵秘抄』と同時代に成立したと考えられている『今昔物語集』巻13、「籠葛川僧値比良山持経仙語(かづらかはにこもるそうひらのやまのぢきやうせんにあふこと)第二」に、現在の滋賀県大津市北西部に所在する葛川(かつらがわ)にこもり、五穀を断ち、何ヶ月にも渡って修行する僧が、『法華経』を誦する仙人と出会うエピソードが描かれている。
仏教民俗学者の五来重(1908〜1993)によると、彼らは山から山、村から村へと旅をした。とはいえ村に現れても、長逗留することはなく、すぐに山に移動し、窟(いわや。洞窟のこと)にこもる。『梁塵秘抄』に挙げられた品々に加え、聖たちは入山時に枝を切り払ったり、自分の身を守ったりするため、そして薪(たきぎ)を取るのに役立つ、山刀(やまがたな。鉈(なた))を携行していた。そしておこもりの際にそれを使って、木や石でできた仏像をつくり、村人たちに与えたり、誰も構うことがなくなった荒れ寺やお堂に安置したりしていたという。
出家するまでの但唱
今回取り上げる但唱だが、摂津國多田(ただ)郷(現・兵庫県三田市)生まれ。16歳または18歳の頃、「作仏聖(さぶつひじり)」とも称された念仏聖(ねんぶつひじり)集団を興した弾誓(たんせい。1551か52〜1613)を訪ねて佐渡國(現・新潟県佐渡市)の檀特山(だんとくせん)を訪れた。「自分の念仏は誰を師とするものでもなく、誰から授かったものでもなく、阿弥陀仏が内面で獲得された自内証(じないしょう。自らの内に体得された真実)の念仏が自分の念仏になった」と主張していた弾誓に惹かれるものがあったのだろう。但唱は彼の弟子になった。詳細は判然としないが、出家前の但唱は、江戸の檜物町(ひものちょう。現・中央区八重洲1丁目〜日本橋2・3丁目)または神田堅大工町(かんだたてだいくちょう。現・千代田区内神田3丁目〜鍛冶町1丁目)に住む、仏師またはキリシタンだったという言い伝えがある。キリスト教が禁教だったためか、或いは何らかの罪を犯したのか、磔になる寸前で赦されたことを機に、出家したという。
全国行脚の作仏聖 但唱と二万体を超える仏像
そのような但唱だが、主に信州(現・長野県)を中心に活動した。それに加え、越後(現・新潟県)、駿河国富士山麓(現・静岡県)、伊豆三島(現・静岡県三島市)、房州清澄(現・千葉県鴨川市)、上総国尾瀧(現・千葉県君津市)など、全国13ヶ所で合計13000体にも及ぶ千体仏を納めたり、各地で7000体の仏像をつくったりした。寛永8(1631)年頃、但唱が51歳になった時、それらが合計2万体になったことを記念し、それに加えて二代将軍徳川秀忠(1579〜1632)の菩提を弔うためとして、冒頭に登場する「五智如来」像をつくることを志すようになる。その製作地は「江戸」ではなく、下伊那郡小横沢(現・長野県下伊那郡松川町)に所在する、「奇妙山(きみょうさん)」だった。山の南麓の洞底にこもり、およそ1年半の間、3人の弟子と共に、作仏に勤しんだ。但唱らの活動の後、信濃国伊那郡(現・長野県伊那市)に置かれていた高遠(たかとう)藩に、内藤清枚(きよかず、1645〜1714)が入封した頃、石造物の造営がさかんになったことから、藩を挙げて石工の出稼ぎを奨励していたという。この「下地」や「技術力」は但唱の決意当時から、この近辺に存していたのだろう。
話を但唱の作仏に戻そう。但唱の師・弾誓の念仏は「跳踉囀蹶(ちょうろうてんけつ。飛び跳ね、踊り、さえずり、つまずくこと)」「ツムリフリマワス(頭を振り回す)念仏」などと称されるほど、体の動きや声音が激しいものだった。それゆえ、山の近くに住む村人たちからすると、「あやしい人々が何やらあやしいことをやっている」などと恐怖の対象になっていた。それが嵩じ、但唱たちはとうとう寛永11(1634)年、近在の3つの村から信州飯田藩の奉行所に訴えられてしまう。その結果、山から追い出され、仏像も没収されてしまった。しかしその翌年、幕府からのお達しだろうか。仏像が彼らに戻された。この5年後になるが、天海大僧正(1536?〜1643)から但唱は、高輪に開山した如来寺を上野の寛永寺の末寺(まつじ。本山の支配下にある寺のこと)とする許可状や、高位の僧に着用が許される、青色の直綴衣(じきとつい)を但唱が着ても構わないという書状を受け取った。これらは、「保守的」な人にとっては「奇抜」に見える弾誓派の念仏集団が、権威ある天台宗の傘下での存続が認められたことを意味する。以上のことから推察されるのは、但唱らと江戸幕府、そして天海との間には、強いコネクションが存在していたということだ。
苦難を乗り越え再建 大火と「大仏」の蘇り
江戸への「旅立ち」にあたり、五智如来像は一旦解体され、陸路で天竜川まで向かった。そして現在の上伊那郡山吹に所在した小沼(こぬま)の渡しから筏で河口の掛塚湊(かけつかみなと)まで進んだ。そして遠州灘(えんしゅうなだ)に出て、江戸の霊岸島(れいがんじま。現・東京都江東区白河)までは大船で、更にそこから高輪の海岸まで、艀(はしけ。小舟のこと)で運ばれた。五智如来像はおよそ300kmに及ぶ、かなり大掛かりな「旅」を「体験」したことになるが、当時から既に、天竜川流域の材木を江戸や大坂(現・大阪府)に送る「ルート」及び「物流システム」ができていたことに加え、それらを構成する有能な渡し守や船乗りたちを含む、弾誓派の念仏集団を支える信徒たちが天竜川流域、そして遠州灘から江戸まで、手厚く、そして慎重に仏像と但唱一行をサポートしたこと。それによってこの大がかりな「旅」が成功裡に終わったと言える。
その後但唱は高輪の、海を望む小高い土地を見つけ、寺を建てることを望んだ。寛永13(1636)年3月19日、但唱が56歳になった時、ようやくその願いが叶う。高輪大木戸のすぐそば、海岸に面した東海道沿いの、当時は茶店が並び、人の往来が多く、賑わっていたという場所を拝領され、帰命山如来寺(きみょうざんにょらいじ)が建てられた。但唱の苦労が「報われる」格好で、「芝大佛」は多くの人々を惹きつけた。
しかし、享保10(1725)年、延享2(1745)年と如来寺は、2度の大火に見舞われた。その際、但唱たちがつくった五智如来像は、正面から見て一番右に座する「薬師如来像」を除いて、全てが消失してしまったと言われている。その翌年〜宝暦10(1760)年ごろに、つくり直しが行われ、再び、「大仏」は蘇った。
江戸から太平洋戦争末期までの五智如来像
江戸が終わり、明治元(1868)年に出された神仏分離令、廃仏毀釈など、仏教界全体が危機に陥る。その影響を強く受けた如来寺もまた、「高輪」で寺を運営・維持することが難しくなった。そこで、大井村字篠谷(しのやつ。現・品川区西大井)への移転が決まった。そうなると当然、五智如来像は高輪から大井村へ再び、「旅」をすることになった。
また如来寺同様、江戸幕府が開かれるまでは大手(おおて。現・千代田区大手町)に所在し、上野に移転してからは対馬藩主・宗家の菩提寺として厚く庇護されていた養玉院(ようぎょくいん)もまた、同4(1871)年の廃藩置県によって、かつてほど宗家を含む対馬藩関係者からの支援が受けられなくなっていた。それに加え、大正9(1920)年には「文明開化」のシンボルである鉄道敷設のため、移転を余儀なくされていた。そうした状況から、同15(1926)年、如来寺と養玉院は合併し、「養玉院如来寺」として再出発することになった。
そのわずか20年足らず、太平洋戦争末期の昭和20(1945)年5月24日未明、現在の品川区のおよそ7割が灰燼に帰したという「城南大空襲」の影響を受け、またも全焼の憂き目にあった。不幸中の幸いだが、戦中戦後の混乱による再々移転などということにもならず、如来寺は昭和56(1981)年、同63(1988)年に新築された。そして今も、五智如来像はもちろんのこと、寺内に残る但唱の墓や但唱作の石仏2体を含め、存している。それはとてもありがたいことだ。
五智如来が見守る回向文 旅路と祈りの象徴
変転を経て、静かに建つ如来寺の本堂の脇に、1mほどの、「大佛 如来寺」と刻まれた古い石の柱が佇んでいる。その裏面には、「皆が一緒に悟りをひらけますように」という意味の、
願以此功德普及於一切 (願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし)
我等與衆生皆共成佛道 (我らと衆生とみな共に仏道を成ぜんことを)
天台宗の回向文(えこうもん。法要や日々の勤行の後に僧侶が読み上げる文)が彫られている。天竜川から高輪までの長旅を経験した五智如来同様、これから東海道を旅立つ人、長旅から戻った人、そしてそれらの人々を迎え、もてなす人々を、寺の門前で見守っていたのだろうか。
最後に
2012(平成24)年、長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に渡っていた銅製の「観世音菩薩坐像」が今年5月12日、13年ぶりに無事、対馬に戻った。仏像はトラックに乗せられ、仁川(インチョン)国際空港から福岡空港まで運ばれた後、フェリーで対馬に向かった。そしてまた再び、トラックに乗せられ、観音寺に到着した。これはおよそ5時間半以上の長旅だ。窃盗団と共に韓国に渡った「旅」も、大体そのくらいかかったことと推察される。
話は飛ぶが、10代後半の、イギリスの支配階級や貴族の子弟たちが、数ヶ月から2年間ほどイタリアに旅行する「グランドツアー」が17世紀末に始まり、18世紀後半にピークを迎えた。それは子どもから大人への通過儀礼であり、なおかつ彼らが学んできた教養の確立、そしてギリシア・ラテン精神の源流を求め、旅立ったのだ。そのため、時に彼らのチューター役として、著名な哲学者が随行することもあったという。この旅は、貴族たちの交友関係を広め、彼ら自身の人間性向上に役立ったばかりでなく、イギリスという「国」そのものの文化や精神風土をも豊かにしたという。
このような「旅」であれば、実に有意義である。しかしまた再び、観世音菩薩像も、五智如来像も、社会状況に翻弄される形の「旅」をしないことを祈るばかりである。
参考資料
■景山到恭・戸松昌訓・井上能知(編)『江戸切絵図』1849〜1862 尾張屋清七
■磯ヶ谷紫江「伊皿子の墓」『墓碑史蹟研究』第26号 1925年(251-255頁)墓碑史蹟研究発行所
■東京市芝區役所(編)『芝區誌』1938年 東京市芝區役所
■滝沢貴杯・向山勤弥「景観の変遷(高輪)」東京都港区文化財調査課(編)『港区の文化財 第6集 高輪・白金 その1』1970年(3-30頁)東京都港区教育委員会社会教育課
■石川悌三『東京の坂道 –生きている江戸の歴史』1971年 新人物往来社
■東京都港区役所(編)『新修 港区史』1979年 東京都港区役所
■宮島潤子『信濃の聖と木食行者』1983年 角川書店
■長谷川正次(監修)東京都港区立みなと図書館(編)『文政のまちのようす 江戸町上書上(二)芝編 下巻』1985年 東京都港区立みなと図書館
■白石つとむ(編)『江戸切絵図と東京名所絵』1993年 小学館
■大隅和雄「木食上人」下中弘(編)『日本史大辞典 第6巻』1994年(712-713頁)平凡社
■西海賢二『漂泊の聖(ひじり)たち –箱根周辺の木食僧–』1995年 岩田書院
■馬淵和夫・国東文麿・稲垣泰一(校注・訳)『新編 日本古典文学全集 35 今昔物語集 1』1999年 小学館
■有限会社平凡社地方資料センター(編)『日本歴史地名大系 第13巻 東京都の地名』2002年 平凡社
■「シリーズ 過去の災害に学ぶ 第2回:1657 明暦江戸大火」『ぼうさい』No.26 2005年3月号 内閣府
■「田中圭一講演集 第8集 東京佐渡三田会郷土史研究会編:佐渡の木食上人」『首都圏佐渡連合会』2005年11月27日
■「法話集 No.33 願以此功德 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道(がんにしくどく ふぎゅうおいっさい がとうよしゅじょう かいぐじょうぶつどう)」
■『天台宗』2006年11月30日
■岡田温司『グランドツアー 18世紀イタリアへの旅』2010年 岩波書店
■小杉達「掛塚港の『みなと文化』」『港別みなと文化アーカイブズ』2011年5月10日
■山野勝「東京歴史ウォーキング 江戸の坂道散策 伊皿子坂(港区)」東京土木施工管理技士会(編)『DOBOKU技士会 東京』第54号 2012年12月号(11頁)東京土木施工管理技士会
■岡本哲志「品川」陣内秀信+法政大学陣内研究室(編)『水の都市 江戸・東京』2013年(146-157頁)講談社
■品川区立品川歴史館(編)『平成25年度特別展 大井に大仏(おおぼとけ)がやってきた!養玉院如来寺の歴史と寺宝』2013年 品川区立品川歴史館
■豊島修「解説」五来重『円空と木喰』1997/2016年(312-317頁)株式会社KADOKAWA
■荻原稔「幕末の天台宗に伝わった井上正鐡の『信心』の系譜」『中外日報』2016年11月4日
■中島俊郎『英国流 旅の作法 グランド・ツァーから庭園文化まで』2020年 講談社
■「第64回 特別展 信州ゆかりの作仏聖 –弾誓派から円空・木喰へ–」『博物館だより』第119号 2021年9月30日 長野市立博物館
■「のぼりくだりの街(2)伊皿子(いさらご)坂(港区) 渡来人も見た絶景!?」『東京新聞』2021年10月2日
■「信州の山にこもった木食『但唱(たんしょう)』とは?」『Skima信州』2023年2月3日
■岩本憲治『木食の地から 但唱・閑唱』2023年 いわもとぷろ
■岩本憲治「《講演録》木食の地から 但唱・閑唱の足跡」『須高』第97号(1-14頁)2023年10月20日 須高郷土史研究会
■木下守「松本の石造文化史を考える −但唱と高遠石工−」『信濃』第76巻(75-87頁)2024年1月20日 信濃史学会
■「対馬仏像、韓国での『法要』終了 瑞山・浮石寺、10日に日本側へ」『KYODO』2025年5月5日
■「対馬仏像、日本へ引き渡し 韓国浮石寺、盗難12年半で解決」『KYODO』2025年5月10日
■「盗難仏像、韓国の浮石寺で観音寺側に引き渡し 『和気藹々と終わった』…13年ぶりに長崎県対馬市に」『読売新聞オンライン』2025年5月11日
■「対馬で盗まれた仏像、13年ぶり観音寺に戻る…韓国から到着」『読売新聞オンライン』2025年5月12日
■「観音寺総代長 『やっと取り戻したよ、と言いたい』父の遺影手に…盗まれた仏像が13年ぶり韓国から長崎・対馬市の寺に 歓迎の法要営まれる」『FNNプライムオンライン』2025年5月12日
■「盗難仏像『観世音菩薩坐像』が長崎県対馬市で特別公開…『優しいお顔。おかえりを喜んでおられるようだ』」『読売新聞オンライン』2025年5月16日
■「伊皿子坂」『港区』
■「大井の大仏」
■「掛塚湊の碑(竜洋海洋公園内)」『磐田市観光協会』
■「かつては海を望む別荘地、歴史の色濃き高級住宅街『高輪』を巡る」『Curiosity』
■『しながわ平和のための戦争展』
■「高輪地区の旧地名 三田台公園」『港区』
■『高輪 正源寺』
■「天竜川」『国土交通省』