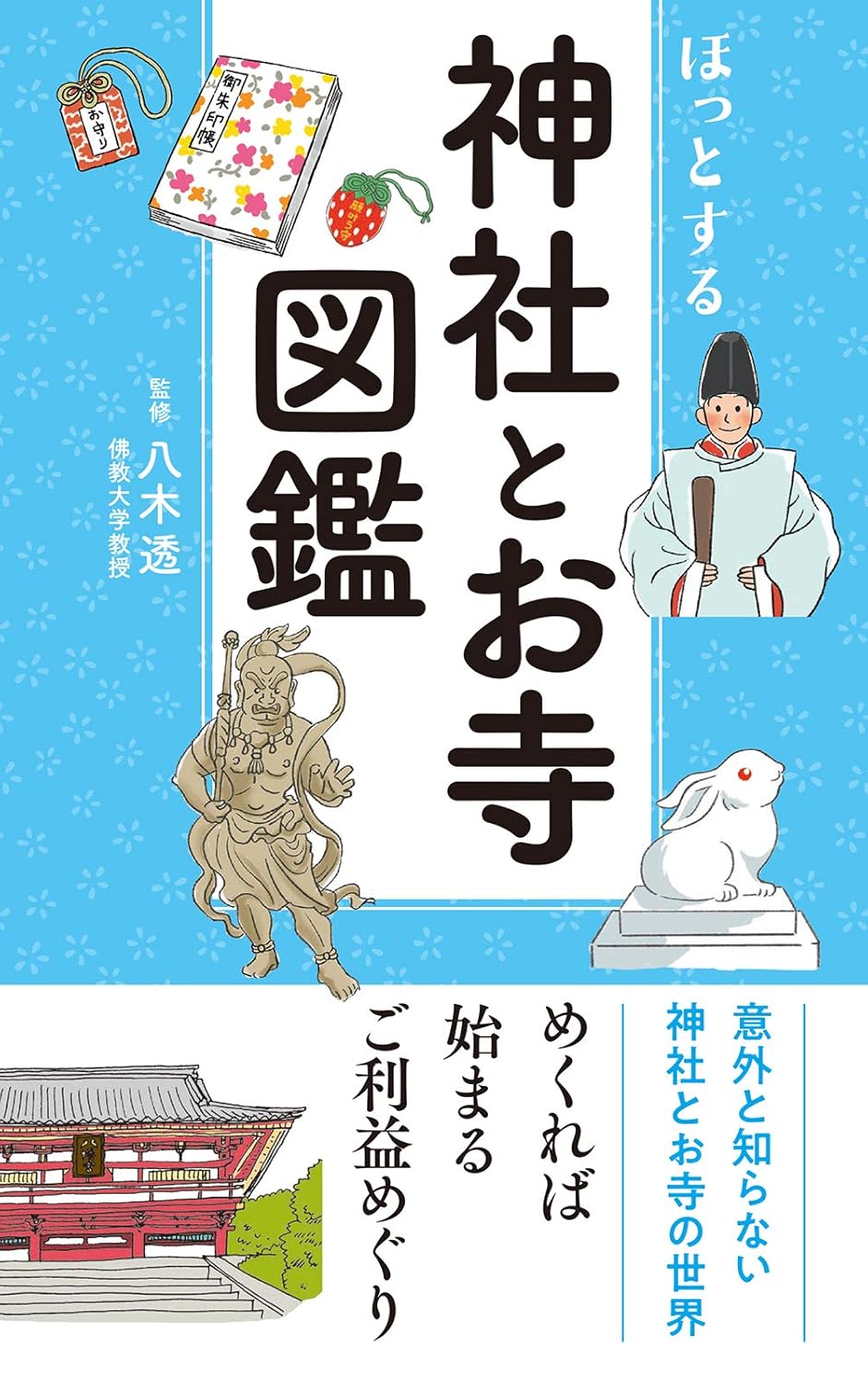いわゆるパワースポット、癒し、ヒーリングといった効果を求めて人々が訪れる場所として紹介されるのは、どちらかというと寺より神社の方が多いように思われる。有名な寺はともかく、街を歩いていて神社を見かけ散策することはあっても、寺に足を踏み入れることはあまりないのではないか。神社仏閣は2大宗教空間として日本人の生活に根ざしているが、神社は生命に満ちた「陽」、寺院は死を感じる「陰」の存在だといえる。

「陰」の寺院
僧侶によるターミナルケア、つまり終末期患者の心を癒すケアである「ビハーラ」を普及する運動がいまひとつ盛り上がっていない。僧侶や諸宗派の怠慢も指摘したいところだが、病院で僧衣を見た人が死を連想し、抵抗を感じるのは無理はないことだろう。寺には「癒し」とは真逆の「死」のイメージが根強い。筆者の父は母が入院する病院に向かう際、道のりにある菩提寺を避けた。失礼な気もしたが気持ちは理解できる。寺には墓がある。つまり遺骨が埋まっている。実は境内に墓の無い寺も少なくないのだが、一般的に寺と墓、寺と死の関係は切っても切れない。高野山のような観光地として知られる有名な場所は別として、法事や墓参り以外には、あまり墓地には立ち入りたくないのは本音ではないだろうか。
そもそも穢れを忌避され路上に打ち捨てられた死体を、心ある遁世僧(国家公務員である官僧ではない私僧)が供養したことから、仏教と葬儀が結びついた。仏教は自ら「陽」から「陰」に入ったのである。死が「気枯れ」であるなら、癒しにこれほどマイナスな存在はない。対して穢れを徹底的に遠ざけた神社にはお宮参りや七五三などがおこなわれ、生命力が溢れている。癒しや開運を求める人たちが向かうのは、やはり相対的に神社に軍配が上がるようだ。
「陽」の神社
11月15日、三笠宮妃である崇仁親王妃百合子殿下が薨去(こうきょ)された。慣例により天皇皇后両陛下、上皇上皇后両陛下は一連の葬儀の儀式には参列されなかった。後日一般的な礼拝を行ったとのことである。国の頂点である天皇(上皇)陛下は先帝を弔う以外の葬儀には勅使、名代が参列するのがしきたりである。その元々の起源は、天皇が神道の盟主であり祭祀王であるから、死は穢れとして忌避するというものだった。現代では外国のエリザベス女王の葬儀や、今回も通夜には参列されるなど、昔日ほど厳密に守られてはいないようだが、皇族の正式な儀式となればやはり通例通りになるのだろう。
神道、神社は徹底して「陽」の存在である。死は穢れであり死体は不浄なものとして避けられる。また「穢れ」は「気枯れ」ともいい、生命力の消失を意味する。つまり「陰」として忌避する。とはいえ、神社でも「神葬祭」と呼ばれる神式葬儀を行なうことがある。儀式によって「穢れ」を払い、枯れた気を取り戻した故人は、先祖と共にその家を護る「神」「祖霊」になるとされている。彼らを年の始めに迎えるのが正月である。しかし、その「神葬祭」も、神域である神社では行わない。死体を境内に持ち込むことは絶対にあり得ないのである。
「神棚封じ」という慣習がある。地域にもよるが通夜などの際、神棚の扉が閉じられ、白い和紙が張られる。これは神棚に鎮座する神に死を触れさせないための慣習で、「神葬祭」の際にも「神棚封じ」は行われる。やはり神社に「死」を持ち込んではいけないのだろう。神社は明るい「ハレ」の場、「陽」の場なのである。
本尊との対話
「陰」である寺は建物の造りとしても閉鎖的な空間で、森の延長のような神社より入りにくい雰囲気がある。檀家以外はお断りのような寺も少なからず存在する。だからといって寺を避けるのはもったいない。神社との大きな違いに本尊の存在がある。元々神道は自然崇拝なので、基本的に神社のご神体は具体的な姿形はなく、鏡や剣など神が宿る「依代」である。神像というものもあるが、これは仏教の影響で作られたもので、その多くは一般公開されていない。人は形があるものの方が感情を入れやすく、感情を投影しやすい。例えば不動明王の憤怒は「憎しみ」でなく「怒り」を表すという。本尊と向き合い手を合わせる時間は、本尊との対話の時間でもある。西行が伊勢神宮で「何事のおはしますをば知らねども かたじけなさに涙こぼるる」と詠んだように、神社はご神体との直接の触れ合いは無いが、空間自体から神性を感じる場である。寺の境内にも神性な雰囲気はもちろんあるが、阿弥陀さまやお不動さまら、表情を持って迎えてくれる本尊との触れ合いこそが寺の本領であるといえる。しかし、本尊がいる本堂は寺によっては扉が締めきっていたり、許可を得なくてはならない場合がある。神社はご神体のいる本殿には元々入れることはできず、そのために拝殿が用意されている。この点でも神社の方が開放的ではある。
寺に行ってみる
神社仏閣は陰と陽の性格を持ち互いを補ってきた。本来そこに優劣は存在しないが、寺に対するある種の暗いイメージは拭い難い。それは結局、死は穢れであると考えているからだ。だが「陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転ず」と言われる。生は死へのカウントダウンであり、死は新たな再生の始まりであると考えれば、死を忌避し恐れることもなくなるかもしれない。寺に行けばその考えに至る道筋を、ご本尊が教えてくれるはずである。
拙稿
■神と仏が同居する国 日本における神と仏の役割分担・棲み分け
■「死の世界」を遠ざけてきた現代神道の歴史と課題
■江戸時代の檀家制度 明治時代の神仏分離令と廃仏毀釈 そして現代の神仏習合