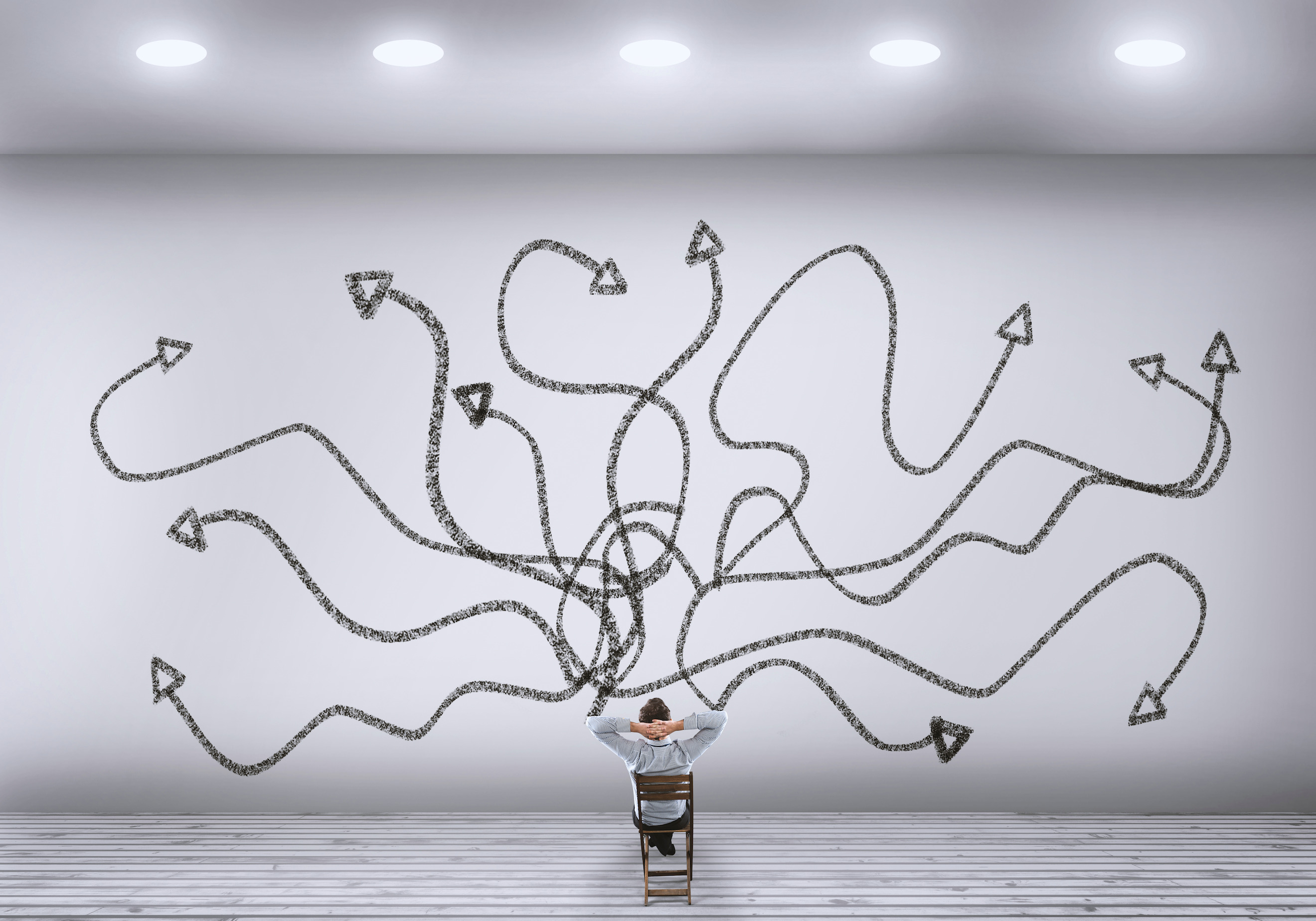自ら命を絶つには相応の理由があるだろう。人それぞれの事情があるとしかいえないが、その昔「哲学的煩悶」によって、この世を去った若者がいた。彼はなぜ死んだのか。彼の死が社会に与えた影響とは。

「不可解」の絶望 若き哲学徒の遺書が社会に与えた衝撃
明治36年(1903年)旧制一高の学生、藤村操(1885-1903)が日光・華厳の滝から身を投げた。享年17歳。藤村は身を投げる際にミズナラの木に「巌頭之感」と題する遺書を墨書した。これが新聞紙上に写真と共に発表され大きな反響を呼んだ。その内容は、若き哲学徒が「煩悶」の末に、人生の真理は「不可解」であるという結論に達っした絶望が綴られていたものである。当時の社会に大きな衝撃を与え、多くの若者が藤村の後を追うことになった。こうした影響を配慮してか、当局はこの木を伐採した。影響を受けたのは若者だけではない。特に文学者たちの関心は高く、様々な論文や考察が発表された。「巌頭之感」の全文は以下の通りである。
「巌頭之感」の全文
悠々たる哉天壌。遼々たる哉(かな)古今。五尺の小躯を以て此大をはからむとす。
ホレーショの哲学 竟(つい)に何等のオーソリチィーを價(あたい)するものぞ。
万有の真相は唯一言にして悉つくす。曰く「不可解」。
我 恨(うらみ)を懐いて 煩悶 終(つい)に死を決するに至る。
既に巌頭に立つに及んで、胸中何等の不安あるなし。
始めて知る、大なる悲観は大なる楽観に一致するを。
巌頭之感の意訳
聞き慣れない「ホレーショの哲学」については、当時から議論されていた。ホレーショとは、「ハムレット」に登場するホレーショのことであるとの説、古代ローマの詩人ホラティウスの「nil admirari(ニル・アドミラリ)」「何事にも驚かない」という態度を指しているという説などがある。この世の真理はどれほど考えても不可解であり、答えには到達し得ない。故に死を決意した。もはや何の不安もない。絶望は解放への入口なのだ。といったところだろうか。このいかにも「哲学的」な文を遺し、藤村はこの世を去った。センセーショナルな事件だが、当時の社会にそれだけでは収まらない余波が襲いかかった。
知識人たちの思索 藤村の死をめぐる賛否両論と多様な解釈
藤村の死について世間の大半は批判的だった。これは当然で表立って自殺を容認することはできないだろう。その一方で、知識人、特に文学者たちは藤村の死について様々な論文や考察を発表する。「萬朝報」創設者・黒岩涙香は「我国に哲学者なし、この少年に於て始めて哲学者を見る」と彼の死を「哲学的自殺」と定義づけた。仏教学者・亀谷聖馨は「巌頭之感」を簡潔にして高妙と賞揚した上で学んだのが懐疑論的な哲学ではなく仏教なら死ぬことはなかったと惜しんだ。
堀正士(早稲田大学)は、藤村が大うつ病性障害に罹患したため心理的視野狭窄に陥り、自己を追い込んでしまった末の自殺であったと考えるのが妥当であると述べている。藤村の死には失恋説も存在しており、多感な時期であることを考えれば、実際の理由はそんなところだったのかもしれない。つまり藤村の自殺自体は精神疾患などによる偶発的事件に過ぎなかった可能性が高い。
だが、生活苦のような俗なことではなく、哲学的・観念的な理由で死を選んだ若者の行為は、観念の世界に生きる文学者たちによって多様な意味付けが成された。もちろん自殺の美化するような言説には批判もあり、知識人や報道人たちの言論空間は喧々諤々となった。
後追い心理の連鎖 若者たちの「ウェルテル効果」と「煩悶」の時代
その一方で、同世代のある種の若者達は、彼が装飾した「哲学的自死」を字義通りに受け取った。彼の死後、多くの若者達が後を追う形で同じ場所から身を投げたのである。4年間で185名が自殺を試み、そのうち40名が死亡したという。そうした「追随者」は藤村と同じ知的エリート学生に多かった。この時代、生きる価値とはなんなのか、人生に意味などないのではないかと、人生観が揺さぶられていた「煩悶青年」と呼ばれる若者が相次いでいた。彼らの間でいわゆる「ウェルテル効果」と呼ばれる、後追い心理が広まった可能性がある。
立身出世が美徳とされていた当時の社会において、将来を約束されたエリート学生が人生に対して「煩悶」し自殺した事実は、同世代の知的学生たちを震撼させた。自死した中には藤村のように煩悶もせず、のうのうと生きていることを恥じたとする者もいた。追随者の1人である女学生は「我をして徒らに藤村操を學ぶものとなす勿れ」と遺書で述べているが、藤村の存在が彼女の煩悶に行為を促してはいないとは言えない。
自分は何のために生きているのか。生きる意味などあるのか。若者なら一度はそのような哲学的な問いを抱くものである。まして知的階級にある学生なら様々な文学、思想に触れ、そうした煩悶はより深まったことだろう。だが大概は成長と共に現実社会にすり合わせて終わる。藤村の死は、観念的な煩悶に自死という実践行為にまで進ませる起爆剤になってしまったのである。
彼女の死を受けた母校は、生徒に哲学書を読むことを禁じた。文芸評論家の亀井勝一郎は哲学を学びたいことを両親に話すと「藤村操のように自殺するからいかん」とはねつけられたという。それほど藤村の死は衝撃的だった。哲学的な死の理由を大書して滝に身を投げる、派手な演出に近い死に方が社会に与える影響を当の本人はどこまで自覚していただろうか。
憧れとしての死 哲学と感情が交錯する自殺の美化か
藤村の死の真相は本人以外知る由もないが、自殺を美化するのような言説は疑問である。とはいえこの一連の騒動には、本来忌避されるはずの「死」に対し、ある種の憧れのような感情が見える。だが実は感性的な文学者に比べて理論的な哲学者の自殺は少ない。カントもヘーゲルも長生きし、年齢を重ねると共に思索も深まっていった。何を考え悩もうと死はやがて必ず訪れる。早急にならず、じっくり向き合って生きていくべきである。
参考資料
■平岩昭三「検証藤村操: 華厳の滝投身自殺事件」不二出版(2003)
■堀正士「藤村操の『哲学的自殺』についての精神病理学的一考察」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』第22号 早稲田大学(2002)
■高橋新太郎「『巌頭之感』の波紋」『文學』第54巻第8号 岩波書店(1986)
■拙稿 自己のあり方に悩む若者から絶大な人気を得た思想家・綱島梁川