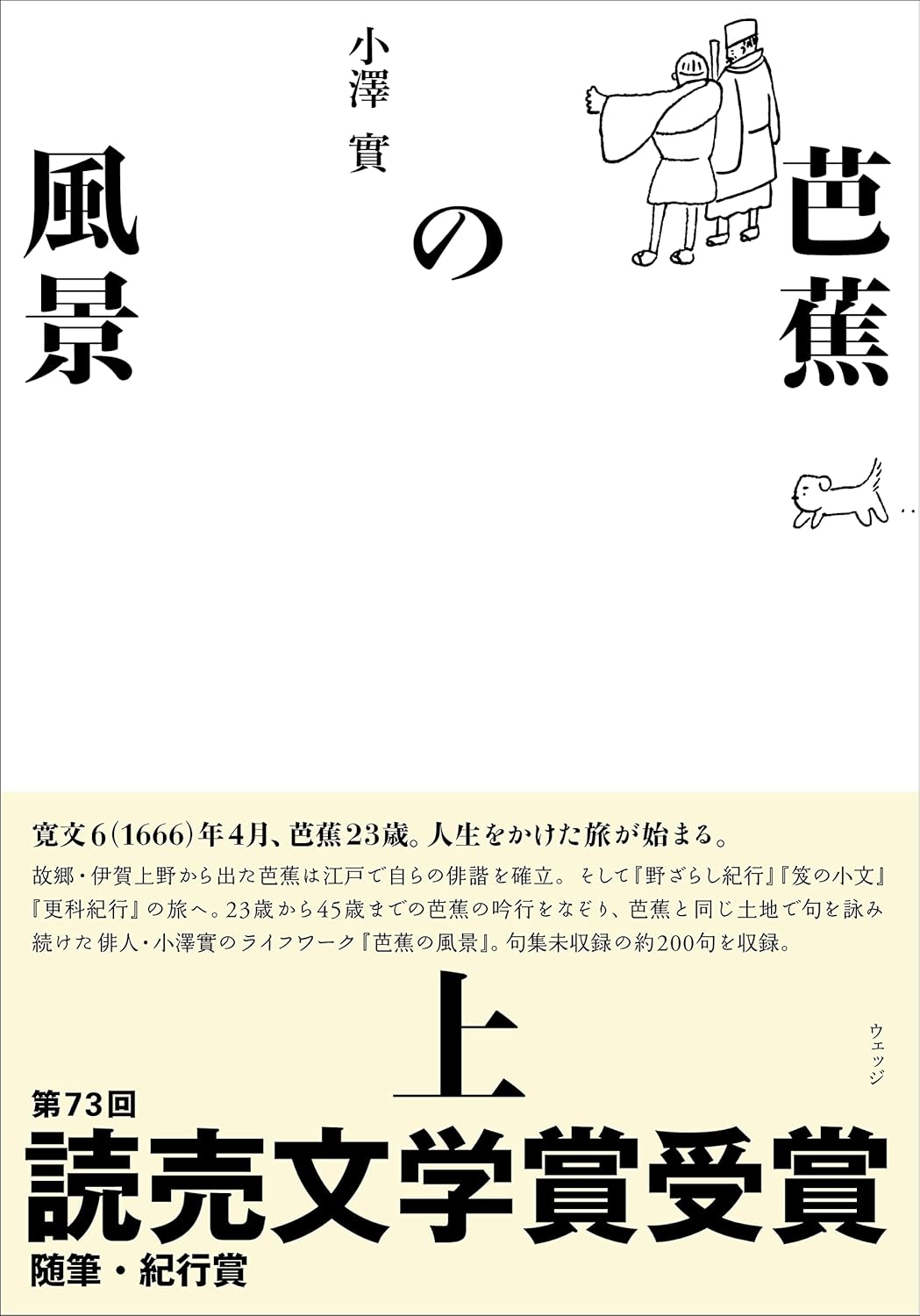昨年の11月13日に日本を代表する詩人・谷川俊太郎(1931〜2024)が亡くなった。谷川の代表作として1971(昭和46)年につくられた、「生きているということ」から始まる、「いま生きているということ/それはのどがかわくということ/木漏れ日がまぶしいということ…」など、39行にも及ぶ、「生」の喜びを数多く挙げた長編の詩『生きる』は、時代や世代を超え、多くの人に愛され、勇気づけてきた。

愛されすぎた松尾芭蕉
今年の2月20日に百か日忌を迎えたばかりであるので、全国津々浦々の「谷川ゆかりの地」に「記念碑」「詩碑」などがつくられるのは、まだまだこれから先のことだろう。しかしそうした中に、遺族の手による、地下に骨壷が埋葬されたものではなく、谷川と知己のあった人々によって、生前の谷川を讃え、なおかつ追悼するための『谷川俊太郎之墓』が建立されるということは、今の日本の文化・慣習において、まずあり得ないことだろう。しかし、そのような「墓」が、郷土史家の田中昭三(1929〜2000)による調査・検証によって、1990(平成2)年時点で、日本全国に134基も建てられていた人物がいた。それは江戸時代前期(1603〜1690)に活躍し、後に俳聖と称された松尾芭蕉(1644〜1694)だ。
松尾芭蕉の墓の所在地

松尾芭蕉の俳句といえば「古池や 蛙飛び込む水の音」か。それとも「夏草や兵どもが夢の跡」か。「好き嫌い」はともかく、これらの俳句は多くの日本国民がすぐ、「芭蕉といえば…」で、連想するものだ。もちろん、江戸時代なら与謝蕪村(1716〜1784)、小林一茶(1763〜1828)。明治に入ってからは正岡子規(1867〜1902)など、偉大な俳人は他にも存在するが、芭蕉の場合は特に、「旅に病んで 夢は枯野をかけ廻る」(1694年)ではないが、世のあまたの、春夏秋冬の折々を俳句に託した俳人たちよりも、「旅」「移動」「漂泊」。そして道中で行き倒れてしまい、誰にも気づかれることなくそのまま亡くなってしまう。更に遺体が腐敗し、白骨化するまで放置されたままであることを想起させる「野ざらし」などのイメージが強烈だ。
そんな芭蕉だが、いわゆる普通の「墓」は、生前の遺言通り、亡くなった大坂・南御堂前(現・大阪府大阪市中央区)から、彼が慕った武将・木曽義仲(1154〜1184)の墓がある滋賀県大津市馬場の義仲寺(ぎちゅうじ)まで運ばれ、埋葬された。その後、芭蕉の親族や門人たちによって、松尾家の菩提寺である愛染院(現・三重県伊賀市農人町)に、遺髪が納められた「故郷塚」が建てられた。
各地に建てられた松尾芭蕉の顕彰墓

それでは、遺体や髪などが納められていない、松尾芭蕉を顕彰するための「墓」とは一体何なのか。芭蕉の句の数々に比べれば、ほとんどの人々に「知られていない」ものではあるが、例えば、福岡県福岡市東区馬出(まいだし)の路地裏に、『芭蕉翁之墓』と刻まれた、高さ70cmほどの茶色い自然石でできた「墓」がある。「枯野塚」と呼ばれている。「ここ」でかつて、博多の僧侶で俳人の松月庵哺川(しょうげつあんほせん、1633〜1713)が庵を結んでいた。自身に地縁がある福岡、そして九州に「蕉風」を広めようと訪れていた、「蕉門十哲」と称された芭蕉の弟子・向井去来(むかいきょらい、1651〜1704)から哺川は1700(元禄13)年頃、生前の芭蕉が最後に詠んだ、「旅に病んで…」の懐紙―しかもそれは実際に床に臥していた芭蕉の枕元で書き留められた貴重なもの―を受け取った。そこでそれを地中に埋めて、「塚」或いは、両墓制(りょうぼせい)における、地下に遺体などが埋められ、それゆえに「穢れたもの」と捉えられていた「埋め墓」とは異なり、清浄な魂をお祀りしたお参りのための墓、「詣墓(まいりばか)」を建てた。墓石の揮毫は、同じく「十哲」の志田野坡(しだやば、1662〜1740)が手がけたものだ。
松尾芭蕉を慕う俳人らによる追善供養を目的とした墓
今日の感覚では、「芭蕉のお墓がどうして福岡の『ここ』に?」「お墓は普通、お寺にあるんじゃないの?」などと、思わず驚いてしまうが、元・国鉄マンで郷土史家の川上茂治(1933〜)によると、「初期の芭蕉塚には、芭蕉を慕う俳人らの敬虔な気持から追善供養した、墳墓形式のものが多かった」という。墓の右奥には「旅に病て(原文ママ)夢は枯野をかけめくる(原文ママ)」と彫られた、1893(明治26)年、芭蕉の二百回忌を祈念した、高さ2.5m、幅40cmの「枯野塚」も建てられている。とはいえ芭蕉の「墓」の左隣には『哺川菴主之墓』こと、先に登場した哺川の墓がある。また、芭蕉の「墓」の右側には、旧・福岡城における「お綱の祟り」で知られる、麻井おつな(?〜1630)と彼女が手をかけた2人の幼な子の墓が並んでいることから、「ここ」は「墓地」でもあったと考えられる。だが、例えば芭蕉が亡くなってから十回忌にあたる1704(宝永元)年に、野坡が「ここ」を再訪したことをきっかけに、哺川は芭蕉追悼のための句集『枯野塚集』の企画を立て、翌年に完成させたりした。このように『芭蕉翁之墓』は、「墓」本来の目的である個人を偲ぶための「場」であることに加え、芭蕉の句、或いはその思想を弟子たちが九州圏の俳壇に伝え、それを受けて地元で活躍している多くの俳人たちとの交流が図られるための大切な「依代」でもあったと推察されている。
そもそも墓とは一体何なのか
では、そもそも「墓」とは何なのか?権力の中枢が貴族から武士に移り変わる、変革の時期ならではの政情不安定を写し出したかのような絵巻物、『餓鬼草子』(12世紀半ば頃)第4段には「墓」が描かれている。絵を注視すると、高雅な身分の人の墓と思しきものは、盛り土の上に塔婆が立てられていたり、むやみな「立ち入り」を制限するかのように柵が設けられ、その中心に立派な宝塔(ほうとう)が建てられていたりする。一方で道端には、まだ「人の姿」の遺体が転がっていたり、或いは白骨が散らばっていたり、野犬が棺の中の遺体に喰らいついていたりする。「今」の我々がこの絵を見ると、恐怖と嫌悪感で思わず目を背けてしまうかもしれないが、「当時」であれば、この絵の状況が当たり前だったのだろう。
何故「当たり前」だったのか?それは、日本においては古来より「言霊」という言葉・思想が存在するように、霊魂に対する信仰、或いはそれを「重視」する傾向があった。その反動で、結果的に肉体を「軽視」してしまい、人里離れた山野や海辺に遺体を打ち捨てても、「魂」を大切にお祀りしているから「構わない」と思う傾向があった。それは「今」でも変わらないかもしれないが、ある個人の何もかもを「強制終了」させてしまう「死」を「穢れ」として極度に恐れ、できる限り忌避したい気持ちが強かったことも影響しているだろう。もちろん、支配者層に関していえば、3世紀半ば頃から中国大陸や朝鮮半島から伝来し、造営が始まったという巨大古墳に手厚く埋葬されてはいるが、一般庶民の場合、各々の埋葬地に石を立てるようになったのは、15世紀後半になってからのことである。
葬法も増えていった
またその間に、死後の体を「野ざらし」にする風葬ばかりでなく、土葬や火葬を行うようになった。民俗学者の五来重(ごらいしげる、1908〜1993)は、阿弥陀聖と称される空也(903〜972)が「曠野古原(こうやこげん。荒れ果て、人が近づかない古くからの野原)に委骸(いがい。遺骸のこと)があれば、それをひと所に集めて、油を注いで焼いて、阿弥陀仏の名前を唱える」と、今日で言う葬送儀礼を行った意義として、一般大衆からすると、人が死に、腐乱した姿のままでは極楽往生できないという思い込みが強く、それがために「火葬による浄化」を行ったのではないか、と指摘している。土葬・火葬が普及してからは、極度に崩壊・変容した遺体を人々が巷で目にする機会が「減った」ことから、古代〜中世に比べると人々の「死」への嫌悪感や忌避感がいくらか和らいでいったとも、言われている。
しかも『芭蕉翁之墓』がつくられた江戸時代(1603〜1868)は歴史学者の関根達人(1965〜)曰く、「墓石時代」だと指摘する。つまり、上は将軍・大名から、下は一般市民まで、墓石を建てるようになった。しかもその頃から、個人墓・夫婦墓だったものが家族墓へと移行し、それに伴い、墓石を立てることが普及した。しかも当時の人々の識字率も高かったことから、墓石に文字を刻むことが「当たり前」になったというのだ。今日我々がイメージする「墓石」の代表格である、「方柱(ほうちゅう。四角の柱のこと)墓石」はこの頃に登場した。それが『餓鬼草子』に描かれていた宝塔系のものなどを駆逐し、多勢を占めるようになってから、今日に至っている。当時、『芭蕉翁之墓』のような自然石は、なきにしもあらずだったものの、いつしかあまり用いられなくなっていったという。
人が墓を建てるようになった理由
評論家の戸井田道三(といだみちぞう、1909〜1988)は『忘れの構造 新版』(1984/2024年)の中で、人が墓石を建て始めた理由について、人間の忘却と関連があるとして、以下のように述べていた。
「人の命のはかなさにくらべて石の不変性をよく知っていたのだ。腐敗しやすい肉体に対して容易に変化しない石とその重さが対比され、肉体を離れて浮遊する霊魂を土中にしずめるため、と同時に、石によって記憶を外在化しておけば安心して忘却にまかせられるために石が利用されたのだ。
人の名をしるす墓は歴史が新しい。征夷大将軍源頼朝の墓でも貧弱な五輪の石にすぎない。名はきざんでないのである。五輪の石のあらわすものは地・水・火・風・空である。石の固さが風や空を指示するところに考えねばならぬものがあるようだ。」
最後に
芭蕉にとって、死後に福岡・馬出という、自身が訪れたことがなかった「場所」に『芭蕉翁之墓』が建てられるとは、思いもよらなかったことだろう。しかし戸井田が言う、「容易に変化しない石」にその名が刻まれ、九州の俳人たちから大切に守られていたこと。それと同時に、明治〜大正〜昭和〜平成〜令和と、壊されることなく保存されてきたとはいえ、「忘却にまかせられ」てもいたことを思うと、まんざら「悪い気」はしないのではないか。もちろん芭蕉は、「墓」の中におとなしくとどまってはいない。死を目前にしていた当時思い描いた夢、例えばまた再び、全国津々浦々の旅に出ること。自身が極めた「蕉風」を超えた新しい句をもっとたくさん生み出したいという創作欲などを叶えるべく、今も日本全国津々浦々を駆け巡っていることだろう。
参考資料
■出口対石『芭蕉塚』1943年 長崎書店
■杉浦正一郎「九州蕉門の研究(1)枯野塚と『枯野塚集』」九州大学大学院人文科学研究院
■(編)『文學研究』第45号 1953年(82-121頁)九州大学大学院人文科学研究院
■杉浦正一郎「九州蕉門俳諧史概説:元禄年間まで」九州大学大学院人文科学研究院
■(編)『文學研究』第49号 1954年(1-47頁)九州大学大学院人文科学研究院
■尾形仂『日本詩人選 17 松尾芭蕉』1971年 筑摩書房
■川上茂治(編著)『九州の芭蕉塚』1974年 佐賀出版社
■川上茂治「“九州の芭蕉塚”をさぐる(上) ―第4回旅客営業研究発表より―」『運輸界』1974年2月号(63-66頁)中央書院
■川上茂治「“九州の芭蕉塚”をさぐる(下) ―第4回旅客営業研究発表より―」『運輸界』1974年3月号(71-74頁)中央書院
■藤井正雄「葬制と墓制」金岡秀友・柳川啓一(監修)菅沼晃・田丸徳善(編)『仏教文化事典』1989年(714-722頁)佼成出版社
■田中昭三「芭蕉塚について」『芭蕉塚蒐』1990年11月28日
■井之口章次「墓制」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典 第12巻』1991年(726-727頁)吉川弘文館
■田中昭三(編著)『芭蕉塚蒐 六』1993年 近代文芸社
■日外アソシエーツ(編)『詩歌人名辞典 新訂第2版』2002年 日外アソシエーツ
■「萬盛堂歳時記 vol.62 枯野塚」『石村萬盛堂』2005年12月 https://www.ishimura.co.jp/saijiki/61_70/vol_62.html
■五来重『五来重著作集 第11巻 葬と供養(上)』2009年 法藏館
■「草日誌 生きる」『信陽堂編集室』2011年7月23日
■大輪靖宏『なぜ芭蕉は至高の俳人なのか』2014年 祥伝社
■「福岡歴史探訪 第8回 枯野塚」『福岡教育連盟』2014年9月30日
■山辺信男「歴史さんぽ 馬出の史跡 芭蕉の『枯野塚』(馬出)」『東区歴史街道を往く』Vol.4 2017年3月(16頁)東区歴史ガイドボランティア連絡会「歩歩歩(さんぽ)会」
■白石悌三「松尾芭蕉」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典 第12巻』1992/2018年(102-103頁)吉川弘文館
■関根達人『歴史文化ライブラリー 464 墓石が語る江戸時代 大名・庶民の墓事情』2018年 吉川弘文館
■東区歴史ガイドボランティア連絡会「歩歩歩(さんぽ)会」(編)『箱崎・馬出地区歴史ガイドマップ 筥崎宮と古民家の残るまち 箱崎・馬出』2008/2012/2019年 福岡市
東区総務部 生涯学習推進課
■眞杉泰輝「芭門九州伝播考 −支考と野坡と正教寺−」『東洋大学大学院紀要 文学研究科<国文学>』第55号 2019年(39-55頁)東洋大学大学院
■「松尾芭蕉の墓が馬出にある?!」『三好不動産』2020年5月26日
■鵜飼秀徳『絶滅する「墓」 日本の知られざる弔い』2023年 NHK出版新書
■戸井田道三『忘れの構造 新版』1984/2024年 筑摩書房
■「松尾芭蕉の有名な俳句10選 季語と意味も一挙に解説」『ノミチ』2024年2月26日
■「義仲寺」『滋賀・びわ湖観光情報』2024年4月1日
■「詩人の谷川俊太郎さん死去 『二十億光年の孤独』『生きる』など」『NHK』2024年11月19日
■「愛染院 故郷塚」『忍びの国 伊賀を発見』
■「伊賀の歴史探訪 芭蕉翁故郷塚 愛染院」『伊賀市 デジタルミュージアム 秘蔵の国 伊賀』
■「お綱門」『日本伝承名鑑』https://japanmystery.com/fukuoka/otunamon.html
■「餓鬼草子」『東京国立博物館』
■「餓鬼草子」『八景DIGITAL ART CUBE』
■「枯野塚」『福岡市の文化財』
■「墓場と餓鬼」『林正樹ホームページ』
■「芭蕉終焉の地」『大阪中心』