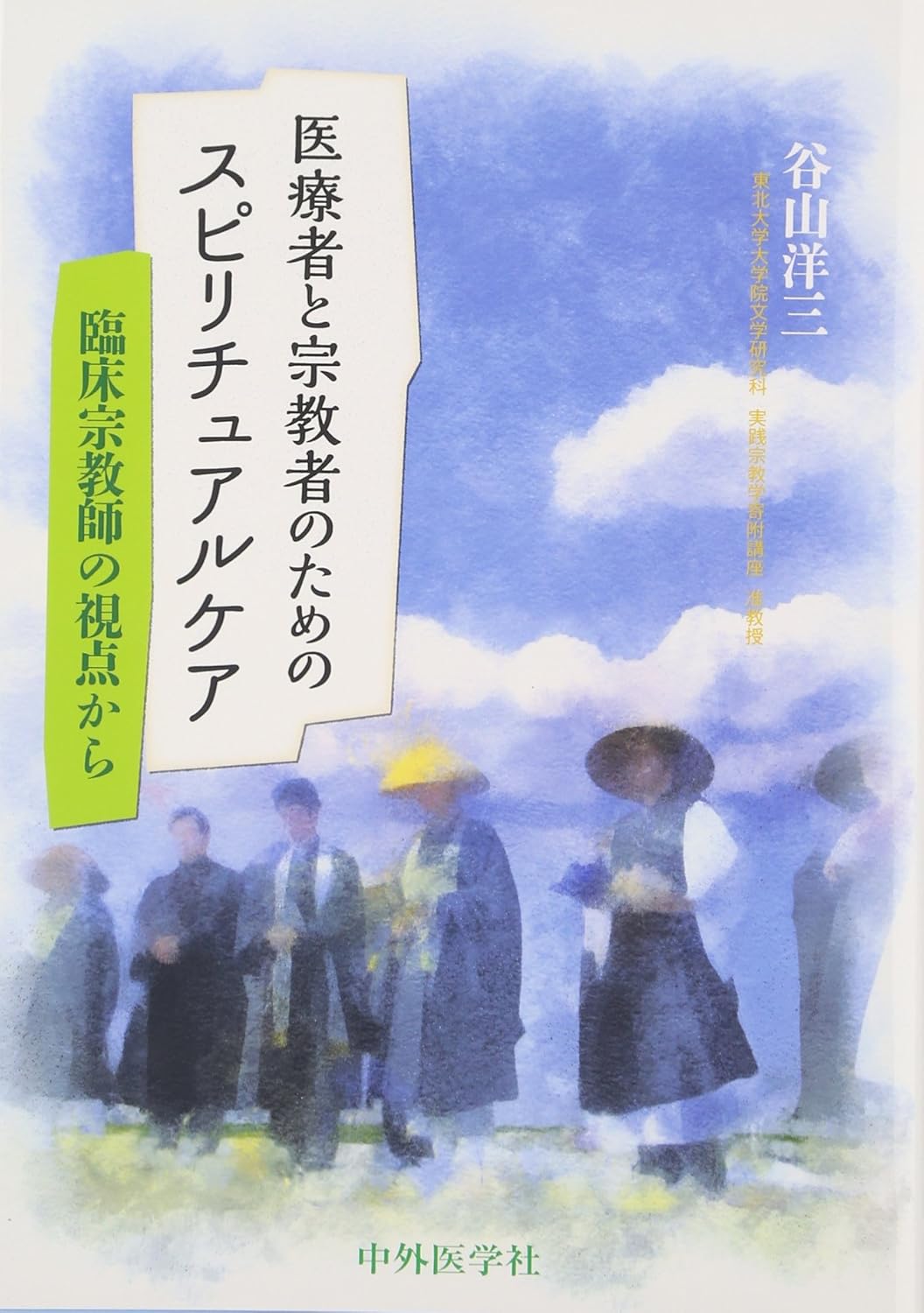リアルな死との対面は、日常の悩みやストレスとは異なる、人生の目的や価値などとの対面でもある。そうした人々へのケア「スピリチュアル・ケア」は宗教が果たすべき役割のひとつといえるだろう。日本におけるキリスト教と仏教の対応を見てみたい。

教会と牧会
牧会(Pastoral Ministry, Pastoral Care)とは、キリスト教教会内における霊的・精神的なケアを行う活動のことである。キリスト教は最も大きい分類として、カトリック、プロテスタント、東方正教会が存在するが、牧会は主にプロテスタント系の名称。カトリックでは「司牧」というが、ここでは「牧会」で統一する。「牧」は聖書の「羊飼い(牧者)」の「pastoral(牧者の、牧畜の)」に由来し、信徒を「羊」として導くという意味がある。プロテスタントの「牧師」もここから来ている(カトリック・正教会では「牧師」は「神父」)。信徒に対する礼拝や説教から、個人の悩みの相談なども行い、信徒の霊的・精神的な支えとなる。キリスト教で言う「霊的」とは科学・物質を超えた、神秘的・超越的な存在に関わる領域を指すもので、即物的なオカルトや怪談の類とは関係ない。「スピリチュアル」も本来は同義と見てよい。
スピリチュアル・ケアとしての牧会的ケア
これらの活動は教会のみならず社会全体に対しても開かれている。キリスト教系の病院における専属の聖職者、チャプレンによる牧会的ケア(Pastoral Care)は、キリスト教に立脚する「スピリチュアル・ケア」として実践されている。スピリチュアル・ケアとは、生きる意味や存在の価値などを喪失し悲嘆に苦しむ人々の苦悩や不安に対し、哲学・宗教など科学では割り切れない世界を探究する分野から寄り添う支援である。特にターミナルケア(終末期医療)、グリーフケア(遺族の悲嘆ケア)との親和性が高い。死は最大の苦痛であると同時に、生命や存在の謎に向き合ざるを得ない哲学・宗教的機会でもある。そして死の苦しみに際して、宗教ほど完備されている体系はないからである。その中でもキリスト教は最もスピリチュアル・ケアに積極的な宗教といえる。カトリック、正教会で終末期患者に施す祈りの儀式「病者の塗油」などは代表的なものである。日本では聖路加国際病院、淀川キリスト教病院などで、チャプレンが終末期患者へ聖書の朗読や祈り、最期の看取りなどを行っている。
一方、仏教では
日本のキリスト教人口は極めて少ない。国内におけるスピリチュアル・ケアを担当するべき宗教は、仏教ということになるだろう。仏教によるスピリチュアル・ケアは「ビハーラ」と呼ばれ浄土真宗や曹洞宗を中心に展開されている。医療現場では京都府の「あそかビハーラ病院」があるが、キリスト教ほどの積極的な活動とはいえない状況である。
教会と同様、法話や写経の会などが開かれ、人生相談などを行っている寺院もあるが、基本的には葬儀、法要以外の付き合いは薄いといえ、信徒との距離が近いようで遠いといえる。むしろ天理教、創価学会といった新興宗教系諸団体の方が、それぞれの地域での定期的な集まりなどがあり信徒との距離が近いといえる。
仏教、寺というと「死」が前面に出すぎているのは大きな問題といえる。仏教寺院の活動の主体はなんといっても葬儀と法要であり、つまり出番は「死後」ということになる。その前に出張られると縁起が悪いと忌避されかねない。病院にチャプレンのつもりで僧侶がやってきたら、大抵は抗議されるだろう。仏像を愛でたりパワースポットを求めて参拝する人々も、入院先に僧侶が訪れたらどう思うか。ゆりかごから墓場まで面倒を見る教会とは違い、日本には神社が「生」仏教が「死」を担当してきた歴史がある。「死・死後」の専門故の停滞といえるかもしれない。
求められる医学と宗教の習合
死は避けられない問題であるのに、医療の現場でスピリチュアル・ケアが浸透しているとは言い難い。緩和ケア、終末期医療におけるスピリチュアル・ケアの重要性が高まっているとはいえ、医師は死を受け入れることに積極的になれないようだ。そもそも医学にとって死とは「無」でありすべての終わり、敗北である。当然、死の向こう側について現代医学が語ることは何もなく、宗教との折り合いも簡単ではない。神仏習合の日本より、クリスチャンの科学者が珍しくない欧米の方が柔軟であることは皮肉である。いまこそ宗教と医学の習合が必要な時ではないだろうか。