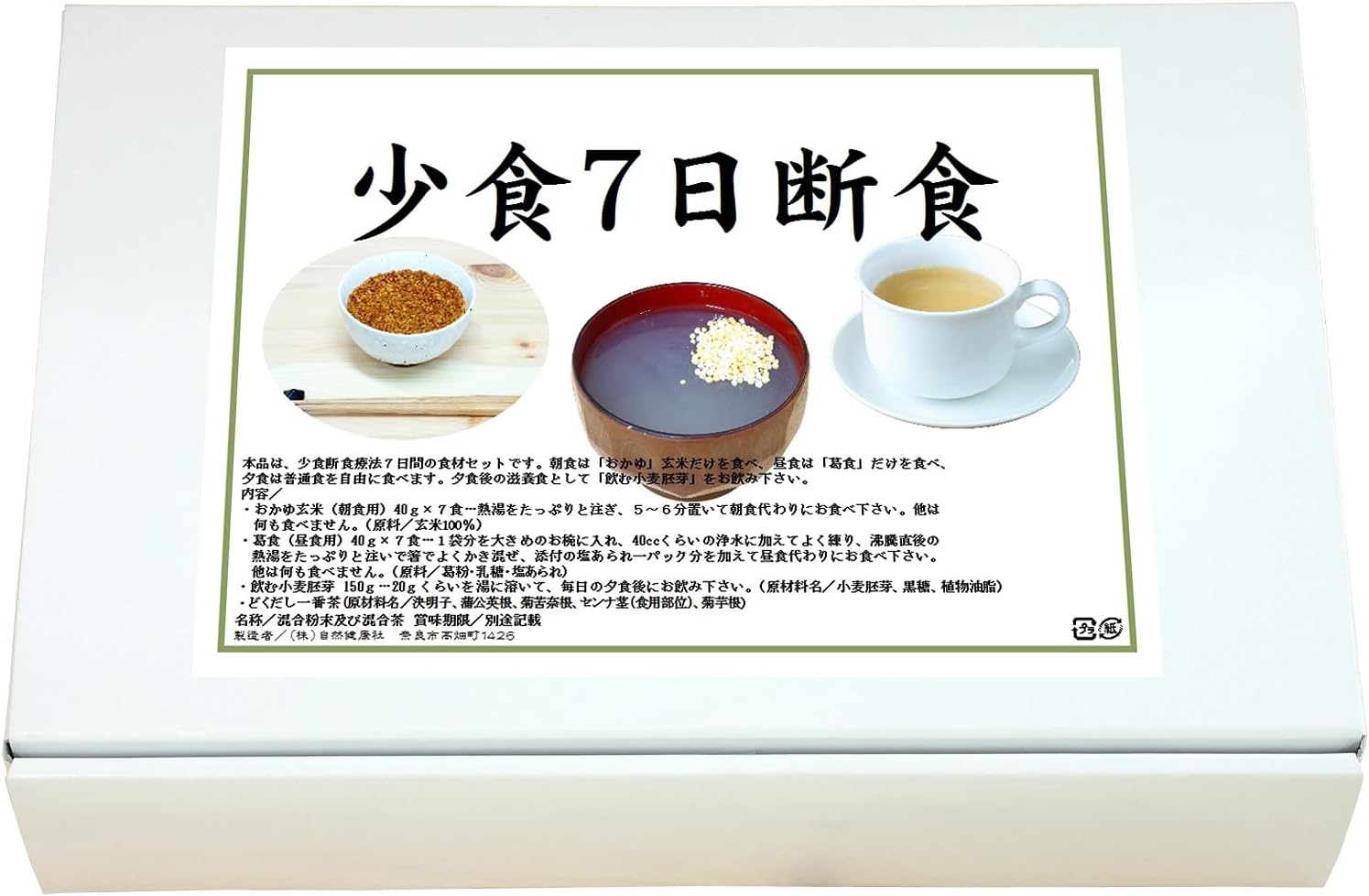霊能者。この響きにほとんどの人が胡散臭さを感じざるをえない。それでも彼らが滅ぶことはない。科学や医学では救われない人たちにとって、宗教や特殊な力を持つ人物の「霊能」は最後の拠り所となる。とはいえ、信頼に値する「霊能者」は決して多くはないと思える。人格や経歴に信用が持てる人物であるに越したことはないだろう。油井真砂(ゆいまさご)は曹洞宗の正式な禅僧であり、かつ、大変な異能を発揮した知られざる人物である。

病と困窮
油井真砂は明治20年(1887)長野県佐久に6人姉妹の長女として生まれた。実業家の父を持つ真砂は医師となり地元で開院、当時は女医の存在自体が珍しく繁盛したようである。そんな真砂に肺結核が襲った。結核は不治の病の代表格のようなものである。家族以外の人間が真砂を忌避した。病院は閉院し借家からも追い出された。この病の恐ろしさは周囲との関係を破壊してしまうことだった。父の破産による困窮に襲われた。どうにもならない真砂に恩師の勧めで座禅を始め、曹洞宗管長にして、大本山・永平寺の管主である森田悟由禅師を訪ねた。真砂はすがった。「苦しくて。苦しくて。人は何のために生まれ、どこに死んでいくのでしょうか。人が生きる意義はなんでしょうか」。森田禅師は「座禅は急場凌ぎの即効薬ではない」「自ら悟ることだ。是非を論ずる余裕はない。覚悟だ、死ぬ覚悟だ。死んでしまえ」と言い捨てた。そして唖然とする真砂の髪を切り落とし、戒律を授け「仏の位に入った」と言い残して去った。
完治と異能
真砂は帰郷すると、近場の洞穴に篭もり座禅を組んだ。一人、死を見つめる真砂に病魔は容赦なく襲いかかる。ある雷雨の夜、胸を掻きむしり、転がるように洞穴から出ると大量の血を吐き出した。雨に打たれ気を失ったという。そして、結核は完治した。この信じ難い話は曹洞宗の正式な教化資料として頒布されている。そして真砂に異能が備わった。蕾の花を摘んで咲かせ、誰も知るはずのない個人の秘密を言い当て、痛風などの病を手を当てだだけで治癒した。作家の今東光は真砂が「水上に座った」のを見たと著書に書いている。それらの真偽は検証しようもないが、その後の活躍を見るに、多くの人が救われたことは事実である。
様々な不思議を見せる真砂だが、医師として誰よりも自身が最も不思議だった。なぜこのようなことができるのか。「天の声」や「神のお告げ」を聴いたわけでもない。だが肉体を超えた不思議を知ったからには医師には戻れない。そんな矢先、新聞である広告を見た。そこには霊術団体「太霊道」と、その創始者・田中守平の写真が掲載されていた。
太霊道・田中守平との出会い
真砂は自分の身に何が起きているのか。はっきりした答えが欲しかった。自分の体験を言語化して説明してくれる人物を求めていたのだ。太霊道を知ったのはそんな折だった。大正期に宗教、オカルト界を席巻した霊術団体、太霊道。その創始者、田中守平は、初対面の真砂に尋常ならざる力を見出した。田中は真砂に手拭いを持つように言うとその手拭いが軽くビリビリ破れた。その場に居合わせた男性2人に同じことをしたが手拭いはビクともしなかったという。田中は入門したばかりの真砂に、いきなり霊術の実践指導を受け持たせた。真砂も田中の話を聞き、たちまち心酔した。真砂の異能を理論付けて説明してくれたの田中が初めてだったのだ。
真砂は田中の講話に感動する日を送った。とにかく自分の実体験や霊的な感覚を的確に言語化してくれるのである。「そうです、そのとおりです」「それはそのように表現するのですか」真砂は心の中で何度も頷いた。医師であり論理的思考を持つ真砂にとって、自分にしかわからない感覚を言葉にし、形にしてもらうことはどれほど嬉しいことだっただろう。田中によると真砂は生きることに諦めて、消極的な姿勢で死に近づいたのではなく、積極的に死に突入しこれに打ち勝った。それによって異能が発揮されたのだと語っている。田中の説明は抽象的であるが、「死中に活を求める」ということだろうか。真砂は太霊道の指導者として名を馳せるようになった。その能力は田中以上とも評され、大霊能者となった彼女の講話には各界の著名人も押し寄せた。真砂は時代の寵児となった。
大霊能者から禅僧へ
そんなある日「大霊能者」真砂を森田禅師が訪ねた。そして一喝した。異能、霊能…そうした力の発現は禅では魔境として否定される。そんなものは小手先の業に過ぎない。「正法に不思議なし」という。禅門にいながら霊能者として世に出た弟子は、禅師から見れば外道に陥っていた。真砂は開眼し、太霊道を辞して、改めて尼僧となった。禅堂の庵に入り、霊能による不思議より、禅の講話や座禅の指導を行うようになった。だが霊能を封じたわけではない。病気治癒などの形で前面に出すのではなく、仏道に導くための方便として用いるようになった。具体的には相談者に自動書記のようなことをさせ、自ら答えを出させるなどである。
禅は一部の特別な人間のみの悟り勝ちという側面がある。真砂と森田禅師との一連のやり取り、病の完治と異能の発揮。これらは大変ドラマチックだが、「死ね」と言われて悟りを得るような人間がどれほどいるだろうか。真砂は小手先の霊能から仏法の深みへと歩み始めても、方便としての霊能は放棄しなかった。悩める人間にはまず、わかりやく癒しを与え、少しずつ仏の道を説いていけばよいのである。真砂の評判は高まり、参禅者は日増しに増えた。その中には著名人や有力者も多く盛況を極めた。だが真砂は驕らず清貧を貫き、頂いた金銭のほとんどを病院や孤児院に寄付した。生涯借家住まいだった。
遷化
昭和34年正月。真砂は新年の挨拶の際、「今年中にはおいとまいたしますよ」と言った。
「先年病気した時あなたは、私が死ぬだろうと思ったでしょう。今年は元気だから死なないと思うでしょう。健康と生命は別のものです。健康だから長生きするだろうと思うのは常人の考えです。御因縁ですからね」
「では今年じゅうに」
「そうです」
この後、真砂は断食を開始。80日にも及んだが、声量も衰えず日々の講話をこなしたという。日増しに身体は目に見えて衰えていったが、断食が満願成就した後も講話は続けられた。そして最後の禅定に入った。正座をしたまま返事もしなくなった。
昭和31年(1956)9月21日。家族は、次第に呼吸の間隔が長くなっていることに気づく。やがて息は止まっていた。真砂は座したまま遷化したのだった。解脱したかのような情景である。戒名は遷化の翌日に到着した、永平寺の副管主、福井天章老師が授けた。その事実からも真砂が胡散臭い祈祷師ではなく、道元以来の歴史ある曹洞宗の正統な僧として高く認められていたことがわかる。
知られざる人格者
東京都青梅市 曹洞宗・常福寺。真砂の墓は実弟が住職を努めたこの寺院にある。元は空き寺で、寺にある聖徳太子像は、実弟が開眼し、真砂が入魂したものだという。信じ難い奇跡譚も伝わる真砂だが、実際の活動は「霊能者」というには地味なものだったといえる。清貧だから偉いというわけでもないが、真砂の生涯には温かいものを感じる。極論だが医師なら性根がどうであれ技術さえ優れていればよい。だが「霊能」を持つ者が名利に走れば、それは「魔」に近づくということである。弱者がすがる「霊能者」が皆、真砂のような人格であることを望む。
参考資料
■油井正智「この人生」万貴山常福寺(1971)
■油井真砂「信心と坐禅」分身会(1935)
■中矢伸一「日本霊能者伝」廣済堂出版(1994)