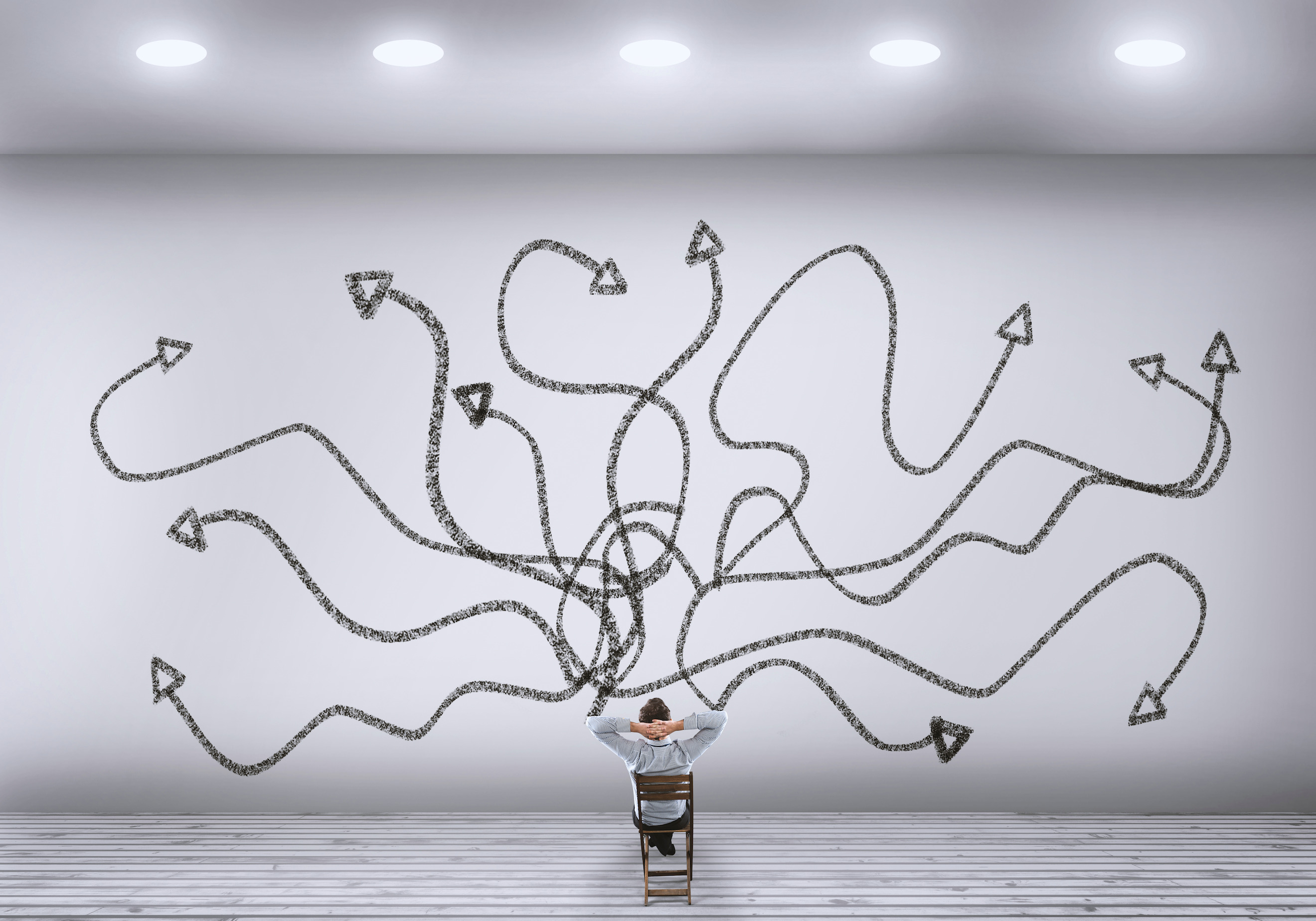「人間(じんかん)五十年 下天(げてん)の内をくらぶれば 夢幻の如くなり 一度生を得て滅せぬもののあるべきか」(人の世の50年の歳月は、天界であれば1日にしか充たらない、夢幻のようなものだ。この世に生を享けて、滅びない者はいない)
戦国武将・織田信長(1534〜1582)が好んだという能、『敦盛(あつもり)』の有名な一節だ。「人生50年」のはずが、いつの間にか今日では、その倍の「100年」になっている。

増え続ける異状死
第二次世界大戦の敗戦後、日本は一面に広がる焦土から立ち上がり、目覚ましい復興を遂げた。そして経済的かつ科学技術的にも、欧米列強に激迫しようとしていた1967(昭和42)年、『青年は荒野をめざす』を著したベストセラー作家・五木寛之(1932〜)は『こころは今日も旅をする』(2024年)の中で、「老人も荒野をめざす」という章を設け、「コロナ禍以降習慣となっていた、早寝早起きを止める」「かつての昼夜逆転生活を今また再び、送る」「クレイジーケンバンドのライヴに行く」、そして昨今話題の生成AI、「ChatGPT」についても、頭ごなしに否定するのではなく、面白がりながら、あれこれと考察している。
しかし、「老人」のみんながみんな、五木のように「柔軟」「自由闊達」「前向き」に「人生100年」における、残り30年前後の毎日を楽しめているとは限らない。
殊に「今」。町中がクリスマスのイルミネーションでキラキラと輝いている。コンビニやスーパーのBGMは、陽気なクリスマスソングばかり。今年を締めくくる忘年会やパーティがあちこちで催されている。テレビをつけると、ニュース・情報番組には、酔ってご機嫌な老若男女たち。「おすすめケーキ」ローストチキン、限定メニューを供するレストラン、通な地酒、ワイン等々…が映し出される。「世間がこんなに楽しそうに盛り上がっているのに、自分だけがたったひとりで取り残されている」と落ち込んでしまい、いわゆる「記念日自殺」の道を選ぶ老人が少なくないのだという。
また「自殺」ではなく、思わぬ急病や事故によって「異状死」を遂げる老人も少なくない。東京都観察医務院のデータによると、2022年、東京23区における、「検案(けんあん。医師が死因を究明する作業のこと)」や「法医解剖」が必要な「異状死」のうち、およそ7割に当たる1万7000人余りが65歳以上。しかも「一人暮らし」の人々は、2021年は7544人だったものの、1年後には8762人と、1000人以上増加している。更に死後経過数が10日以上の人は2731人、30日以上の人は965人だったという。
「孤独死」の心配はない「自分」でも、「今までの自分」のままで残り30何年、生きていられるとは限らない。認知症になるかもしれない。がんのような重篤な病で、何年も寝込んでしまう場合もある。しかもそれは「自分」だけの問題ではない。今、90代の「おふくろ」や「おやじ」はもちろんのこと、「自分」の「つれあい」にしても、いつ一体どうなるかわからない。「死なない程度に生きている」がゆえの、「終わり」のない「老々介護」の不安もある…
「介護」問題に絡んでくることではあるが、彼らの命の「終末期」において、人工呼吸器や点滴、そして胃ろうなどの「延命措置」はどう考えたらいいのか?人の「死」は、意識不明状態に陥った時が「終わり」なのか?それで「終わらせていい」のか?
だったら「自分で自分の始末をつける」または「一緒に」と、「自裁」の道を選ぶ「老人」たちも少なくない。これらの事例は「人生100年」の残酷な現実なのかもしれない。
家賃48000円のアパートで自らのタバコの不始末で焼死した中江滋樹
上記の例で言えば、「異状死」になるのか。あるひとりの66歳の男が亡くなった。たばこの不始末による焼死だったようだ。それは2020年2月20日、東京都葛飾区の中川(なかがわ)、そして小社・冨士神社にほど近い、家賃48000円の、2階建て木造アパートの一室だった。「現場」は「寅さん」ゆかりの「人情味あふれる」「下町」エリアの「柴又(しばまた)」まで3kmほどだったとはいえ、先のデータを勘案すると、このような「孤独死」や「異状死」は「下町」であっても「珍しくない」のかもしれないが…男の名前は中江滋樹(なかえしげき、1954〜2020)。現在50代以上の人々なら、「あああの…」と思い浮かべることができるかも知れないが、若者世代には誰のことか、わからないだろう。「兜町の風雲児」とあだ名されていた、小太りでひげ面、肩までのくせ毛が特徴的な男だ。
仕手筋 中江滋樹
「チッカー」と呼ばれる、巨大な円型の電光掲示板が特徴的な、今日の東京証券取引所とは異なり、大の男が大勢、派手なジェスチャーを交え、時に激しい怒鳴り合いやつかみ合いをしながら取引を行っていた「あの頃」に、中江は投資顧問会社「投資ジャーナル社」を立ち上げた。そしてそこでは、「会員になれば億万長者になれる!」という謳い文句で顧客の投機心を煽り、ひとり当たり10万〜数百万円の会費を取って、推奨銘柄を教え、投資希望の客には、系列証券会社を紹介していた。彼自身、そしてその大胆かつ積極的な「手法」は、昭和54(1979)年4月9日、『朝日新聞』の朝刊に「北浜(きたはま)の若獅子」「弱冠25歳だが、大阪・北浜はもとより東京・兜町でも最近、相場のリード役を果たし、その筋では教祖的存在」「20数人の企業で顧客約3000人、動員できる資金は数百億円」等々の記載がある。中江は、ある企業が行なっている、誰も知り得ない新製品開発の情報をつかみ、それを「流す」。そのことで株価を「操作」する。いわゆる「仕掛け人」だったのだ。当時の大卒初任給は109500円、たばこ1箱75円。そんな時の「数百億円」が、どれほど膨大な金額だったか…
小学校5年生から始めた株取引
中江は小学校5年生の時に、証券会社の外交員だった父親が持っていた『会社四季報』を見て、「大好きな映画がタダで見られる、しかもお金が減らないからいいや」と、まだテレビが映画業界全体の大脅威ではなかった1960年代半ば(昭和39〜40年)に、1株20円だったという日活の株を1000株買った。それが1年後には、日活の株価が2倍となったことから、20000円の儲けを得たのだ。それが中江の株取引デビューだった。そこで「大失敗」していれば良かったのだろうか。とはいえ中江は、決して、金金金!と血眼になっていたわけではなかったのだ。「勝機」に助けられ、「勘」が磨かれていったのだろう。中学、高校と授業の合間に短波ラジオの株式市況を聞き、動向のチェックを行い、時に学内の公衆電話から証券会社に、取引の指示を行っていた。1971(昭和46)年8月のニクソン・ショック時には、日頃追いかけていた株価の動向をふまえ、カラ売り(株券を持たず、または持っていてもそれを使用せず、他から借りて株を売ること)を行った。その結果、1000万円単位の儲けを出した。もちろん、「いいこと」ばかりではなかった。情勢の読み間違えから数百万円の大損を出したりもした。いずれにせよ中江は、大人顔負けの株取引を行なっていたのだ。
進学せずにひたすら株式相場にのめり込んでいった
そんな中江だったが、高校時代に受けた全国模試で、数学が全国3位の高得点を得たことがあった。いわゆる「秀才」だったにもかかわらず、中江は大学には進学しなかった。代わりに、愛知県内の投資顧問会社に「弟子入り」のつもりで就職した。会社に誰よりも早く出勤し、掃除する。それから夜遅くまで、株価のローソク足(あし。相場の始値・高値・安値・終値をそれぞれ、1本の足のように表したもの)を引いて、チャートを作っていた。しかもそれに対し、お出入りの人々がチャートの読み方を中江に教えてくれたり、意見を述べたりしてくれた。このおよそ3年間の経験が、中江の「相場師」人生の下地になっていたという。
3年後に中江は独立した。京都で相場情報リポートを顧客に送る会社を立ち上げたのだ。当初はたったひとりで株式レポートをまとめ、客に郵送していた。中江の画期的だったところは、予想に数学の確率論を取り入れたことにある。本人曰く、「10倍になる株を見つけるよりも、2割ずつ儲けていけばいい。それを10回繰り返したら、10倍になる株どころではない」と。また、企業が所有している特許に着目し、その情報を相場予想に用いたという。このような中江の着眼点は安心でわかりやすいと、顧客から高い評価を得た。そして会員も増えた。その2年後、中江が24歳になった時、東京・兜町に進出し、後々大問題になる「投資ジャーナル社」を設立するなど、先の『朝日新聞』の記事ではないが、自身や顧客が大いに儲かり、更に事業も拡大の一途を辿っていった。
登ったらあとは落ちるだけ 中江滋樹の天国と地獄
それらに伴い、1982年(昭和57)年前後には、中江には有名アイドルとの「熱愛報道」はもちろんのこと、田中角栄(1918〜1993)、中曽根康弘(1918〜2019)、竹下登(1924〜2000)などの大物政治家とのコネクションのみならず、「テレ朝の天皇」と称された実力者で、テレビ朝日の専務を務めた三浦甲子二(きねじ、1924〜1985)。そして日本船舶振興会の笹川良一(1899〜1995)にとても可愛がられるほど、「株」の世界のトップへと上り詰めていった。
しかし「栄枯盛衰」は世の常なのか。1984(昭和54)年、中江が長らく推し、巨額の金を投じていた、某化学メーカーの株が急落し始める。機微に聡い証券会社各社は、「絶対に儲かる」と称され、実際に「そうだった」、通称「中江銘柄」の取り扱いを自粛し始めた。「負のスパイラル」は止まらない。最終的に、顧客から集めていた数百億円にも及ぶ金を返すことも叶わなくなり、中江と関係者たちはその翌年に逮捕されてしまう。とはいえ中江は、勾留中であっても、チャートブックや経済誌・業界誌を差し入れさせ、それらに目を通し、株のことをずっと考えていたという。裁判では詐欺か否かが争われたが、中江には1988(昭和63)年3月、詐欺罪で懲役6年の実刑が下ってしまった。
出所後の中江滋樹
1992(平成4)年、中江は滋賀刑務所から仮出所した。全盛期の中江が「株の師匠」だったというパソナグループの南部靖之(1952〜)は、約10年前の「恩義」を忘れず、中江のためにアルマーニのスーツを用意し、ベントレーを刑務所前に待機させていた。それに乗って中江は、実家がある滋賀県・近江八幡に帰った。しかも実家には、服役中に南部へ手紙で書き送っていた中江の好物、「アワビの肝」まで用意してあったという。
…それから28年。暴力団関係者絡みの取引等々を経験しつつも、流れ流れて中江は、東京・葛飾区のアパートでひとり、亡くなった。「孤独だった」或いは、心の奥底に沈殿している「昔の栄光」が忘れられない、またはそれを超える「再起」が果たせないがゆえの「酒の飲み過ぎ」だったのか。2012(平成24)年頃から、「そこ」に住んでいた中江だが、誰もあの「中江滋樹」とは気づくことはなく、訝しく思われていたのだろう。「ひとり暮らしのはずなのに、毎晩怒鳴るような声が聞こえた」「酔っ払っては、何かしゃべっていた」という、近所の人々の証言がある。
中江滋樹にとっての株はロマンだった
どこかで止めればよかったのではないか。株に限らず「勝負ごと」は全般に、引き際を見極めることも肝心だ、という。しかし中江にとっての株取引は、「ギャンブルではなく、ロマン」。小学生の頃から死ぬまで、人生と共に、常にそばになくてはならないものだった。もしも中江に株取引に必要な「世の中の動きを読む」、そして売り買いをするタイミングを測る「勘」を含めた「才能」が全くなく、まだまだ若いうちに「挫折」し、他の生き方に舵を切らざるを得なかったとしたら、中江は詐欺罪で逮捕・収監されることもなかったであろうし、アパートの一室で「孤独死」「異状死」しなかったのかもしれない。
山あり谷ありの人生か 平坦な道を選ぶか

もしも「選べる」としたら、人はどちらを「選ぶ」のだろうか?中江のように、いい意味でも悪い意味でも、時代の寵児として輝かしい日々を過ごすものの、「転落」してしまい、「たばこの日の不始末」による急な「孤独死」「異状死」を遂げるか。それとも地味に堅実に、「道」から外れるような「余計なこと」、刺激的だが時にリスクを伴うような「冒険」を一切せず、心穏やかに多くの人に看取られて亡くなるのがいいのか。「両方体験してみないと、わからない」のが、正直なところだろう。
ただ、中江が最後の時を過ごした葛飾区の中川や冨士神社は、四季折々の美しい姿を見せている。酔いが醒めたタイミングで中江が、それらを満喫してくれていればよかったのだが…もっとも、そのような「情緒」に浸ることを好む人間ではなかったからこそ、中江は「株の天才」だったのかもしれないが…。
参考資料
■「マネー 14:仕掛け人 情報流し株価操る 市場の“鬼子”現状では野放し」『朝日新聞』東京版 1979年4月9日 朝刊(7頁)
■西井一夫(編)『昭和史全記録 1926−1989』1989年 毎日新聞社
■「大卒初任給」『年次統計』2013年5月27日
■中江滋樹「中江滋樹の金と女と相場人生」『Ameba』2013年7月29日〜8月25日
■「東証ってどんなところなの?実際に行ってみた」『マイナビニュース』2016年4月8日
■「1960(昭和35)年頃の東証見学案内【前編】」『日本取引所グループ公式チャンネル The Official JPX Channel』2016年9月9日
■「1960(昭和35)年頃の東証見学案内【後編】」『日本取引所グループ公式チャンネル The Official JPX Channel』2016年9月9日
■「1985(昭和60)年頃撮影:立会所事務合理化システム導入前の立会場」『日本取引所グループ公式チャンネル The Official JPX Channel』2016年10月26日
■中江滋樹「“兜町の風雲児”ゼニの哲学」『日刊ゲンダイDIGITAL』2019年9月8日〜2020年3月8日
■比嘉満広『兜町の風雲児 中江滋樹 最後の告白』2021年 新潮社
■「追跡 記者のノートから “兜町の風雲児”の最期」『NHK』2021年4月9日
■「孤独な高齢者を苦しめる『記念日自殺』という病 −年末に高齢者の自殺が増加する理由」『集英社オンライン』2022年12月22日
■佐高信・森功『日本の闇と怪物たち 黒幕・政商・フィクサー』2023年 平凡社
■「もっと!能楽を旅するコラム 織田信長が愛した『幸若舞』と『敦盛』」『能楽協会』2023年6月6日
■「『兜町の風雲児の波瀾万丈』投資ジャーナル事件(1985年)【TBSアーカイブ秘録】」『TBS NEWS DIG』2024年5月14日
■「養老孟司×小堀鴎一郎 『生かす医療』から『死なせる医療』への転換をどう見極めるか?86歳・現役の2人が<高齢者の終末期医療>を考える 『死を受け入れること −生と死をめぐる対話−』」『婦人公論. jp』2024年7月27日
■五木寛之『こころは今日も旅をする』2024年 新潮社
■「東京23区の『異状死』高齢者が7割占める…一人暮らしも大幅増加 検案の際に死後数日経過した事例多数」『FNNプライムオンライン』2024年11月28日