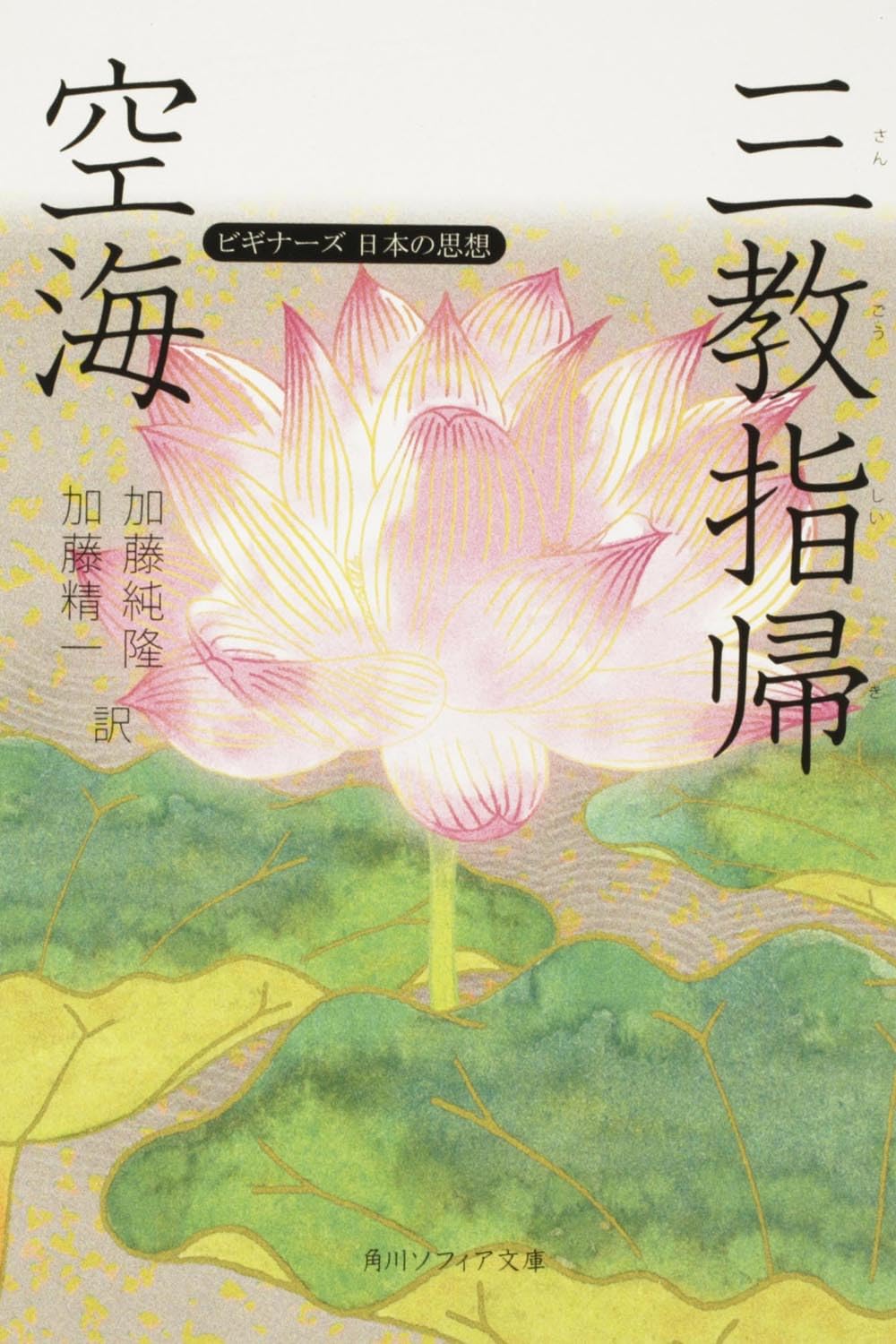神仏混合の日本人の死生観には様々な宗教が流れて混んでいる。本稿では煩雑になるため、最も影響が大きく内容が広い仏教は除き、儒教と道教を概観した。そこには理性の象徴である哲学・思想と、理性を超える世界を提供する宗教・信仰の悩ましい関係が見えてきた
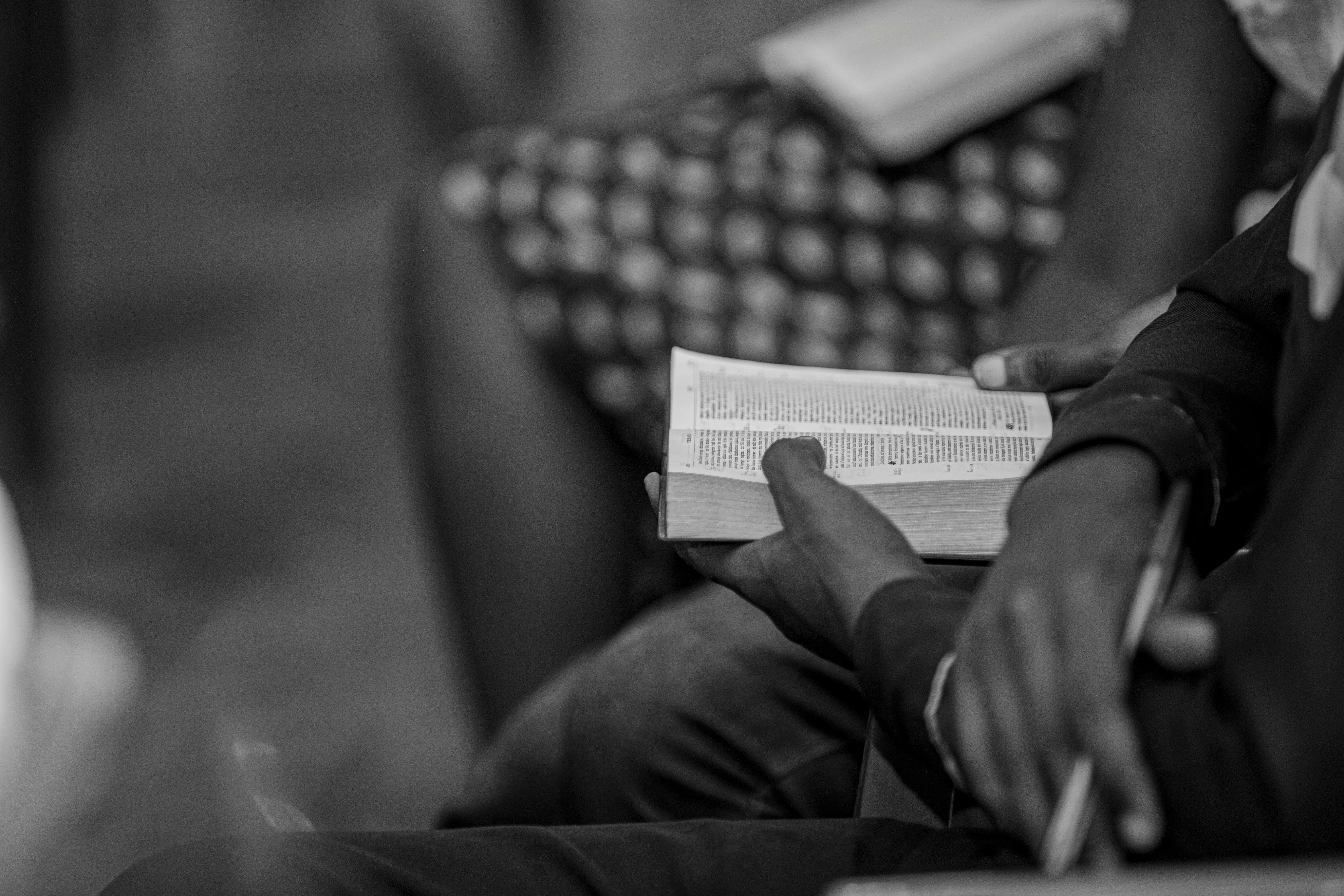
仏教 儒教 道教 三教
仏教、儒教、道教。中国では「三教」と呼ばれ、それぞれの開祖とされる仏陀、孔子、老子の三賢人が一堂に会する絵画や仮想対話が存在する。空海が三教を比較し仏教の優位を説く「三教指帰」もそのひとつである。日本では道教の代わりに神道を入れて三教とされたこともあるが、道教の信仰も深く根付いている。むしろ神道は日本古来の宗教として三教を受容し習合してきた、メタ宗教といった感がある。そしてこの三教は「開祖」が俗世の凡人には及ばない境地に達した純粋な哲学者、思想家であるにも関わらず、民衆の要請により宗教化していったという共通点がある。
霊魂を語りたくない孔子
儒教の最も重要な要素は祖霊崇拝である。祖先の霊を祭祀する儀礼こそが儒教そのものといってよい。そもそも「儒」とは、死者と交流するシャーマンを意味する語で祖霊祭祀に大きな役割を果たした。「儒」の考えは、人間は霊的存在「魂」と肉体的存在「魄」によって構成される「魂魄」であるとする心身二元論だった。死後は「魂」と「魄」に分離し、「魂」は天上へ行き、「魄」は土に還るとした。そして「魂」は祖霊として現世の子孫が祭祀を行い厚く敬った。
祖霊の下には現世の長老から子供に至る厳格なヒエラルキー、いわゆる「長幼の序」による家族一族が構成され、年長を敬うための「礼」が定められた。儒「教」の祖、孔子は皆が「礼」を尊び、心正しく生きる道徳的な世の中を目指した。すると、死についてよりも、生について考えることに重きが置かれてる。孔子はそのために世を惑わせる鬼神(幽霊)などの迷信の類を追放し合理的な学問を構築しようとした。有名な「怪力乱神を語らず」である。
では元々の根幹に位置する「祖霊」の存在と祭祀の意義とは何か。孔子は祖霊を祭祀する心得を「礼」の根拠としたのだが、祖霊も鬼神のひとつである。その根拠自体を問われると矛盾が生じてしまう。祖霊の存在は人間の死後生を保証してくれる。人間は死後どうなってしまうのか。孔子は明確な答えは出さなかった。その問いに対して、その後、朱子が形而上学的な解釈を加えていった。
朱子の形而上学
朱子によると、この宇宙は宇宙を生成する根本原理「理」と物質原理「気」によって成り立つとする理気二元論を展開した。「理」によって「気」が様々な形に凝縮して生命や物質が生まれ、時期が来れば散じて雲散霧消する。そして時期を経て再び「理」によって何らかの形に凝縮するという。人間も動物も物質も「気」の塊である。イメージとしては原子論に近いが、原子と異なり「気」そのものは物質ではない。鬼神=霊魂すらも「気」で構成されている。「理」は宇宙の法則、規則性といったもの。対して「気」は何らかのエネルギーのようなものだろうか。人間は「気」を今の自分に象っている「理」を知り、「理」の通りに生きていくことが大切であるとし、形而上学的な存在論から道徳・倫理を導いていった。
ではその「気」が散じた後はどうなるのか。朱子は祖先の霊(気)だけは散じても子孫とつながっており、子孫が祭祀を行うことで以前の形に凝縮して帰ってくるとする。帰ってきた祖霊が降り立つ場所が神主、現代の位牌である。位牌は祖霊が降りる依代である。葬儀とは祖霊を呼び、位牌に降りて頂く祭祀だといえ、別れどころか再会の場である。位牌が日本でも本尊以上に大切にされているのは当然といえるだろう。だから祭祀が大切なのだという論である。
朱子は孔子が避けた霊魂の問題を形而上学的な理論を打ち立て解決しようとした。そして祖霊信仰の立場から、死後別の人間に生まれ変わる仏教の輪廻転生説を批判した。しかし散じた「気」が「理」によって生成されていく繰り返しは、輪廻と変わらないのではないか。また祖霊だけが祭祀によって復活する仕組みもよくわからない。民衆が望む宗教的な世界と、民衆を導びくための哲学の融合はやはり難しいのであった。
現世利益の道教と無欲な老荘思想
儒教、仏教に比べると日本ではマイナーな印象のある道教だがその影響は無視できない。「六曜」の友引には、葬儀を避けるものだし、仏滅に結婚式を挙げる人はほぼいないといっていい。この六曜は陰陽道を起源とするもので、その陰陽道の起源は道教に行き着く。死者をも蘇生させるという陰陽道最大の秘儀「泰山府君祭」の泰山府君は道教の神である。七夕、鬼門、全国に存在する庚申塚といった民間信仰も道教発祥のものだ。そして日本人の精神的支柱「天皇」の語源も道教の最高神・天皇大帝が由来とする説もある。
宗教としての道教は民間信仰として自然発生したとされるが、伝説上の開祖とされるのが老子である。老子とその後継者と呼ぶべき荘子の思想を老荘思想、道家思想という。老荘思想は宇宙の究極原理「道(タオ)」を追究する学派で、常識や作為、欲望願望を否定し自然のままに自由に生きていく「無為自然」を唱えた。合理主義、形式主義の儒教と並ぶ中国の二大思想である。一方、それらの思想と並行して発展していった原始道教というべき民間信仰が老荘思想と合流し道教が成立した。老荘の思想は自由な生き方を示唆する観念的な世界である。しかし現実的な中国人は観念の世界では物足らず、「道」を得て不老長寿を実現するための具体的な方法を求めた。老荘が唱える、無為自然を体得した境地に到達するために様々な具体的な修法が生まれた。これらを会得した者は「仙人」と呼ばれることになる。それは老荘が否定したはずの作為的な方法といえるだろう。生きる時は生きる。死ぬ時は死ぬ。そもそも生死に拘らない。それが老荘の説く自由であったはずだが、民衆はそのようは高尚な境地より、不老長寿、そして究極的には不老不死を求めるようになった。
聖人vs凡人
合理主義を目指した孔子だが、後年は自身が神格化され、各地に「孔子廟」が創建され礼拝の対象となった。鬼神を語らない自らが神となったのである。一切の作為、欲を否定し自然のままに生きよと説いた老子は太上老君という神に祀り上げられ、道教は現世利益の宗教となった。仏教も事情は同じで、仏陀は神格化され本尊として崇めらている。「三教」の祖は、不確かな死後のことや、虚しい願望などを超越する道を説いたのだが、民衆は高尚な哲学では救われず、現世を超える世界と具体的な神を求めたのだ。結局、聖人・聖者と言われる人は凡人とは違う世界の人である。他方、凡人には自らを救う宗教も哲学も作れない。人間が理屈では割り切れない現世を超える世界を求める限り、哲学と宗教、聖人と凡人は悩ましい関係を続けていくのである。