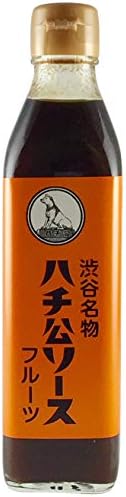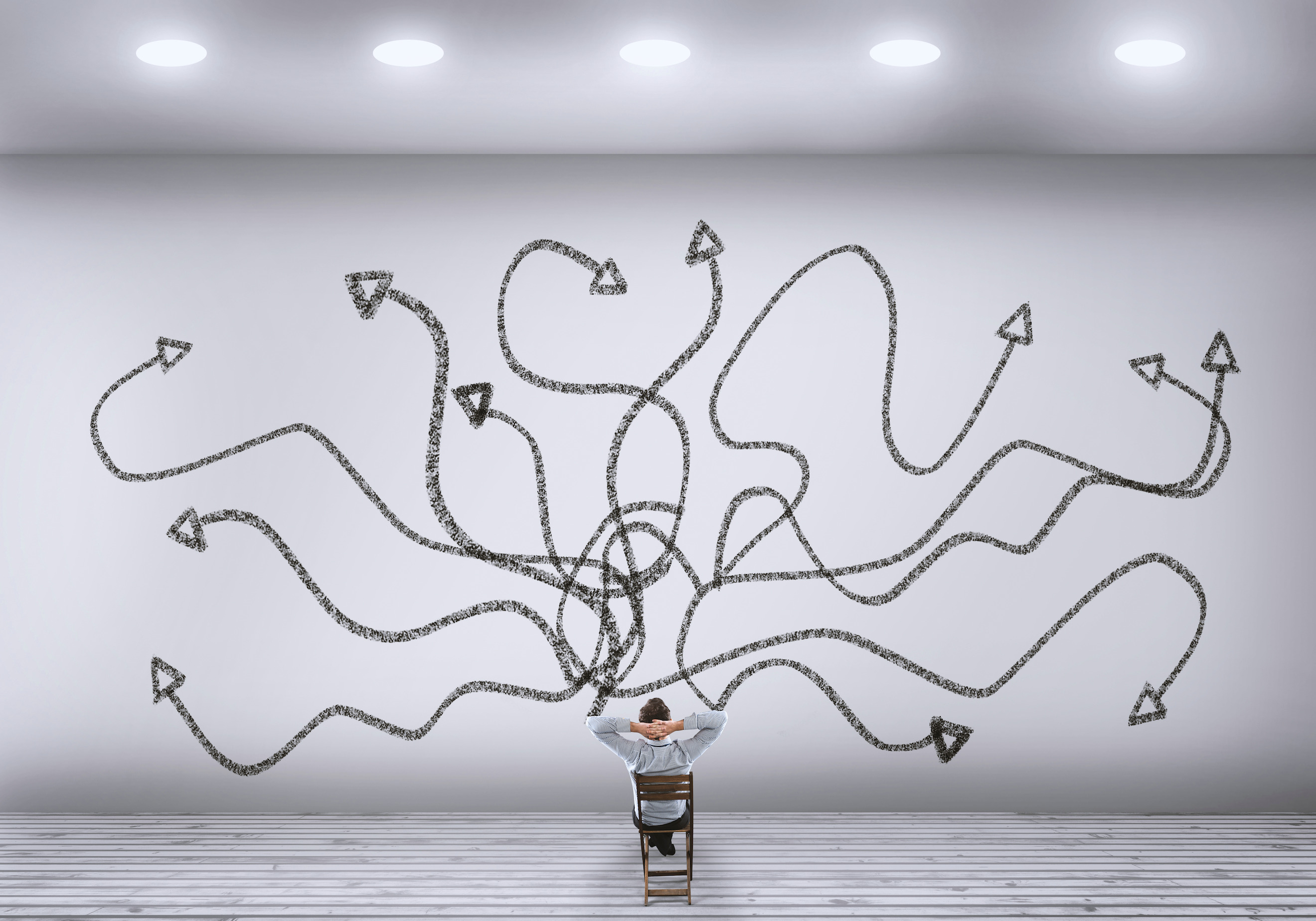ペットとして動物を飼っていると、人によく懐く種類の生き物いる。食べ物がほしい、散歩に行きたい、などの要求に人が応えることでお互いに繋がりを感じ、「かわいがる」「懐く」という関係になるのだろう。動物の死はペットロスのような状態を引き起こすこともある。関係が密接だからこその感情とも言えるだろう。

急逝した飼い主を待ちつづけ、やがて亡くなったハチ
愛玩動物とのあいだにはそれが顕著であり、犬と人との関係を描くものとして「忠犬ハチ公」の物語がある。飼い主を駅まで迎えにいくことを習慣としていた秋田県犬・ハチの話だ。ハチは飼い主が勤務先で急逝してからも駅で待ち続け、新藤兼人原作の映画『ハチ公物語』(1987年)では飼い主を待ちながら死んでしまう犬を映して物語が終わる。ラストシーンは飼い主に会えないままで死ぬことになるが、「忠犬ハチ公」の物語はただかわいそうなだけの話としては作られない。描かれるのは「死後に結実する絆」というテーマである。
渋谷のハチ公像は待ち続ける健気な印象を与えるが
渋谷駅のハチ公像は有名であるが、三重県津市には飼い主であった東京帝国大学教授の上野博士とハチ公が並んでいる像がある。上野博士が現在の津市出身だからである。渋谷のハチ公像がハチの生きている間に作られたものである一方でこの像は、上野博士とハチの死後に作られたものだ。もしハチが「亡くなった飼い主を待つ犬」ではなく「飼い主と共に死んだ犬」だったとしたらこのような像が作られることはないだろう。
三重県津市のハチ公像は飼い主に会えた喜びを感じさせる
三重県津市で飼い主の横に並ぶハチの像は生前のように駅から帰る日常の姿をイメージさせると同時に、別れを経て「ようやく会うことができた」という喜びの姿を喚起させる。この像に作られた姿がそのどちらなのかは、像だけ見たときのわたしたちにはわからない。
生と死をどう解釈するか
後者のイメージをするとき、死と生とは必ずしも永遠の別れを意味するものではない。生きている者が死者を思うような感情は亡くなった者たちにとっても同様なのではないかと人々は考え、両者の死後は念願のもとに再び会うことができるという想像をすることになる。「ハチ公の物語」は死者と生者の絆を示し、また人と犬という種族を越えるものであるところから人々はその絆の深さを感じる。
会えない者を待ち続けるという行動は美談となるが、本当に待つだけではこの物語は完結しない。のちに飼い主を見上げる像が作られるなど、死後においても生前のように並んだ姿が作られるまでが「忠犬ハチ公」の物語と言えるだろう。
参考資料
■「ハチ公物語」 2024年3月13日参照
■「忠犬ハチ公像|観光スポット|観光三重(かんこうみえ)」 2024年3月13日参照