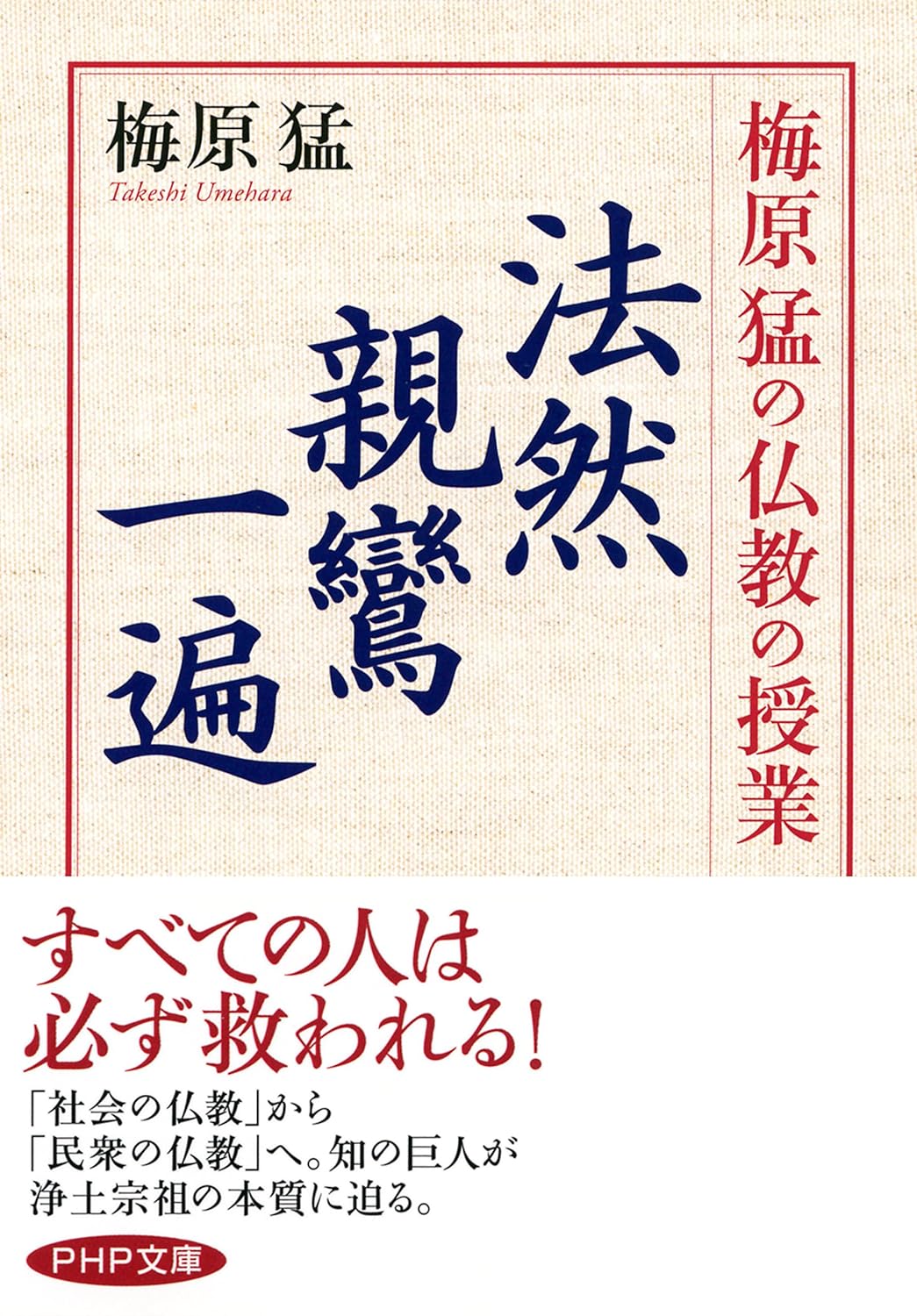「南無阿弥陀仏」を唱える浄土系仏教といえば法然が開いた浄土宗と親鸞が開いた浄土真宗が代表的な宗派だろう。現代ではこの両派の違いを説明できる人も多くはないと思われるが、それにも増して知られていないのが時宗とその宗祖一遍(1234〜1289)である。知名度は低いが本来は両宗派に続くべき重要な宗派であり、その思想は現代的ですらある。

一遍と時宗
鎌倉時代は法然が興した浄土宗に始まり、新しい仏教が次々と登場した。その特徴は従来の難解な貴族仏教から、庶民でも理解が平易な庶民仏教への変換である。一般的には大きく浄土系(浄土宗、浄土真宗)、禅系(臨済宗、曹洞宗)、法華系(日蓮宗)に分類される。このうち日本浄土仏教の流れは法然が浄土宗、親鸞が浄土真宗、一遍が時宗の祖とされ完成したとされる。しかし日本史でも必ず習うほどの足跡を残したにも関わらず、一遍の知名度は低く正当な評価を受けているとはいえない。実際、時宗の寺院は全国でも数百カ所に過ぎず、浄土宗や真宗とは比較にならないのが現状である。
捨聖と踊り念仏
住まいを定めず全国を旅した一遍は「遊行上人」と呼ばれた。また最低限必要なもの以外はすべて捨てたので「捨聖(捨てひじり)」とも呼ばれた。仏教が最も戒めることは「執着」である。物欲や生への執着を断ち切った時、輪廻転生の環から解き放たれ解脱することができると説く。浄土仏教ならそれは極楽浄土に往生することだと解釈される。一遍は自分のような徳を持たない者は家や寺に安住すればそれらに執着してしまう。だからすべてを捨て全国を遊行に出ることを決意したという。
一遍といえば「踊り念仏」で知られる。踊り念仏は念仏を唱えながら身体を揺らし心だけでなく、身体で念仏の響きを味わい、忘我の境地に至る。すべてを捨てて踊り陶酔するという行為には、変性意識状態を作り出す一種のシャーマン的な要素を見ることができる。庶民は理屈を超えた念仏の世界に酔ったことだろう。この大胆かつアグレッシブな発想は、元々比叡山の秀才だった法然や、法然の教えを深めようとした親鸞は考えもしなかった。一遍を敬愛する庶民は念仏を唱え、踊り、俗世を離れ、活き活きと極楽へ往生することを願ったのである。
時衆と時宗
仏教史では便宜上一遍により時宗が立宗されたとされるが、一遍は時宗には全く関わっていない。捨聖・一遍は教団などを作ろうなどとは思っていなかった。当然というべきか一遍の死後、時衆は瓦解した。一番弟子の他阿弥陀仏・真教(1237〜1319)は一遍を偲び速やかに念仏して往生するつもりだったが、乞われて再編し組織作りに着手した。捨てるどころか守るべきものを増やしてしまうわけだが、組織がなければ現代にその教えは伝わっていないことを考えるとその役割も否定できない。
時宗の場合は一遍を慕い念仏を唱えながら身を揺らす人々が「時衆」と呼ばれるようになり、一遍の死後に弟子たちが集団を形成して「時宗」となった。「時衆」の「時」とは臨場の際の念仏「臨終命終」を「六時」(四六時中)唱えるという意味だとされる。時宗は南北朝時代から室町時代にかけて隆盛を誇った。その勢いは初期の真宗教団など足元にも及ばないものだった。特に南北朝時代は「婆娑羅(ばさら)」と呼ばれるアナーキーな思想の持ち主が跋扈していたが、彼らの「ノリ」は踊り念仏と相性が良かったと思われる。
時宗の衰退
その時宗もやがて衰退した。大本山の清浄光寺はさすがに現代においても堂々としたものであるが、この寺も火災などにより度々消滅の危機にひんしている。浄土真宗が本願寺が東西に分裂してもなお日本最大の信者数を誇る巨大教団に成長したのとは対照的である。その要因のひとつに一遍が自身の死に際して、経典などを焼き捨ててしまったことが挙げられる。一遍は「南無阿弥陀仏」を唱えながら焼き捨てたといい、「南無阿弥陀仏」の名号のみを残したといえる。念仏以外の何物にも執着してはいけないとする徹底ぶりであった。また、日本人は静謐を好む傾向があり仏教も例外ではない。日本密教とチベット密教の仏像・仏画を比較するとよくわかる。チベット密教の極彩色あふれるアグレッシブな様式と日本密教の静謐さは正反対である。踊り念仏も日本仏教にあってはかなりの異端といえた。事実南北朝のような戦乱の世が終わるとその勢いは衰える。一遍の念仏者としての徹底さと、その教えのアグレッシブさを考えると衰退は避けられない運命だったのかもしれない。
アグレッシブに死ぬ
栗原康は独特のファンキーな語り口で一遍を描いた伝記に「死んでからが勝負。いくぜ極楽、なんどでも」と書いている。まさに踊り唱えて極楽へ往生するのが一遍と時宗の極みである。また、ホリスティック医学の第一人者帯津良一氏は著書やインタビューなどあちこちで、面白いことを言っている。
ー私が考える「攻めの養生」のゴールは、命のエネルギーを日々高め続けて、死ぬ日に最高潮に持っていって、その勢いであの世へ飛び込むことです。先に向こうへいっている人たちが「今の何だ? 帯津か!」と驚くような死に方をしたい(笑)ー
勢いであの世へ飛び込む。まさに、行くぜ極楽の境地そのものではないか。アグレッシブな往生、つまりアグレッシブな死を表現した一遍の教えは現代でこそ活かされるのではないだろうか。時宗教団には奮起して頂きたい。
参考資料
■聖戒「一遍聖絵」岩波書店(2000)
■柳宗悦「南無阿弥陀仏」岩波書店(1986)
■栗田勇「一遍上人」新潮社(2000)
■栗原康「死してなお踊れ 一遍上人伝」河出書房新社(2019)
■【松岡修造の健康画報】86歳の現役医師・帯津良一先生が実践する「攻めの養生」とは?(2022/06/07配信)