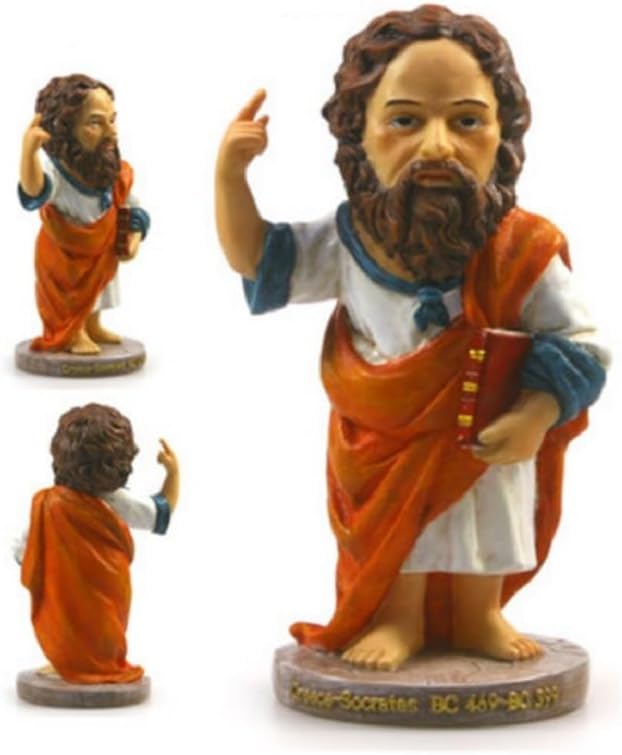哲学の祖と呼ばれるソクラテス(BC470〜399)は、人はただ生きるのではなく、哲学的な「真理」を知り、「善く生きること」が人間の本道であると説いた。それが口先だけの綺麗事でなかったことは自身が証明している。死刑を前にしてもクラテスは己の信じる、本当の「善」や「美」などの「真理」に殉じた。
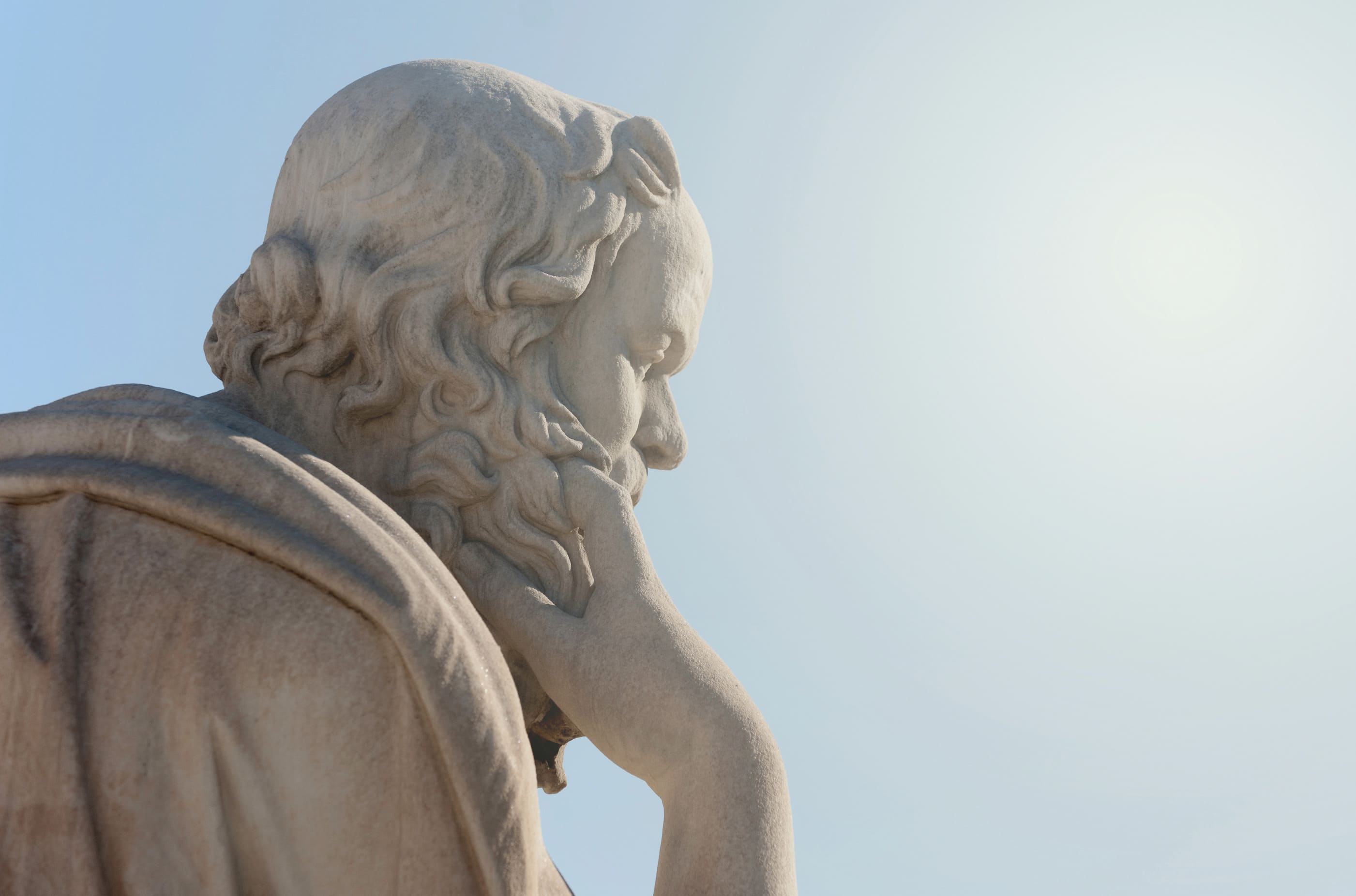
ソクラテスの弁明
ギリシャ哲学はソクラテス以前と以後に分類される。前ソクラテスの哲学者たちは万物の根源を探究する、後の自然科学につながる自然哲学であった。これがソクラテス以降は「人間とは何か」「いかに生きるべきか」などについて深く思索する人間学になっていく。ソクラテスにおいて人間の関心は、天地自然の仕組みから真、善、愛と、人間存在へと深みへと移っていった。そしてソクラテス最大の関心は「善く生きる」ことであった。善く生きなければ人として生きる意味がない。これはソクラテスが神から与えられた使命だった。そのようなことをアテナイ(アテネ)の人々に問い、真理(真の善、美、正義など)とは何かを追究した。アテナイの議会は古来から信仰されている神とは違う怪しげな神を信じ、若者を問答で誑かす不届きな人物として、ソクラテスを拘束し裁判にかけた。ソクラテスには弁明の機会が与えられたが結果は有罪で死刑。自ら毒人参の液を呑み、これが死刑執行となった。
無知の知
ソクラテスが「哲学」という真理の探究を行ったのは「アテナイで最も知恵がある者はソクラテス」という神託を受けたことによる。ソクラテスは自身がそれほど優れているわけはないと、知者・賢者と言われる人物を訪ね歩き問答を重ねた。すると誰もが真の知者でないことがわかった。しかも本人たちは自身を知者だと思い込んでいたのだ。ソクラテスは自身が「本当のこと」は何も知らないと自覚していた。神が言うのはそのわずかな分だけ優れているということなのだとの結論に達した。名高い「無知の知」である。よく誤解されるが、ここで言う「知」とはあくまで哲学的な「真理」を指す。様々な具体的な事例に対する知ったかぶりを指摘することではない。
そして「知者」とは今日私たちが言う「知識人」とは違う。「知識人」に該当するのは、ソクラテスが敵視したソフィストに代表される。現代なら弁護士などにあたる人達だ。豊富な知識とその知識をディベートで展開する応用力。頭の回転と透徹した論理。素晴らしい能力ではあるが、ソクラテスに言わせれば言葉の使い方が上手いだけの人達で真理からは程遠かった。彼らの仕事は言葉や理屈で相手を論破することで高額な報酬を得る。何が真実なのかはどうでもよく真の知者とは言えない。それを対話によって悟らせ、真理に導くことがソクラテスの「哲学」だった。
ソクラテスは裁判で何を語ったか
真の知とは、金銭や名声など目に見える富に囚われず、目に見えない「善」や「美」そのものといった真理に目覚めることである。知識の量や小手先の理屈でわかることではない。浄土真宗の信者に妙好人という人達がいた。その一人、讃岐の庄松(1799 ~1871)には仏壇を開き、御本尊(阿弥陀仏)に向かって「バーアバーア」と甘えだしたという逸話がある。宇宙の真理そのものである阿弥陀仏を「親様」と呼び、人生のすべてを任せきっていたのだ。現代の価値観に照らせば知的な疑問を持たれかねない人物であるが、当時の知識人たる僧侶の問いに機鋒鋭い解答を返しやり込め、彼に教えを受けに来る僧侶も少なくなかったという。無知無学の極みといっていい彼らは、金銭や名声に囚われず、もっと大切なもの、真理を掴んでいた。もしソクラテスが彼らを知ったなら、妙好人は真の知者であると言ったのではないだろうか。裁判でソクラテスは言う。
ーただ金銭をできるだけ多く自分のものにしたいというようなことにばかり気をつかっていて、恥ずかしくはないのか。評判や地位のことは気にしても、思慮と真実には気をつかわず、魂(いのち)をできるだけすぐれたものにするということに、気もつかわず心配もしていないとはー
論理と倫理の人 ソクラテス
ソクラテスは死の恐怖を克服した信念の人と呼ばれるが、この評からは「倫理」のみが強調され哲学に必須の「論理」が見えない。裁判はこれ以上哲学を説くなら死刑との判決だった。死刑囚は毎朝怯えるという。死刑執行の宣告は朝行われるからだ。看守の足音が近づくと緊張が走り過ぎると肩をなでおろす。これで今日一日を生きられると。ところがソクラテスは死に対して怯える様子はない。彼は死刑を前にして動揺を見せず法廷でも弟子の前でも淡々と論を進めていく。死刑を受け入れたのは、哲学を説くことが自分の使命であり、それなら哲学を説くのであるから死刑ということである。死刑を避けるために哲学を止めるとか、死を甘んじて受け入れるというのではない。哲学を説く=死刑なのだから、その論理に従ったまでであった。ソクラテスは淡々と死を受け入れた。死の恐怖に直面し、それに打ち勝ち死を受け入れた…わけではない。神からの使命として哲学を説いたソクラテスは魂の不死を確信しており、元々死ぬことに恐怖などなかった。だからといって自ら死を選んだわけではない。ソクラテスは「哲学をすれば死刑」との判決を言い渡されただけである。そして哲学をやめはしなかった。真理を説かないことはソクラテスにとって「善」ではなく「悪」である。進んで死にたいわけではないが、自分を偽って生きることもしなかった。
しかし、命より大切なものがあるだろうか。まずここは生き延びることだ。友人クリトンは獄中に忍び込み脱獄を説得している。だがソクラテスはブレない。ただ生きていればそれでいいのか。善く生きなければ生きる意味はないのだと。ソクラテスは論理と倫理が一致した人物だった。
「真理」を求める心
ソクラテスの死生観は何よりも生きることが大切、「生きてこそ」の現代の死生観とは相反している。富や名声を得ることが人生の真実なのか。真理を知らずただ生きているだけで本当に「生きている」と言えるのか。現実に実践するには難しい指摘である。真理なんてものは人によって違うだろうも言う人も多い。「それはあなたの感想ですよね」というフレーズが流行語にもなった。それでもソクラテスが読み継がれているのは、心のどこかで「本当のこと」を求めているからなのかもしれない。
参考資料
■プラトン著/岩田靖夫訳「パイドン―魂の不死について」岩波文庫(1998)
■プラトン著/久保勉「ソクラテスの弁明・クリトン」岩波文庫(2007)
■田中美知太郎編「世界の名著 プラトン 1」中央公論社(1996)