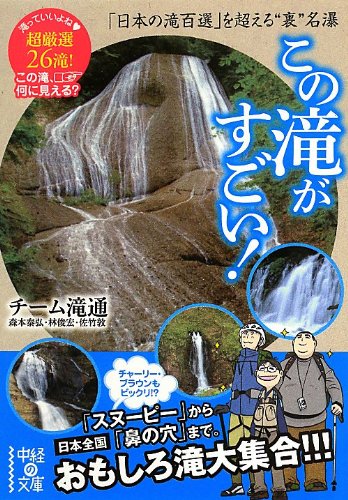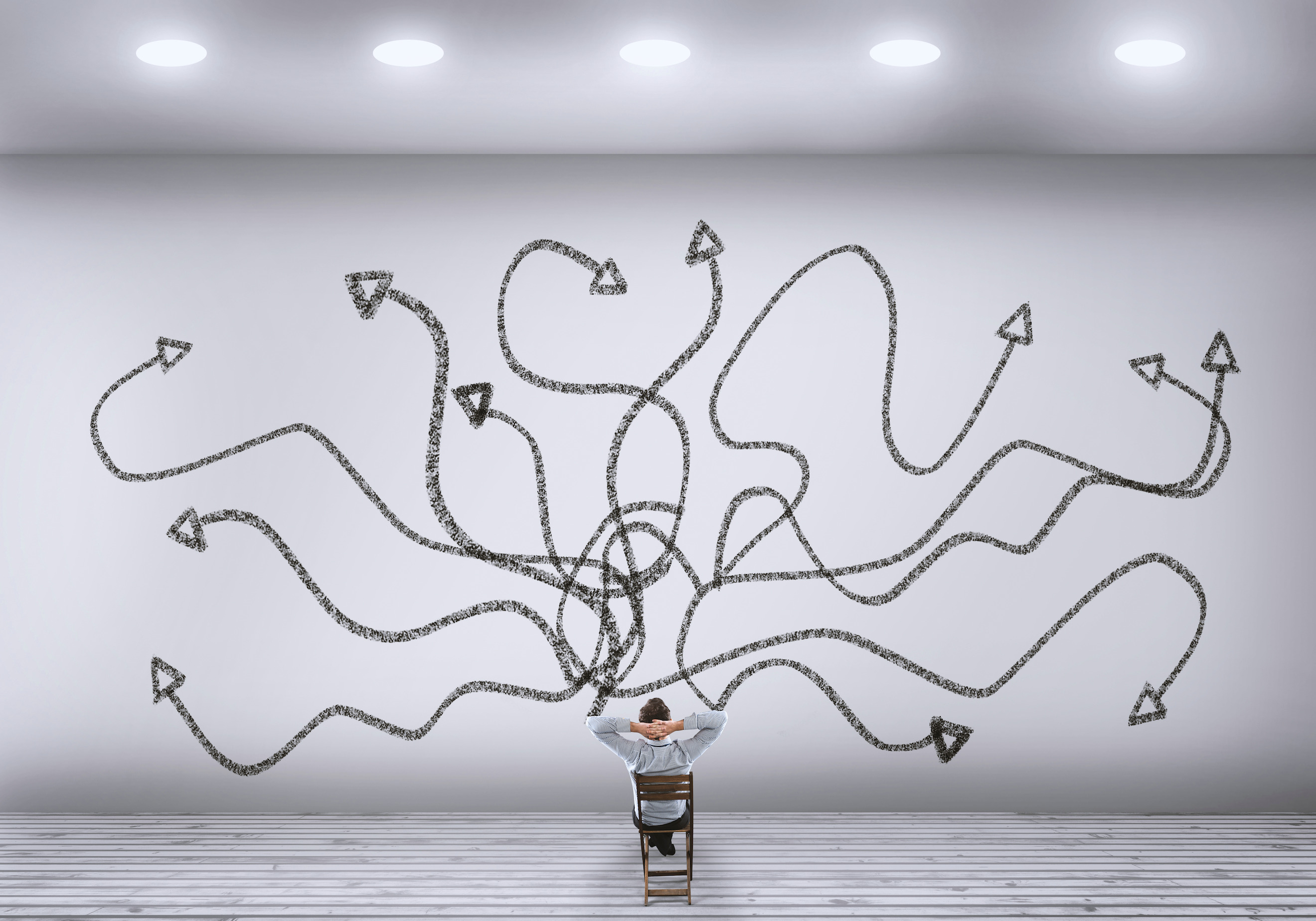日本人は世界一清潔な国民と呼ばれ、不潔を極端に嫌う。コロナ禍以前からマスクを好んで着用すると世界から奇異に見られていた。この潔癖さは、日本古来の「宗教」神道の重要な概念である「穢れ」と「禊ぎ」の心が棍本にあるように思われる。この「禊ぎ」の概念を具体的な行法として現代の神道に伝えたのが神道家・川面凡児(かわつらぼんじ)だった。

禊と滝行
「禊ぎ」の思想は神道の最重要概念といえる。神道が目ざすものは「清明心」である。「清明心」を保つには心を浄めなくてはならない。それが「禊ぎ」である。禊ぎは黄泉の国から脱出した伊邪那岐命がけが川原で水を浴びて身を清め、黄泉の穢れを祓ったことに由来する。穢れとは「気枯れ」であり、禊ぎを行い邪気を祓うことを重んじた。
こうしたことで神道では不浄、穢れを忌み嫌う。清浄、清潔であることが第一義だ。それは精神的な意味でも同じことである。いわゆる汚部屋で生活して清らかな心が養われるのは相当難しいと思われる。最近は職場の制服の自由化が進んでいる。その発想自体は結構なことだが、一方でスーツや道着、袴などを身に着けると気持ちも引き締まることも事実である。軽い服装では気分も緩くなるし、だらしない格好では気持ちもだらしなくなる。その意味でもまず身を清め、場を清潔にすることが求められる。
禊ぎには滝行や冷たい水の中での沐浴などがあるが、伊邪那岐の神話は禊行の原型といえるだろう。この滝行など一連の禊ぎの行法を考案し世間に広め、現在の神社神道に取り入れられるに至った人物が川面凡児(1862〜1929)である。
神人・川面凡児
明治から終戦にかけての日本には、大本教の出口王仁三郎、天理教の中山みきなどオカルティックな人物が次々と登場した。川面凡児もその一人である。だがこの人物は単なるオカルティストではなく、現代に至るまでの神道の行法を作り上げた人物でもある。明治政府は神道を国家統一の精神的支柱に据えるため、神道は宗教ではないと規定した。当時は神憑りや神降ろし、「鎮魂帰神法」と呼ばれる神秘行法などが流行していた。川面の説く禊行は、こうした胡散臭さそうなオカルティックな要素がない座禅のような健康的な鍛錬法に見えた。さらに記・紀に由来する伝統的な風格が相まって政府に好意的に受け止められた。禊行が大政翼賛会の行事に採用され全国に波及し各神社に伝えられると、川面は学会、政財界の名士の前で講演を行うまでになる。日露戦争の英雄、秋山真之らを発起人として、川面の講義や講義録の出版を支援する団体も発足した。明治の日本哲学界の大物、井上哲次郎も川面の講義録を高く評価したといわれる。神降ろしの代名詞的存在で、国から大弾圧を受けた出口王仁三郎とは雲泥の差がある。そして戦後も禊行は神社本庁の正式な行法として認められ現在に至っている。我々がイメージする滝行や寒中沐浴などは主に川面が広めたものだったのだ。禊行を現在の神道に採用された川面の業績は多大なものがある。
だが禊行が健全なイメージによって広まったのは皮肉といえる。川面はまぎれもない神道系オカルティストだった。私たちが知る禊行は、川面流本来の体系からするとかなり簡略化されており川面神道の一端に過ぎない。
「禊ぎ」と「直霊」
川面の説く「禊行」は単なる滝行や沐浴のみではなく、独特の拍手や呼吸法、合気道にも取り入れられている身体技法などを用いて、神との交流を求める神秘行だった。行を積んでいくと、人間を構成している棍本要素である「直霊(なおひ)」が覚醒するという。川面によると人間は「直霊」「和魂(にぎみたま)「荒魂(あらみたま)」によって構成されている。和魂は精神、荒魂は肉体を指し、直魂は宇宙の棍本的な神的存在と結ばれている霊的な要素である。これらは西洋の神秘思想でいう「霊」「魂」「肉体」に類似しており、この棍本的な存在を川面は「天御中主太神」と呼ぶ。古事記が伝える最初の神「天之御中主神(アメノミナカヌシ)」がモデルと思われる。禊行により「直霊」が覚醒すると「太神」と一体となり、時空を超えたありとあらゆることが知覚出来るとしている。本来の禊行は非オカルトどころか、一種の変性意識状態に導き神秘体験を得るためのものだった。
直魂は究極の神とつながっている。つまり人間は神の分身である。だが直霊は普段の生活の中で煩悩にまみれ穢れている。我々は美しいものや圧倒的な自然現象を目の当たりにしたり、悲嘆に暮れ、死に直面した時などに神を想うことがある。それは普段は汚れて見えない自身の直霊に触れるということなのだ。川面は本来の禊ぎを行い、心の穢れを祓えば直霊が覚醒し元々の清らかな神に近づけると説いた。
川面凡児は1929年(昭和4年)に帰幽した。その前年に自身の死期を予知していたと言われ、主宰する団体の機関紙に辞世の歌まで詠んでいた。川面によると人間は死後、荒魂(肉体)、和魂(精神)、直霊(霊)が分離し、直霊は棍本存在に帰る。そして次の世で新たな使命を遂行するために再びこの世に生まれ変わるのだという。死にあたり川面は、また転生して国や宇宙のために尽くさねばと言い遺し悠然と逝った。
本来の「禊ぎ」の心
いくら洗浄したとしても人の食器で使うことを躊躇ったり、何かにつけて手を洗ったりするのは、「穢れ」と「禊ぎ」の心だろう。しかし自然科学の洗礼を受けた我々は、身体や服装など見た目の汚れには神経質になっても、目に見えない「魂 」や「霊」の穢れには無頓着なようである。それは命を軽んじたりする唯物論的な死生観にもつながっている。
直霊の概念は仏教の「仏性」にも通じる。人間は身体の奥に本来素晴らしいものを持っているとする思想である。神と一体にはならなくても、川面凡児が説いた本来の「禊ぎ」の意味を学ぶ意義はあるといえるだろう。
参考資料
■津城寛文「鎮魂行法論―近代神道世界の霊魂論と身体論」春秋社(2022)
■氷川雅彦「川面凡兒 日本人の霊性に多大な影響を与えた神人」光祥社(2013)
■山蔭基央「神道の神秘」春秋社(2000)
■「古神道の本」学研(1994)