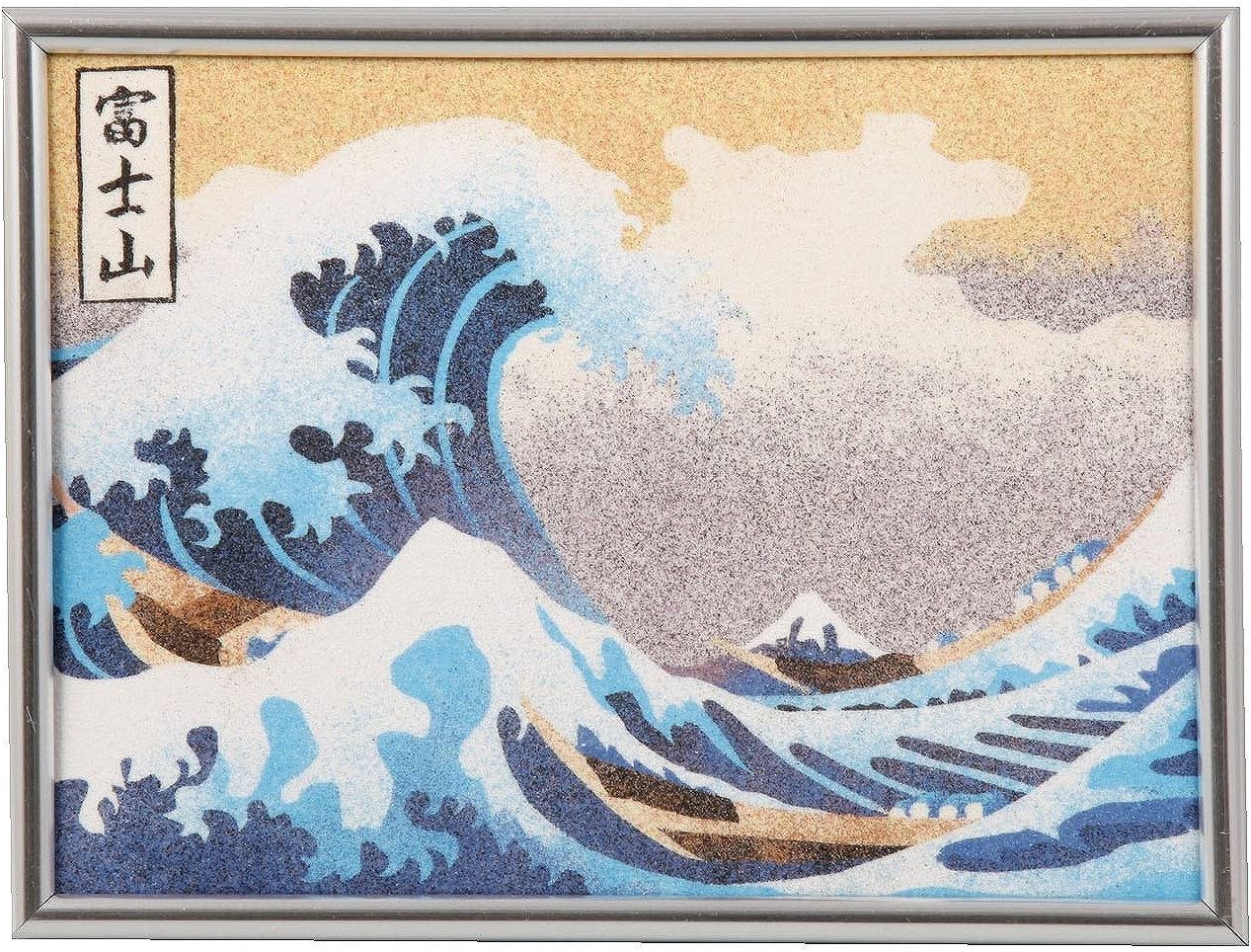「砂絵」をご存知だろうか。文字通り、「砂を用いて描いた絵」のことだが、かつて、年末年始、或いは寺社の縁日・祭日の折など、衆人を惹きつける独特のせりふ回しで知られる「啖呵売(たんかばい)」、例えば国民的映画である『男はつらいよ』(1969〜1995、1997、2019年)の「フーテンの寅さん」や「バナナの叩き売り」、或いは「ガマの油売り」などと同じく、「砂絵書き」「砂書き」「砂絵屋」、または「砂文字」は、大道芸のひとつのジャンルだった。江戸時代後期(1750〜1850)ぐらいから、世間に広まっていったという。

四天王寺にいた砂絵書きの男性
例えば、明治43(1910)年前後の大阪・四天王寺(してんのうじ)の境内には、57〜8歳ぐらいの、「人生五十年」が当たり前だった当時では「老人」と見なされていた砂絵書きの男性がいたという。彼はまず、白い砂を右手に握り、額縁などの形を描いて、その中に二重字(ふたえじ。文字の輪郭を線書きし、中を空白にした文字)で、その日の年月日、または「青年易老學難成(せいねんおいやすく がくなりがたし)」などの名言を、赤や黒に染めた砂で書き表す。その筆致は、巷の提灯屋や傘屋のものよりはるかに優れ、ちょっとした書道の先生が、慌てて逃げ出すほど素晴らしかったという。しかも彼が得意としたのは、字だけではなかった。四天王寺の西門には、能書家で知られる小野道風(みちかぜ。とうふうとも呼ばれる。894〜967)の額字(がくじ)と伝えられる「釈迦如来/転法輪処/当極楽土/東門中心」がある。男は野次馬に向かって、「これより小野道風が、柳に飛びつく蛙に見とれているところを描く。次に西門の額字と全く同じものを横書きにして、皆様にお見せしよう!」と言い、白・赤・黒・緑の砂を握り、巧みに道風の姿を描く。そして柳の木、更に蛙…そして額字へと、絵の具や墨ではなく砂、そしてそれを操る巧みな手業(てわざ)だけでやってのける。
増上寺付近にもいた砂絵書き
このような砂絵書きは、大阪・四天王寺ばかりではなかった。例えば江戸の信仰の場のひとつであった芝の増上寺(ぞうじょうじ)の御成門(おなりもん)前(現・港区芝公園)にかつて存在した借り馬乗り場周辺でも、ひとりの老人が五色の砂を用いて正午前と午後の日暮れ前に、『頼光の鬼神退治(平安中期の武将・源頼光の英雄譚)』や『吉備(きび)公の野馬台詩(やばだいのし)を読む図(奈良時代の官人・吉備真備(きびのまきび)が中国・梁の予言詩「野馬台詩」を読む、歌舞伎狂言「吉備大臣支那譚」の名シーン)』などの大作を手がけ、多くの人々を惹きつけていたという。
書き手と砂絵のギャップ
また、女流日本画家の上村松園(しょうえん。1875〜1949)が幼い頃、京都の町々を門付(かどづけ。民家や商家の戸口の前で芸を行うなどして金品を受け取る芸能のこと)して回っていた砂絵書きの老人が描いた「文字」「花」「天狗」「富士山」などについて、「どのように練習しても、ああはうまくかけるものではない。天稟(てんぴん。生まれながらの才)の技というのはああいうのをさして言うのだろう」と書き残した。老人の「砂絵」は、大御所だと周囲に重んじられ、鎌倉あたりの閑静なアトリエにこもって、世俗の垢やしがらみから離れ、ただひたすら「芸術」に没入した結果によるものではなかった。松園が見た砂絵書きは、「絣木綿のぼろを纏って白の風変わりな袴をつけ、皺くちゃな顔には半白の鬚など生やして」、門々を訪ねて回っている「哀れな老人」だった。しかし彼の「汚らしくよごれた右手」から、いともたやすく、「至妙至極(しみょうしごく。この上もなく優れて、たくみなこと)の芸術の世界」が生み出されていたのだ。
芸人の街である浅草にもいた砂絵書きのお作さん
このような砂絵書きだが、江戸後期〜明治〜大正〜昭和〜平成〜令和の現在に至るまで、多くの参詣客や遊興客で賑わっている浅草にもいた。明治30(1897)年前後ごろまで活躍していたという「砂文字のお作さん」という、60前後の女性だ。お作さんは観音堂の裏、通称「奥山(おくやま)」を根城にしていたというが、1873(明治6)年に浅草公園地改造事業が行われて以降、見世物や露店は沼地を埋め立てて新たに造成された「六区」に移転させられたことから、そちらに場所を移したという。ちなみに「六区」とは、ビートたけし(1947〜)の小説『浅草キッド』(1988年)の舞台になった歓楽街かつ「芸人の町」だ。
多くの人を惹きつけたお作さんの砂絵
とはいえ当時のお作さんは、浅草公園界隈では「さあーさ、お立ち会い!御用とお急ぎのない方はゆっくりと聞いておいでなされ」で始まる「ガマの油売り」の口上と勇ましい居合い抜きで有名だった伝説的人物、初代・永井兵助(ひょうすけ。1737頃〜?)を彷彿とさせる人気を博していたという。例えば、髭題目(ひげだいもく)の「南無妙法蓮華経」を立ち見客から見えやすいように、書き手から見て上下左右いずれも逆から、「経」〜「南」までの文字を砂で書いてみせる。その後、箱の中に、戯曲の主人公となり、俗謡にも唄われ、嘉永年間(1848〜54)頃に脚光を浴びた武士・鈴木主水(もんど)をさらさらと描く。次にそれを箱で覆い、砂を入れてトントンと叩く。箱を開けてみると、まさに手品。今度は、主水と心中した内藤新宿の娼妓・白糸(しらいと)に変わっているなど、先に紹介した砂絵書き同様の手技を発揮していた。
投げ銭を得るためにみすぼらしさをだしてお情け頂戴を演出
ジャーナリストの篠田鉱造(こうぞう。1872〜1965)の著書『幕末明治女百話 後編』(1932年)によると、お作さんは浅草寺から見て南西に位置する、阿部川町(あべかわちょう。現・台東区元浅草3〜4丁目)の「奥の原」と呼ばれるところに住んでいた。夫は馬具職人だった。2人の間には、子どもが1人いた。鬼子母神を深く尊崇し、もともとは由緒ある家の出だったというお作さんだが、没落し、夫婦で猿回しをしながら東京に上ってきた。浅草に住んでから、猿回しは廃業していたものの、猿は飼い続けていた。また、お作さんが家にいる間は、商売道具の砂を染め粉で染めていたため、指先がいつも色鮮やかに染まっていたという。「仕事」に出るときのお作さんは、小ざっぱりした身なりだが、公園に着いてから、汚い身なりに着替える。それは色鮮やかに染まった砂で衣服が汚れてしまうのを避けるためであるのに加え、見物人に「情け心」を喚起させ、多くの投げ銭を得るためだった。
お作さん一人で家族3人と猿を養ったが、技術は継承されずに亡くなった
「真似をする者がないぐらいの腕」を有し、大いに見物人を沸かせ、たくさんの投げ銭を得ていたお作さんだったが、それでもなかなかうだつが上がらない。阿部川町から今度は光月町(こうげつちょう。現・千束2丁目、入谷2丁目)に引っ越す。更に、役者を歌川国貞(1786〜1865)が、建物や風景を歌川広重(1797〜1858)が描いた豪華な錦絵集『東都高名会席尽(とうとこうめいかいせきづくし)』(1852〜1853)にも登場する吉原の土堤下(どてした。現・台東区日本堤(にほんづつみ))近辺に移った。だが、何度「心機一転」を図っても、暮らしはちっとも楽にならなかった。主人の馬具職にしても、明治の世には時代遅れで、全く稼げない。そうしたことから、お作さんが砂絵書きで、家族3人と猿1匹を養っていたのだ。
苦境にめげず、お作さんはいつも日なたで砂絵を描いていたため、顔は真っ黒に日焼けし、年齢よりも老けて見えた。しかも、日々の憂さを酒で晴らしていたことから、日頃の疲れもあったのか、あるとき土堤下で頓死してしまった。お作さんの葬儀の折、参列した多くの人々が、あの手業を習っておけばよかった…と悔やんでいたという。篠田もお作さんの砂絵は本来、「物もらい」ではなく、「上品にお金が儲かったに違いない」ものだけに、砂絵の技を「誰に教わったのか、聞き逃してしまった」ことを後悔し、「臨終は淋しいものでした」と締めくくっていた。
そもそも砂絵とは
そもそも「砂」とは、「土」ではなく、岩石が自然の摩耗によって細かく砕かれているもの、或いは人工的に細かく粉砕したもので、「山」にはなく、主に海辺に広く存在している物質のことだ。しかし「砂」は、「砂上の楼閣」という言葉にあるように、堅牢な建物が砂の上に建っていることは「もろい」「壊れやすい」「儚い」という意味があり、昭和を代表する推理小説作家・松本清張(1909〜1992)の名作『砂の器』(1961年)のタイトルは、上記の砂の持つ特性やイメージを踏まえて、名づけられたものだろう。
お作さんを含む砂絵書きは、こうした「砂」のありようを知りすぎるほど知り、それを活用し、生業としていた。しかもそれは、現在も有名で継承者も多い「バナナの叩き売り」や「ガマの油」以上に、「見世物」らしい「見世物」だった。何よりも「その場限り」「今、ここ」のものだったからこそ、彼らが砂絵を後世に「残す」ことや、「上品に金を儲ける」ことなどは、一切思いつかなかったのかもしれない。
砂という存在の儚さ 一瞬で消え去る砂絵 突然亡くなったお作さん
日本画家の水島爾保布(におう。1884〜1958)は随筆「淺草漫憶」(1925年)の中で、幼少期に見たお作さんこと「砂畫かきの婆さん」が、いつも「淡島様」、すなわち雷門を背にして、浅草寺の本堂から見て左側に建つ淡島堂の近所に店を張っていた、と回想している。水島はお作さんが桜の花々、そして歌舞伎で有名な白井権八や小紫を巧みに描いていたことに触れつつ、「自分で描いて自ら崩す砂畫(=画)と等しく婆さんの姿も今は全く消えて無くなつて了つた。近い樹蔭にしよんぼり殘つた瓜生岩子(社会事業家。1829〜1897)の銅像を見るたんびに、その婆さんのお喋りを思ひ出すんだから諸行無常だ」と嘆息している。
水島の最後の言葉、「諸行無常」つまり、全ては移り変わり、消えてしまう。この世の事物は、何もかもむなしいものである…は、水島のように、お作さんの実演、そして完成した砂絵を実際に見たことがない我々にとっても、「砂絵」はもちろんのこと、「砂絵書き」そのものがむなしく、悲しく思われてならない。しかも古今東西、さまざまな芸術活動・作品、そしてそれをつくり上げた有名・無名の多くの人々が存在してきたとはいえ、しょせん、全てが「諸行無常」なのだ。とはいえ、一瞬で消え去り、残らないものであっても「むなしい」「儚い」とため息をつくばかりでは、お作さんの「供養」にはならないのではないか。一家の大黒柱として泥臭くも陽気、そしてしたたかに浅草で砂絵を描いていたものの、突然、この世から去ることとなったお作さんを「きれい」に、「諸行無常」という言葉でまとめず、一瞬で消え去り、この世に残らない「美」に驚嘆する「喜び」「高揚感」を感じる「私」、そして多くの人々に愛され、輝いていたお作さんを含めた「人間」そのものの存在をあえて今、肯定したいと考える。
参考資料
■菊池貴一郎(芦之葉散人)『江戸府内絵本風俗往来』1905年 東陽堂
■実業力行会(編)『無資本実行の最新実業成功法』1910年 樋口蜻輝堂
■水島爾保布「淺草漫憶」『聖潮 浅草号』第2巻 第10号 1925年11月(119-124号)浅草寺出版部
■篠田鉱造『幕末明治女百話 後編』1932年 四条書店
■仲田定之助『明治商売往来』1969年 青蛙房
■中村ときを『筑波風土記』1974年 崙書房
■増田靖弘(編)財団法人日本レクリエーション協会(監修)『遊びの大事典』1989年 東京書籍
■吉見俊哉「浅草」石川弘義・津金澤聰慶・有末賢・佐藤健二・島崎征介・薗田硯哉・鷹橋信夫・田村穣生・寺出浩司・吉見俊哉(編)1991年(13-14頁)弘文堂
■岡部昌幸「砂絵」歴史学会(編)『郷土史大事典 上』2005年(957頁)朝倉書店
■堀切直人『浅草 明治江戸編』2005年 右文書院
■米田憲雄『江戸の大道芸人 −庶民社会の共生』2009年 株式会社つくばね舎
■上村松園『上村松園全随筆集 青眉抄・青眉抄その後』1943/1972/1990/1995/2010年 求龍堂
■「錦絵でたのしむ江戸の名所」『国立国会図書館』2014年
■日外アソシエーツ株式会社(編)『地名から引く日本全国作家紀行・滞在記』2018年 紀伊國屋書店
■「淡島堂」『浅草大百科』
■『聖観音宗 あさくさかんのん 浅草寺 公式サイト』
■「二葉屋 吉原 土堤下」『公益財団法人 味の素食の文化センター』
■「ゆるゆる参ろう奥浅草観光ツアー」『浅草観光連盟』