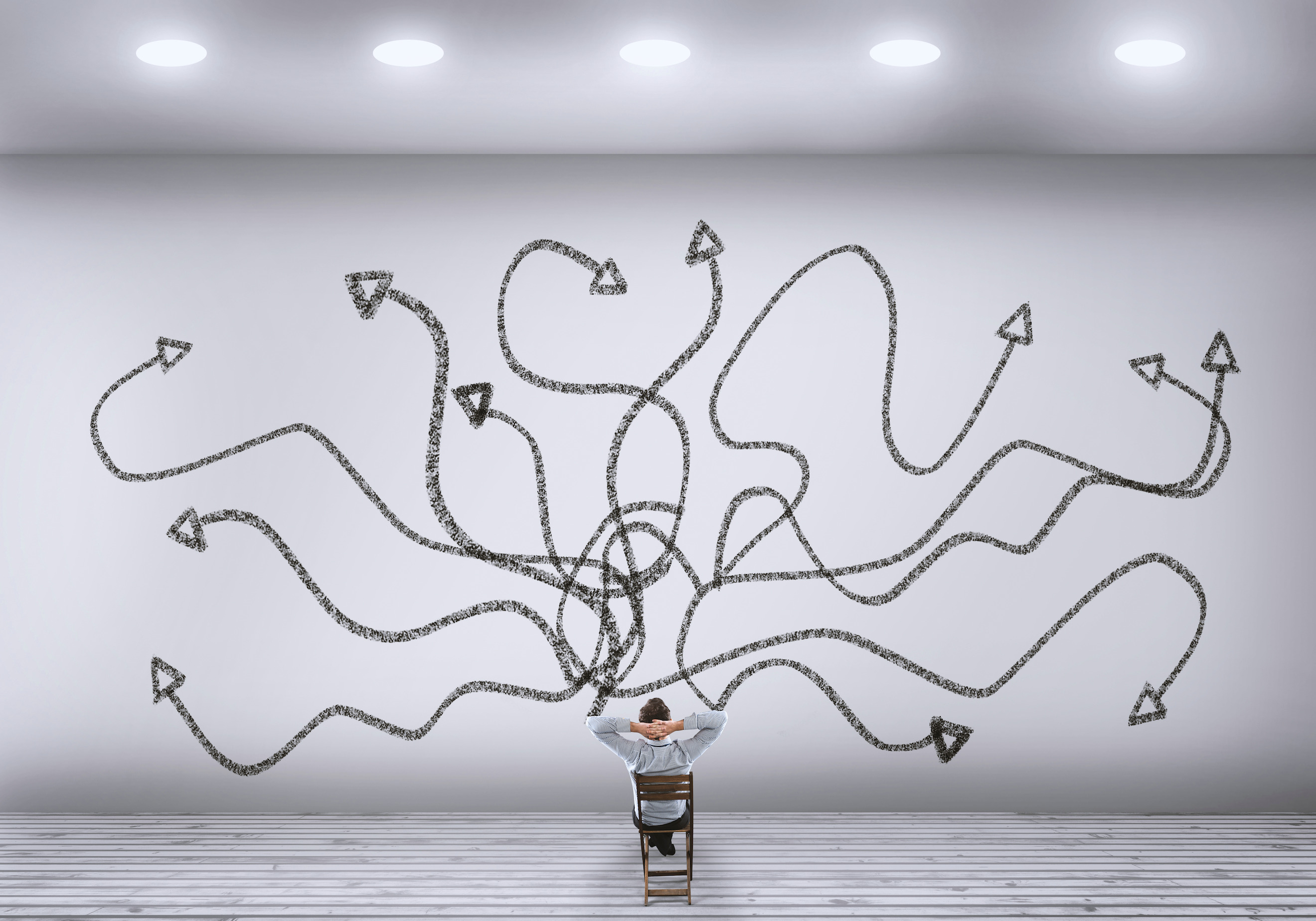何故、世の中に「変わったもの」「珍しいもの」が存在するのか。それは当たり前のことだが、人々が生きる社会や時代の影響から「常識」「スタンダード」ととらえられ、大切にされてきたものが存在しているからこそ、その「枠」から外れたものが、「変わったもの」「珍しいもの」と認識されるのだ。それは「貴重」なものとして大切にされる場合もあるが、時には「異常」だとして、排撃されることもある。
また、「変わったもの」「めずらしいもの」は、たまたま結果的にそうなってしまったものと、人と違うこと、「常識」をくつがえす、または単に目立ちたい、誰かにおだてられてその気になって…などと、「狙って」やって、そのように人々から評されることになったものなど、さまざまだ。それは本来、「危ない」「怖い」ものや状況を表す博徒・ヤクザ言葉の「ヤバい」が、いつの間にか一般社会に広まって、本来の意味に加え、「信じられない!」という衝撃を表したり、果ては「カッコいい!」「凄い!」などの感嘆、賞賛の意味をも持つようになってしまったことと、似たような現象なのかもしれない。
熊谷市の広瀬地区にある上円下方墳の宮塚古墳
今年の8月2日には最高気温41度と予想されるなど、「日本一暑い町」として有名な埼玉県熊谷市の中央部から若干西寄りの広瀬地区に、「お供え山(やま)」と呼ばれていたこともあったという「宮塚(みやづか)古墳」がある。「古墳」といっても、広い田園地帯と上越新幹線の高架があるところに、こんもりと木々が茂った一角があり、「よくある村の鎮守様かなあ」と通り過ぎてしまうような、小規模の古墳だ。だがこれは、日本国内でも例が少ない「上円下方墳(じょうえんかほうふん)」、すなわち、壇状になった方形(四角形、または正方形)の上に、円形の墳丘が重ねられているもののことで、宮塚古墳の場合、過去の水田耕作によって、かなり形を変えられているということだが、上円部が直径10m、下方部が西辺24m、東辺17m、高さ4.15mと判明している。今現在、発掘調査そのものがなされていないため、この古墳の正確なところはわからないが、古墳時代の終末期、7世紀末頃の築造だと考えられている。
上円下方墳とは
「上円下方墳」とは、699(文武天皇3)年に造営が始まったと考えられる、京都市山科区にある「天智天皇陵」が有名だが、その源流は奈良県高市郡明日香村の、墳丘の盛土が失われ、巨大な横穴式の石室が露出した状態の「石舞台(いしぶたい)古墳」が源流であるという説もある。いずれにせよ、極めて珍しい形状だ。
国内最大の上円下方墳は東京都府中市にある武蔵府中熊野神社古墳
明確に上円下方墳だと確認されているもののうちの1基で、国内最大とされるものが、東京都府中市西府町(にしふちょう)に所在する、「武蔵府中熊野神社古墳」がある。7世紀中期以降に造られたと考えられているが、2008(平成20)年7月〜2009(平成21)年3月、建設会社の鴻池組(こうのいけぐみ)によって、復元工事が行われた。美しい河原石(かわらいし、玉石(たまいし)とも言う)で全体を覆われ、1段目が約32mの方形、2段目が約24mの方形、3段目が直径約16mの円形という、3段構造になっている。
また副葬品として、長さ4.1cm、幅3.6cmの、鉄地に銀で、陰陽五行(おんようごぎょう)思想の木・火・土・金・水、そして日(陽)と月(陰)の七曜(しちよう、7つの星のこと)を表す七曜文(もん)の象嵌(ぞうがん)が7ヶ所施された鞘尻金具(さやじりかなぐ)や鉛ガラス製の小さな玉、鉄の刀子(とうす、今日で言う小刀(こがたな)のこと)が出土している。特に鞘尻金具の「七曜文」は、683(天武天皇12)年に鋳造されたという富本銭(ふほんせん)に用いられていたモチーフでもあることから、歴史学・考古学的にとても貴重なものである。
こうしたことから、この古墳がある「府中市」という場所は、奈良時代初頭に今日で言う「県庁」のような役割を担った「武蔵国司」(こくし/くにのつかさ)が置かれた重要な場所であったことを鑑みると、誰が埋葬されたのかは不明だが、恐らく、土地の有力者であったばかりでなく、歴代天皇並びに官人、そして天智天皇陵の造営そのもの、またはその工法をよく知る技術者たちとのつながりが深い人物だったと推察される。
府中市の武蔵府中熊野神社古墳から、熊谷市の宮塚古墳まで、およそ90km離れており、車で1時間ちょっとかかる。とはいえ熊谷市もかつては府中市と同じ武蔵国に属していたことから、古墳造営に関し、どちらが「先」か「後」かは不明であるが、何らかの人的交流・交通があった可能性は捨てきれない。
作家の五木寛之の死を感じた実体験
「病気、災害、喪失の悲しみ、事故、自殺/生と死の恐れを鎮める48の問答集」が収められた『死の教科書』(2020年)という本がある。ある読者の、「コロナウィルスの感染が拡大しているのに平気で外出したり、記録的な大雨で川が氾濫しそうなのに避難しない人がいます。疾患や災害で自分が死ぬかもしれないのに、彼らはどうして適切な行動が取れないのでしょう?」という問いに対し、著者の五木寛之(1932〜)は、「自分の死の実感がないから、危機感をもてず、自分や人の命を守るための判断も行動もできないのではないでしょうか。とはいえ、現在進行形で紛争が起こっている海外の国々や、戦時中や敗戦後の時代ならともかく、表向きは平和で、身のまわりで差し迫った命の危険を感じることなく生活ができる現代の日本において、常日ごろから死の実感をもちながら暮らしていくのは容易ではありません」と答えた。次に、五木自身の体験を紹介している。まだ若い頃、五木が作家デビューして数年目の時、突然心臓が苦しくなり、呼吸ができなくなった。その発作はすぐに治まったものの、その時の、「身動きのできない絶望感、自分がまるで見えない世界に滑りこんでいくような奇妙な感覚は、いまでも忘れられません」と述べている。その後も何度か五木は、「今度こそ自分は死ぬかも」と感じた瞬間はあったが、時が経過するうちに、その死の実感は薄らいでいったという。そのことから、死の実感が何ヶ月も、何年も持続するものだったとしたなら、過剰なストレス状態となり、人間は生きていけないのではないか。忘れてしまうことで、何もなかったかのように生き続けることができるのは、人間が先天的に備えている心理的メカニズムで、生命維持のために必要なことだと言っている。それに加えて、1981(昭和56)年に作家活動を休止し、仏教系大学である龍谷大学の聴講生となって仏教を学び、蓮如(1415〜1499)や親鸞(1173〜1263)、日本や海外の寺院に関する本も多く著した五木らしい感受性だと思われるが、「われわれは見るべきものを見ず、感じるべきものを感じないで、大きな欠落を抱えたまま、生き続けてしまっているのかもしれない」と締めくくっている。
最後に
「宮塚古墳」も「武蔵府中熊野神社古墳」も、大昔に亡くなった人の「お墓」である。古墳の外側の「形状」や棺の形、そして副葬品の数々などを鑑みると、造立当時の人々が抱いていた「死」そのもの、そして死者を「祀る」ことへのこだわりが強く見えることは言うまでもない。五木が指摘するように、「死の実感」や「危機感」が持てない。または古過ぎて「お墓」の現実味を感じることができないため、我々は物珍しい、または貴重な「大昔の遺物」としてしか古墳を捉えていないが、それは、『死の教科書』の質問者が投げかけた「コロナウィルス」や氾濫した川など、人間の命をおびやかす、それゆえに「恐ろしい」疾患や災害に対して、自粛せず無防備に出歩いたり、避難しようとしない人々の態度と同じといえば同じかもしれない。しかし、古墳造営に関わった人々や、主人を失った家族からしてみれば、古墳は興味本位で近づいて眺め回すものではなく、聖なる場所、或いは、「穢れ」である「死」を封じ込めた、ある意味禁断の場所でもあったはずだ。
日本国内には、今回取り上げた上円下方墳のみならず、興味あふれる古墳がたくさんある。実際にそれを見、それに関する調べごとをする際には、死を忘れて生きている我々は、五木が言うように、少しでも葬られた人、造営者、遺族たちが関わり、感じていた「死」を意識し、「見るべきものを見」、「感じるべきものを感じ」、更には、先に挙げた古墳にまつわるすべての人々への敬意や弔意を抱きつつ、場に臨みたいものである。
参考資料
■高橋源一郎(編)『武蔵野歴史地理 第4冊 多摩川北岸地方/多摩川南岸地方』1932/1972年 有峰書店
■梶拓二(編)『埼玉大百科事典 第5巻』1975年 埼玉新聞社
■「武蔵野叢誌」第19号(1884年8月21日発行)府中市立郷土館(編)『武蔵野叢誌 下』1978年 府中市教育委員会
■「天皇陵 天智天皇 山科陵」『宮内庁』2004年
■「国内最大の上円下方墳/7世紀前半、東京・府中市」『四国新聞社 SHIKOKU NEWS』2004年5月25日
■「武蔵府中熊野神社古墳」『古墳 全国の古墳巡り』2004年6月5日 /
■府中市教育委員会・府中市遺跡調査会(編)『府中市埋蔵文化財発掘調査報告 第37集 武蔵府中熊野神社古墳』2005年 府中市教育委員会
■府中市教育委員会・府中市遺跡調査会(編)『上円下方墳 武蔵府中 熊野神社古墳 調査概報』2005年 学生社
■府中市教育委員会生涯学習部生涯学習課文化財担当(編)『新版 武蔵国府のまち 府中市の歴史』2006年 府中市教育委員会
■「やましなを歩く東海道4御陵 天智天皇山科陵」『京都市山科区』2007年11月7日
■梅本哲明「国史跡武蔵府中熊野神社古墳の復元」『技術広報誌 ET』454号 2009年7月1日『KONOIKE』
■三橋浩・相原精次『関東古墳散歩 -エリア別徹底ガイド 《増補改訂版》』2004/2009年 彩流社
■「宮塚古墳」『熊谷市』2013年3月13日
■斎藤忠「上円下方墳」国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典 第7巻』1986/2016年(451頁)吉川弘文館
■府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課「リーフレット 府中の古墳」2016年3月 ふるさと府中歴史館
■府中市文化スポーツ部ふるさと文化財課「リーフレット ふるさと府中の歴史・文化遺産を訪ねて No.2 国史跡武蔵府中熊野神社古墳」2017年3月 ふるさと府中歴史館
■五木寛之『死の教科書 −心が晴れる48のヒント』2020年 宝島社
■「国史跡武蔵府中熊野神社古墳」『府中市』2021年9月13日
■「列島各地で猛烈な暑さ、埼玉・熊谷市では41度の予想…気象庁が熱中症への厳重な警戒呼び掛け」『讀賣新聞オンライン』2022年8月2日
■「山科区 天智天皇陵」『京都府観光連盟公式サイト 京都府観光ガイド』
■「散策スポット 石舞台古墳」『公益財団法人 古都飛鳥保存財団』
■「観光 石仏・石造物・祠:石舞台古墳」『なら旅ネット<奈良県公式観光ガイド>』