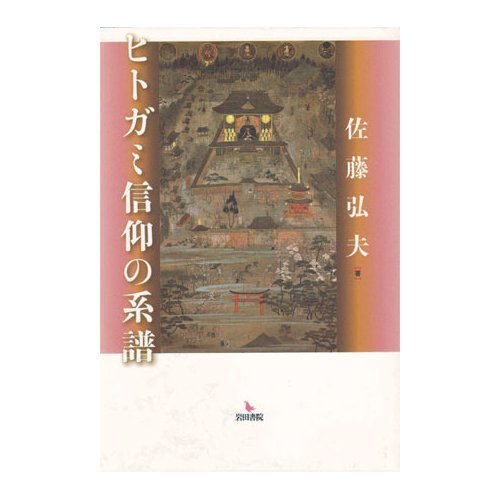民俗学者の小松和彦(1947〜)は『神になった日本人 私たちの心の奥に潜むもの』(2020年)の中で、日本における「ヒトガミ信仰」について、誰でも祀りたい人の「たましい」を「神社や寺をつくって、祀ることができるようだ」と述べた。
前編はこちら

「ヒトガミ信仰」という日本の風習
仮に小松自身が亡くなったとしたら、火葬された小松の「骨」は「墓」に埋葬される。そしてその「墓」は小松の遺族にとって、小松についての「記憶の場所」でもあり、小松の「たましい」が眠る場所である。しかもそれらを管理するのは、小松の遺族である。特別な偉業を成したわけではない「一般人」であれば、「記憶の場所」(記憶の依代(よりしろ))は「墓」で十分だ。しかし、「やっかいなこと」がある。「骨」や「墓」ではない「たましい」の場合は、その管理者・祭祀者があいまいだ。極端な話をすると、小松の「たましい」を祀りたい者は、小松の遺族の許可がなくとも、邸宅内などに社殿をつくって、勝手に祀ることができると、小松は指摘する。しかも祟り鎮め系・顕彰系を問わず、特定の人物の「たましい」を祀ろうとするのは、家族・親族の範囲での「記憶」「追悼」を超えた、政治(権力者)、信仰(信者)、学問(弟子)、生業(ムラ)等さまざまな集団が、その人物の人生や偉業を称賛し、末長く記憶し続けたいと思ったためだ。その「思い」が強ければ強いほど、「忘却」を防ぐ強力な「記憶」「追悼」施設が求められた、と小松は結論づけていた。
場所を作るという行為を通じて思いを届けた安倍正弘
もちろん安倍は、小松が言うように「勝手に」東郷を顕彰する「場所」をつくったわけではない。しかし、その「思い」が強烈だったことはよくわかる。
偶然だろうか。東郷神社がある渡地区から少し離れた天神町(てんじんまち。現・福津市津屋崎3丁目)に「新泉岳寺(しんせんがくじ)」という「墓所」が所在する。「泉岳寺」といえば、東京都港区高輪にある、赤穂の四十七士の墓所がある曹洞宗の寺院のことだ。それが何故、「新」で、やはり「福岡県」なのか?それは、医師で地域の篤志家でもあった児玉恒次郎(1866〜1939)が、大正2(1913)年に建立したものだ。児玉は、『元禄快挙録』(1909年)などを著し、赤穂の四十七士を称賛した、福岡藩士の末裔で、史論家の福本日南(にちなん、1857〜1921)の「思想」を、浪曲師の桃中軒雲右衛門(とうちゅうけんくもえもん、1873〜1916)の「語り」で全国的に広めることに尽力したのだ。その功績によって、高輪の泉岳寺から、「新泉岳寺」の名前と、四十七士の墓の砂を「分霊」として持ち帰ることを特別に許されたのだ。しかも「ここ」では今なお、毎年12月14日の討ち入りの日に四十七士の行列や法要が営まれている。
児玉の「行い」を安倍が実際に見聞きしたり、新泉岳寺に詣でたりしていたかどうかはわからない。しかし「狭い町のこと」で、安倍が児玉のことをよく知っていた可能性は大きい。だとしたら、安倍の「東郷」への熱い思い、そしてそれを顕彰するための「場所」をつくる「行動力」は、児玉を「見習った」ものなのではないか。
著名な歌人による追悼で偉人化されていった東郷
話が戻るが、福本日南が記述した「赤穂四十七士」たちは、今日我々がよく知る「忠臣蔵もの」の典範となった。しかしそれらは必ずしも「史実」に即したものだったとは限らないようだ。とはいえ、インターナショナルランゲージでもあるSamuraiを含む「侍」のありようやイメージに、それが今日もなお、強い影響を与えていることは間違いない。東郷に関して言えば、「顕彰」されるべき「偉人」という存在を超え、第二次世界大戦時を頂点に、「戦意高揚のための軍神」化してしまった事実は否定できない。
東郷が亡くなった際、多くの人々が東郷を追悼し、さまざまな詩や和歌を残していた。例えば1904(明治37)年、日露戦争で旅順に出征していた弟に捧げる詩、「君死にたまふことなかれ」(どうか我が弟よ、死なないでくれ)をつくった与謝野晶子(1878〜1942)は、先に挙げた『東郷元帥景仰録』(1935年)において、「東郷元帥を悲しみて」という題をつけ、以下を含めて5つの歌を詠んでいる。
「東洋の昇平の日を定めつる船いくさ統(す)べこの日神(かむ)さる」
(1905(明治38)年5月、日本海海戦を指揮し、28日にロシアを破り、東洋諸国が平和に治められることになった日を定めさせた東郷だが、30日には『東京朝日新聞』にその大勝利が報じられた。それと同じ30日に、東郷がお亡くなりになられたのは、とても感慨深い)
もちろん与謝野晶子同様に、東郷の死を心から悼み、優れた作品を残した、北原白秋(1885〜1942)、斎藤茂吉(もきち。1882〜1953)、佐佐木信綱(のぶつな。1872〜1963)、土井晩翠(ばんすい。1871〜1952)ら、日本を代表する錚々たる歌人たちには何の罪もない。しかし「第二次世界大戦」を「聖戦」と定め、外交交渉などによる回避や降伏などはとんでもない!国民全員一致団結して戦わねばならない!と、戦争を積極的に推し進めたかった人々にとっては、それを「正当化」するための東郷が「偉人」で「立派」な人物でなくてはならなかった。
偉人化によって懸念される戦争賛美への利用
日本史において、古墳時代(3世紀中頃〜7世紀)とされる時期に、地域の有力首長、或いは天皇などを埋葬した、巨大な前方後円墳が各地に建造された。それは古代人がただ、「大きな墳墓」をつくったというわけではなかった。文書などの具体的な記録が残されていないことから、我々は墳墓そのものの形態、周囲に据え付けられた埴輪、首長の埋葬のされ方、副葬品などで、「当時」を知るしかない。推測されることは、「遺体」そのもの、または「魂」「神」などに対し、作物の出来や天候などの吉兆を占ったり、祈ったりした、何らかの形式に則った祭祀活動が行なわれていたこと。そしてそのような儀式を行う「場所」である墳墓そのもの、そしてその一帯が「聖地」として、その地域を外敵や天変地異から「守る」と信じられていたこと。また、もしもそこで誰かが「イタズラ」や「悪さ」をすると、その人物のみならず、地域全体に害悪が及ぶ、と信じられていたこと…などだ。そこまで古い「顕彰の場所」であれば、多くの人々は被埋葬者が「どのような人物であったか」「何をしたか」はさておき、「雄大な歴史のロマン」に浸ってしまう。しかし「東郷平八郎」はおよそ1800年前につくられた前方後円墳の埋葬者よりは、はるかに「若い」。となると、まだまだ、第二次世界大戦時同様、今後の日本において、「ナショナリズム昂揚」「戦争賛美」のために「利用される」という懸念が生じてしまうのは、無理からぬことなのかもしれない。
東郷神社の場所が大峰山の山頂以外に考えられなかった理由
話は飛ぶが、漢字研究の第一人者である白川静(しずか。1910〜2006)は、古代中国の甲骨文字の精査から、「戦」の字は盾を意味する「單(旧字)」にもう1つの武器「戈(ほこ)」を加えたもの。「争」の字は「上下の手で、棒状のものを引き合って、共に争う」ことから来ていると結論づけた。それは今でも「同じ」意味であろうが、例えば、「劇」という字は、古代中国において、戦う前に神前で虎の姿で暴れる者を刀で討伐するという、勝利を祈る神事が行われていたことがはじまりで、似た漢字である「戯」も、脚の高い腰掛けに虎の頭をつけた人を後ろから「戈」で打つ神事を表していた、と解き明かした。「勝つか負けるかわからない」。古今東西、時の運で「負け戦」だったものが逆転し、勝ちを手にする場合もあれば、「間違いなく勝つ!」と信じられていたものが、兵隊や将軍たちの「油断」「驕り」ゆえに大敗北を喫することもある。しかも白川は、古代中国に限らず、古代ギリシャの叙事詩においても、「戦争は、むかし神々の争いであった…(略)…神々の愛憎が、氏族や英雄たちの運命を支配していた」と述べてもいた。「いくら考えても、敗因がわからない」として、「もしかしたら、非業の死を遂げた敵方の○○の呪い…」のせいで負けたと信じられる場合も少なくないだろう。だからこそ戦争は、言うまでもなく国民と国民、国と国、地域と地域…などの「揉め事」だが、「宗教」という形式や制度が出来上がる前から、「神的なもの」への親和性が極めて高い側面がある。それゆえに知将・名将が「ヒトガミ」となり、勝利を導いてくれるものだと信じられた。また人々は、それにすがらずにはいられなかったのだ。
また、日本中世文学の研究者である久留島元(くるしまはじめ、1985〜)は「神話」について、「神々の時代を再現し、繰り返し演じたり語ったりすることで人々は神話を共有し、共同体としての結束を固めた。神話の主人公は英雄であったり、神の子孫である王族であったりするが、神話を共有し伝えていくのは…(略)…被支配層をふくめた共同体である」。「各共同体でそれぞれに生まれる」、「世界認識の表出の作法であり、共同体内のコモンズであった」と述べている。もちろん「東郷平八郎」も「安倍正弘」も、「神々の時代」の人々ではないが、神話における「物語」とは久留島が言う、「共同体の世界認識の再確認の手立て」だったことを勘案すると、「日本海海戦」が目には見えないものの、その轟音を耳にし、硝煙の匂いを嗅ぐことなど、「五感」で体験した安倍にとって、日本という「国」を世界的に知らしめることとなった大海戦が、「ここ」こと、大峰山の「ほんの少し先」で展開したことは、「極めて重要なこと」なのだ。しかもその勝利を導いた「東郷平八郎」という人物を顕彰するための施設を建てるにしても、東郷の生まれ故郷の鹿児島県でも、東郷の私宅があった、東京市麹町区上六番町(現・東京都千代田区三番町)でもない。現在の日本大学や東京大学で獣医学を学んだ安倍で、卒業後もしばしば訪れた「場所」でもあり、東郷が生涯「本拠地」としていた「東京」であっても、「違う」。「日本海海戦に大勝利した日本」を認識するための「再確認の手立て」としての「東郷神社」の「場所」は、「大峰山の山頂」でなくてはならなかったのだ。
戦争肯定の道具として利用されることを嫌った安倍正弘
旧・唐津藩主の小笠原家の流れを汲む海軍中将・小笠原長生(ながなり。1867〜1958)の長男であった文筆家で映画製作所主催者でもあった長隆(ながたか。1900〜1946)は「淳隆(あつたか)」の筆名で1943(昭和18)年、『大東郷 改訂版』において、「東郷大将の真心・忠節・仁愛・勇気・決断・智謀・信念」を一まとめにしたものを「東郷精神」と定義した。それは日本海軍の中枢精神となって持ち伝えられ、実を結ばせている。しかもそれは、ただ精神上のことではなく、最新の兵器を縦横に駆使して敵を倒す物質面と並行して、邁進していると誉めている。「東郷精神」という言葉がただ単に「東郷平八郎」の「偉業」や「尊敬に値する性格の持ち主だったこと」を比喩的に言い表し、東郷を顕彰する「だけ」に用いられている分には、まだ罪はないかもしれない。しかし、1942(昭和17)年6月のミッドウェー海戦での日本海軍の大敗北を契機に、日本の戦況は一気に悪化していた。「あの」日本海軍が「大敗北」…そうした中、「東郷精神」という言葉が「強調」されたことを、もしも東郷が当時生きていたとしたら95歳だっただろうが、果たしてそれを許諾していただろうか。苦境を強いられていた日本軍を優勢に導き、日本海海戦同様の大勝利に終わらせるために、喜んで自分の生き様や考え方を、兵隊たちや民草の見本であろうとしていただろうか。現実の東郷は、日本の「そのような状況」を目にする、実際に体験する前に、亡くなった。それゆえに東郷の存在そのもの、そして「東郷神社」は、軍人たちはもちろんのこと、全て国民に向けて、あの禍々しい戦争を正当化し、邁進させるための「道具」になってしまった側面があった。だからこそ「東郷神社」創建、そしてその施設の発展・維持を通して顕彰し続けた安倍も、それは望んでいなかったはずである。
政治利用されることなく残り続けている東郷神社
日本の敗戦直前の1944(昭和19)年3月15日、アメリカ国務省戦後計画委員会(Post War Committee; PWC)が日本における神道と信教の自由に関し、「日本:信教の自由(Japan: Freedom of Worship)」という文書を作成していた。宗教社会学者の中野毅(1947〜)によると、この文書における問いは、「神道を一宗教として、極端な国家主義(extreme Nationalism)から区分するのが困難であることを考える時、占領軍は日本に信教の自由を許すべきか否か」というものだった。PWCは日本の神道を古神道(Ancient Shinto)と、極度に好戦的な国家主義儀礼である国家神道(National Shinto)とに区別する必要性を強調していた。さらに当時の日本に所在していたおよそ10万の神道神社を、大きく3範疇に分類した。1つ目は、古代に起源を持ち、地域の守護神を祭る大部分の神社。これのみが、厳密な意味で宗教的な神社である。2つ目は、天照大神を祭る伊勢神宮のような神社で、これらも古代に起源を有するが、国家主義の象徴的存在になっている。3つ目は靖国神社や明治神宮、乃木神社、東郷神社のような、近年建立された、国家的英雄を祭る神社。これらはPWCからすると、宗教的崇拝の場所ではなく、軍国主義的国家主義精神を鼓舞する国家主義的神社とみなされた。
それゆえ彼らは、3つ目の神社を問題視した。「膨張主義的軍国主義の思想的装置」と捉えられたからだ。とはいえ「信教の自由」の原則があることから、すぐにそれらを廃絶させようとはしなかった。強制的閉鎖が「逆効果」を招く恐れがある。これらの神社における示威行進や集会、儀礼を廃止し、施設管理に必要な人員以外は解雇し、国家からの給与の支給は停止すべきであるとしつつも、公的秩序や安全保障に反しない限り、個人的信仰の対象としては公開存続を許されるものとする、と勧告していた。
その文書完成からおよそ1年半後、敗戦による無条件降伏から、先の神社たちはその「勧告」を受け入れた。だからでこそ、「今」も存続している。殊に靖国神社の存続そのものや、政治家の参拝に関しては、81年前の「問題視」を超え、現在に至るまで、毎年終戦記念日前後になると、国内外での激しい政治摩擦が繰り広げられている。とはいえ、「戦意高揚」ではなく、「個人的信仰の対象」としての、安倍が創建した「東郷神社」は今日も存続している。
ヒトガミ信仰は今後も生まれるのか
平成(1989〜2019)、或いは令和(2019〜)において、東郷のように、神社仏閣の祭神に祀り上げられる偉人はいるのだろうか。
2024(令和6)年に亡くなった著名人、例えば『Dr.スランプ』(1980〜1984年)や『ドラゴンボール』(1984〜1995年)の作者で国民的漫画家の鳥山明(1955〜2024)、世界的ピアニストのひとりであるフジコ・ヘミング(1931〜2024)、今年であれば、「ミスタープロ野球」の長嶋茂雄(1936〜2025)…他にも多くの人々がお亡くなりになったが、誰かしらが近い将来、安倍のように強烈に慕う人物によって「○○神社」や「○○寺」などにお祀りされることになるのだろうか。遺族の知らないうちに、先に挙げた小松の言葉のように、人知れず祀ってしまう場合もあるだろう。それによって、「他のファン」も「そこ」に押しかけ、SNS上で「素晴らしい!」「よかった!」「感動した!」などと広まり、それに対するアンチから、「即刻壊せ!」「爆破予告!」…等々の大騒ぎになってしまったら…考えるだけで、ゾッとする。叶うなら、亡くなられた方の魂そのものの安寧、そして遺族が心静かに日々を送りつつ、命日やお彼岸、お盆、そして年回忌などの節目節目に供養を続けられるよう、どうか「金儲け」や「派手なもの」の建立だけは、控えてもらいたいものだ。
参考資料
■博多湾鉄道汽船株式会社(編)『博多湾鉄道路線名勝案内』1924年 博多湾鉄道汽船株式会社
■海軍兵学校(編)『東郷元帥景仰録』1935年 大日本図書
■小笠原長生(編著)『聖将東郷全伝』第3巻 1941年 聖将東郷全伝刊行会
■田中周二『東郷平八郎』1942年 学習社
■小笠原淳隆『大東郷 改訂版』1943年 弘学社
■安倍正弘『東郷公園』1965年 安倍正弘(私家版)
■東郷公園史蹟保存会(編)『いのちの限り 安倍正弘翁の半生』1970年 東郷公園史蹟保存会
■原田種夫『筑紫路』1978年 保育社
■山田尚二「東郷平八郎」南日本新聞社鹿児島大百科事典編纂室(編)『鹿児島大百科事典』1981年(725〜726頁)南日本新聞社
■山田清「渡(わたり)半島」西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部(編)『福岡県百科事典』下巻 1982年(1124頁)西日本新聞社
■小笠原長生(編著)『聖将東郷全伝』第2巻 1940/1987年 国書刊行会
■中野毅「占領と日本宗教制度の改革 -戦後日本の世俗化過程の一考察」『東洋学術研究』第26巻 1987年(174-193頁)東洋学術研究
■北九州史跡同好会(編)『北九州の史跡探訪:知的なレジャーのために 増補・改訂版』1990年 福岡自費出版センター
■新倉善之「東郷寺」圭室文雄(編)『日本名刹大事典』1992年(65頁)雄山閣
■新谷尚紀「【博士論文】死・葬送・墓制をめぐる民俗学的研究」1998年 慶應義塾大学
■津屋崎町編さん委員会(編)『津屋崎町史 通史編』1999年 津屋崎町
■中野毅「【博士論文】戦後日本国家と民俗宗教の政治参加:宗教学的一考察」2001年 筑波大学
■平川祐弘「日本海海戦100周年記念歴史セミナー 『世界を変えた日露戦争』基調講演:『亡びるね』 −日本における国際主義と土着主義の抗争−」『太平洋学会誌』2007年3月号(44-64頁)太平洋学会
■野口文「本日天気晴朗なれど波高し 日露戦争・日本海海戦と福岡」石瀧豊美(監修)『図説 福岡・宗像・糸島の歴史』2008年(182-183頁)郷土出版社
■隈元正樹「近現代の仏教における慰霊と顕彰 −聖将山東郷寺の創建と展開を事例として−」日本近代仏教研究会 代表・圭室文雄(編)『近代仏教』第17号 2010年5月(56-78頁)日本近代仏教研究会
■佐藤弘夫『ヒトガミ信仰の系譜』2012年 岩田書院
■「九州を知る!マンスリーコラム43 国ノ命運ヲ一身ニ 東郷平八郎 鹿児島出身」『F F G調査月報』2015年1月号(4-5頁)ふくおかファイナンシャルグループ
■「『軍神』慕う獣医師が私費で創建 【東郷神社・福津市】」『西日本新聞me』2015年5月8日
■これだけは知っておきたい 教科書に出てくる日本の神社 編集委員会(編)『これだけは知っておきたい 教科書に出てくる日本の神社』2015年 汐文社
■白川静『漢字の世界 1 中国文化の原点』2003/2016年 平凡社
■日本アソシエーツ株式会社(編)『日本の祭神事典 −社寺に祀られた郷土ゆかりの人びと』2014/2016年 日本アソシエーツ株式会社
■劉建華「義民の祭祀・顕彰 -寛延三義民を事例に」『東北宗教学』第13号 2017年(57-80頁)東北大学大学院文学研究科宗教学研究室
■松田十刻「東郷平八郎かく語る 『勝って兜の尾を締めよ』 日露戦争の真実 日本海海戦の戦略を読み解く 第16回(最終回)」『BEST TiMES』2017年2月15日
■「海軍大将 東郷平八郎を祀る『東郷神社』(東京都渋谷区)」『東京御朱印マップ』2017年10月16日
■「2017年に世界遺産として登録された注目の『神宿る島』へ!」『九州旅ネット』2018年5月17日
■「【昭和天皇の87年】世界が驚嘆した東郷ターン 『決戦は三十分で片が付いた』」『産経ニュース』2018年8月4日
■久留島元「第1章 物語と座の時代」日文研大衆文化研究プロジェクト(編著)『日本大衆文化史』2020年(28-49頁)株式会社KADOKAWA
■小松和彦『神になった日本人 私たちの心の奥に潜むもの』2020年 中央公論新社
■花田勝広(編著)『北部九州の軍事遺跡と戦争資料 宗像沖ノ島砲台と本土決戦』2020年 サンライズ出版
■『陸軍墓地・海軍墓地・護国神社・忠霊塔・忠魂碑参拝』2021年8月2日
■「【5月27日は何の日】117年前、日露戦争で日本海海戦が始まる」『ツギノジダイ』2022年5月27日
■「君死にたまふことなかれ(与謝野晶子)の意味 全文と現代語訳、背景も解説」『マイナビニュース』2024年3月1日
■須藤隆「白川静」近代文化史研究会(編)『死を語る50人の言葉 宗教家・学者・医師・芸術家の『死生観』』2023年(32-35頁)アーツアンドクラフツ
■小山鉄郎『白川静さんに学ぶ 漢字の秘密まるわかり』2024年 論創社
■「勝利を呼び込んだ『東郷ターン』 〜日本海海戦、ギリギリの決断」『WEB歴史街道』2017年5月27日/2024年12月16日
■丸山淳一「ドラマ『坂の上の雲』が描く日本海海戦…勝敗を分けた『丁字戦法』と『密封命令』の真実」『読売新聞オンライン』2025年2月26日
■「企画展『戦後80年 昭和100年 報道写真を読む』 『1億人の昭和史』から『毎日戦中写真アーカイブ』へ」『ニュースパーク 日本新聞博物館』2025年4月26日〜8月31日
■「日本海海戦から117年」戦没者慰霊 〜ゆかりの東郷神社で 福岡・福津市」『RKBオンライン』2022年5月27日
■「山の上に巨大な戦艦⁈ 日本海海戦ゆかりのスポット『東郷公園』|福岡県福津市」『Mediall』2023年7月12日
■「追悼 〜2024年に亡くなった著名人を偲ぶ〜」『Neowing』2024年12月12日
■「九州発 西部本社編集局 東郷平八郎をまつる福岡県の『東郷神社』例祭、日露の戦没者悼む…戦闘海域を遠望する日本海海戦祈念碑前で」『讀賣新聞オンライン』2025年5月27日
■『NHK 戦争を伝えるミュージアム』
■「元寇の遺産を巡る 鎌倉武士の抗戦〜海に眠る蒙古襲来の遺跡」『ながさき旅ネット』
■「地元の人々が愛するディープな福津 新泉岳寺」『DEEP福津』
■『勝運災厄摩利支神社ホームページ 楯崎神社ホームページ』