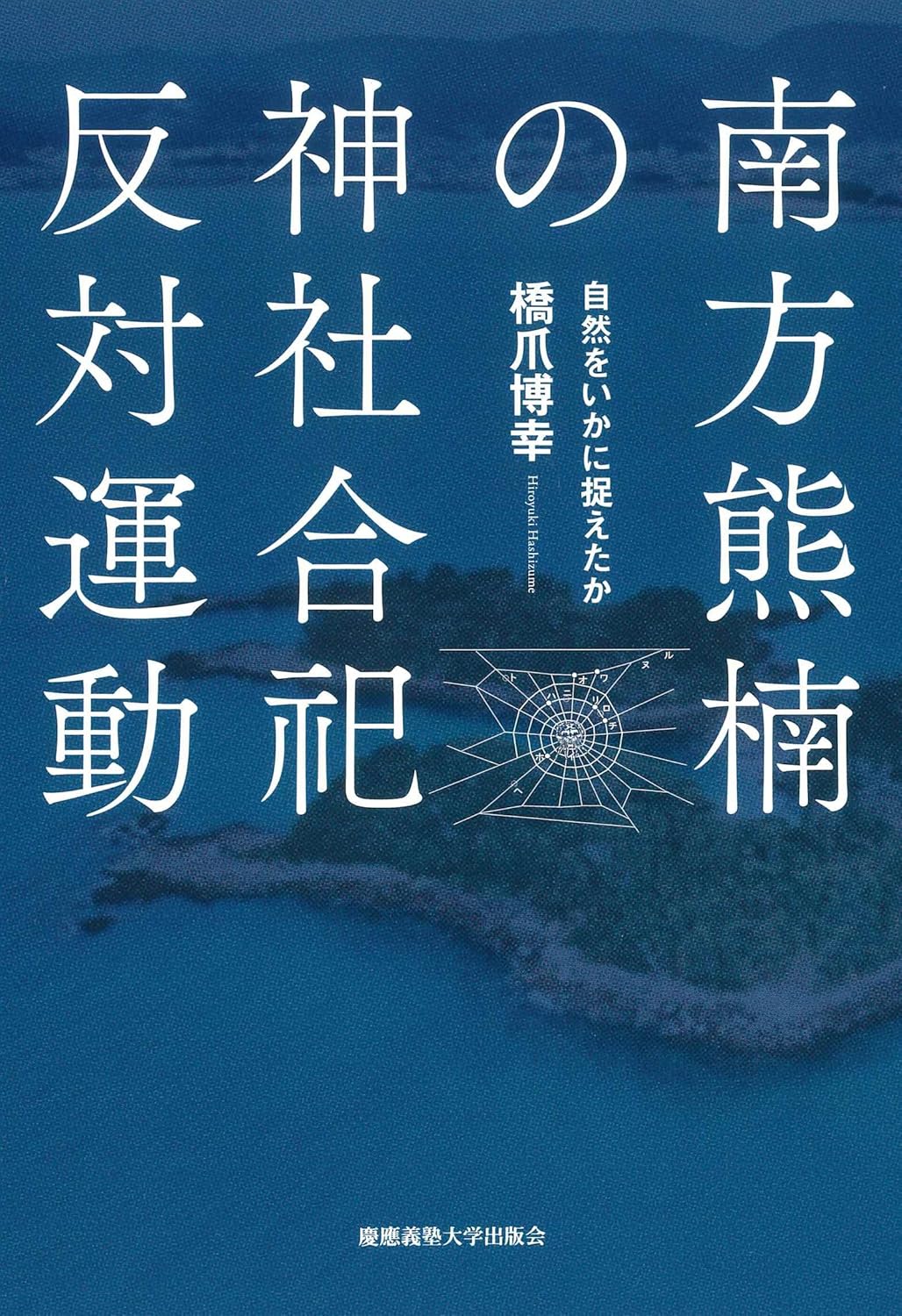神棚の榊は森を表している日本の豊かな山林は後に「神道」と呼ばれることになる日本古来の自然崇拝を育み、それは死生観・宗教観にもつながった。明治政府はそのような日本人の心性を束縛してしまいかねない政策を進めた。それに反対した一人が「知の巨人」として名高い、南方熊楠(みなかた くまぐす 1867-1941)である。

明治政府の神社合祀政策:国民統合と自然破壊の二つの顔
新しい葬送の形式のひとつに樹木葬がある。当たり前だが、厳しい砂漠の国ではできない送り方である。日本にはそれだけ豊かな自然があるということだ。日本人には自然と共存する心性が太古より受け継がれている。山や森、田畑、自然は神様に満ちていた。それを形にしたものが鎮守の森であり、社、祠といった神域だった。自然の怒りを鎮め、恵みに感謝するための小さな社や祠があちこちの村々に点在しており、そのひとつひとつに神が宿っていた。八百万の神と言われるように日本にはたくさんの神々がいる。天照大神や素盞嗚尊などの格式の高い神だけではない。地元には地元を守る「産土神」が民を見守っていた。
人間の魂もまた死後、自然に還り、一族の祖先の霊として田の神や山の神となり子孫の繁栄を見守るとされた。死後の魂が向かう黄泉の国は村・里を見下ろす山や海などにあるとされていたのである。
文明開化と称される明治時代、政府はこれら小さな神域を、町村の中心にあるメジャーな神社に合祀するなどして、全国の神社の統廃合を進めた。一連の「神社合祀政策」である。一町村に一神社として、その他の鎮守の森から神々を追い出し、神が去った土地として森林を伐採した。その目的は様々だが、第一の目的は神道の国教化、いわゆる「国家神道」の形成による国民統合である。明治政府は神道と神社を、天皇を頂点とした国教として、日本国民を精神的に束ねようとした。また、官製神社に統制機関や情報網といった、キリスト教教会の役割を担わせる狙いもあったようである。こうした中、特に苛烈な被害にあったのが和歌山県である。和歌山出身の天才学者・南方熊楠は、神社と森の関係に着目し、合祀された神社が尽く破壊されていく惨状に立ち上がった。
南方熊楠、立ち上がる:神社合祀に反対した「知の巨人」
南方熊楠。博物学者・生物学者・民俗学者。専門のみならず博覧強記を極め、その関心領域の広さと深さから「知の巨人」と称された。
熊楠は神社合祀に反対する理由として、神社と山林の関係について強調した。三輪明神などを例にあげ、古来にはむしろ老樹、大木だけがあって社殿がない古社が多かったという。神社そのものより森林自体が神域だったのだ。
地元に密着した身近な神社が消えてしまうと、神社との距離が遠くなり、敬神の思いが薄くなると指摘した。また神社は地元民同士の結びつきに大きな役割があり、信仰の拠りどころでもある。それらを滅却して大きな官製神社に一元化してしまえば、初詣などの形式的な参拝は残るかもしれないが、日常の生活と密接に結びついた信仰心は薄れる。民衆の心を支えてきた産土神(土地の神)との関係を断ち切ることになると批判した。
そして博物学・生物学者として看過できないのが、合祀された神社林が伐採されることである。熊楠には自然景観の破壊や貴重な生物・生態系が絶滅することのへの懸念があった。これらの点から、熊楠をエコロジー運動の先駆者と見做す見方がある(注)。
熊楠は民俗学者・柳田國男らとも連携し、精力的な反対運動を展開した。雑誌に論文や意見を発表し、地元住民への説得に励んだ。政治家・政府要人・知識人らに手紙や意見書送り、集会に招いて神社合祀の弊害を熱弁したこともある。こうした運動の結果、和歌山県などでは多くの神社が失われたものの、政府の合祀政策は一部で修正され、強制的な合祀は徐々に沈静化していった。
注:自然保護思想、エコロジー運動の先駆であったかについては議論がある。
仏教の日本化:山岳宗教へと変貌した信仰の形
仏教についても触れておきたい。明治時代といえば寺院も明治前半の廃仏毀釈の嵐で甚大な被害を被った。同じ時代に神社仏閣は共に甚大な迫害を受けたことになる。だが森林を奪われ土地から追放された神社に比べ、本来仏教は都市宗教であり、神社ほど地縁にはこだわらない。仏教にせよキリスト、イスラム教らは地縁を捨てることで世界宗教となった。ムスリムは世界のどこにいても聖地メッカの方角に向かって祈りを捧げる。彼らの心はメッカにある。仏教は聖地インドこそ荒れ果てているが、阿弥陀如来、大日如来、久遠実成の釈迦(あらゆる時代に遍く存在する釈迦)などは時空を超えた存在である。日本でも仏教は国家鎮護の目的から朝廷を中心とした都市宗教だった。
それが平安時代になると最澄と空海がそれぞれ比叡山、高野山を開き、仏教は山岳宗教へと変貌していった。日本人の自然観が仏教を飲み込んだといえる。仏教が葬儀に関わることになった一因として、日本人古来の自然観と、そこから生まれた死生観、つまり死者の魂と天地自然との関係が根底にあるのではないだろうか。熊楠も仏教、特に華厳思想と真言密教に多大な関心を寄せており、彼の学問論の中で最も重要とされる「南方マンダラ」を着想している。日本人の心性に宿る自然への思いは深いのである。
熊楠に渡った「錦の御旗」
熊楠の合祀反対運動は社会的に注目を浴びたが、実質的な成果は大きいとはいえなかった。和歌山、紀伊半島の神社合祀による伐採は膨大なもので守りきれなかった神社の方が多い。その中で、彼が特に力を入れ守りきった「神島」(田辺市)に1929年、昭和天皇が来訪した。その際、熊楠からご進講(天皇・皇族への講義)を受けた。天皇は熊楠没の後、熊楠を偲んで和歌を一首詠んだ。この事は、神社合祀の第一の目的を考えたとき、熊楠の運動が国家に対し最終的に勝利したといってよいのではないだろうか。
参考資料
■南方熊楠著/中沢新一編「南方熊楠コレクション〈5〉森の思想」 (河出書房新社)
■松井竜五著/ワタリウム美術館編「クマグスの森 南方熊楠の見た宇宙」新潮社(2007)
■志村真幸「未完の天才 南方熊楠」講談社(2023)
■長崎敏也「南方熊楠の環境保護に関する思想」『森林応用研究』8巻(1999)