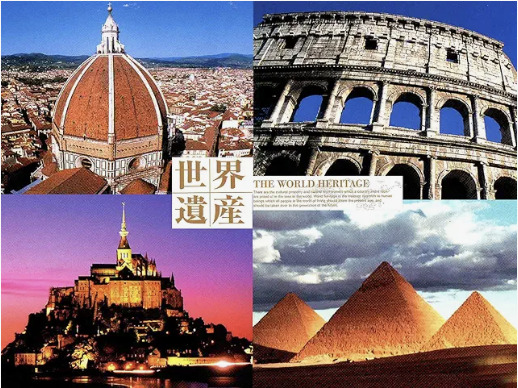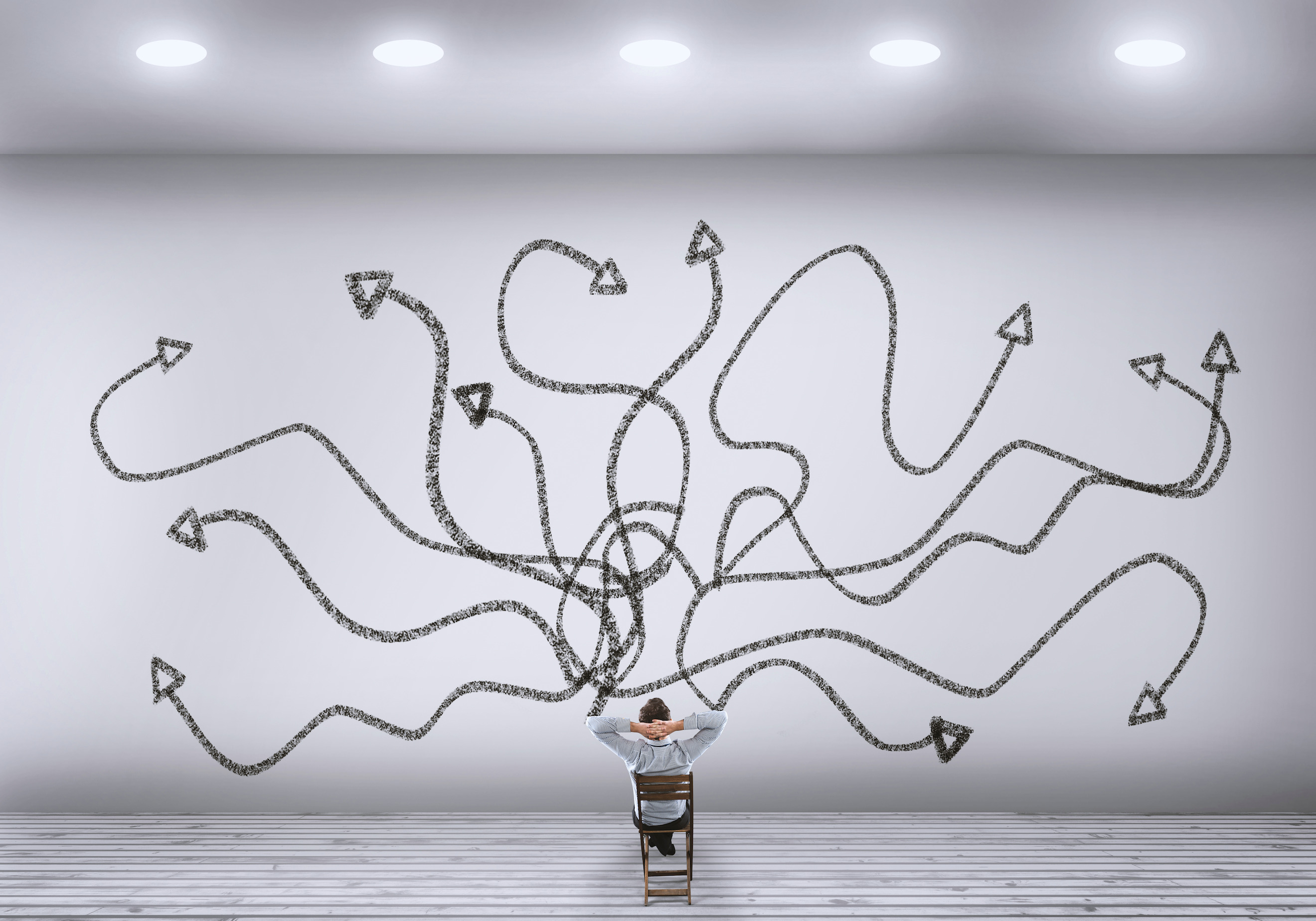アニメや漫画、アイドルなどの影響で「聖地巡礼」という言葉が一般化した。対象は神格化され、人はそれに触れようと旅に出る。スペインの聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼は数ある巡礼の中でも代表的な存在である。

キリスト教三大聖地 サンティアゴ・デ・コンポステーラ
サンティアゴ・デ・コンポステーラはスペイン・ガリシア州の州都であり、エルサレム、バチカンと並ぶキリスト教の3大聖地のひとつでもある。サンティアゴとはイエス・キリストの12使徒のひとり、聖ヤコブのスペイン語読み。この地にある大聖堂にはヤコブの遺骸があるとされており、ある者は贖罪のために、ある者は奇跡を求めて巡礼する。巡礼路のそこかしこにヤコブのシンボル「ホタテ貝」と矢印の標識が巡礼者を導いてくれる。各地には教会や自治体、ボランティアなどが運営する宿泊施設「アルベルゲ」があり、そのほとんどが無料。有料の場合も安価で提供されている。各地でスタンプを押すことができ、徒歩で100km以上、自転車では200km以上の巡礼、到達を条件に大聖堂から巡礼証明書が発行される。1993年、サンティアゴ巡礼路は世界遺産に登録された(1998年フランス側の巡礼路も登録)。
聖ヤコブ伝説が巡礼を呼び起こした理由
サンティアゴこと聖ヤコブは、紀元44年、ユダヤ王・アグリッパに迫害され斬首された。12使徒の中で最初の殉教者である。ヤコブの遺骸は埋葬を禁じられたが、弟子が密かに船で運び出しガシリアの地に埋葬した。以後、正確な埋葬地は忘れられたが、その地のどこかにヤコブが眠っているという話だけは伝えられていた。
9世紀、天使のお告げを受けた修道士が星の光に導かれ、ガシリアの野原に行くと不思議な光が放たれていた。その地点を掘り起こすとヤコブの遺骸が発見されたという。その地には教会が建てられた。これが後のサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂である。そこに行けばすべての罪が許されるとされ、多くの人々が巡礼に訪れるようになった。その後は聖人信仰を認めない、プロテスタントの勢力拡大やイスラム教やイングランドとの戦争などにより凋落したこともあったが、現在では世界遺産にも登録され、世界の巡礼路の中でも最も知られているまでになった。コンポステーラとは、カンポ(野原)とステーラ(星)を合わせた意味との説がある。
カトリックの核心 聖人・聖遺物信仰とは
これらの伝説にはキリスト教、特にカトリックにおける聖人・聖遺物信仰が見られる。キリスト教は本来、イスラム教と同じく偶像崇拝は禁止されている一神教である。だが信者は遠い存在である唯一神、創造神より、神に近い人間とされる聖人を敬い、贖罪や願望を神にとりなしてもらおうとするようになった。神の子イエスの直弟子、ヤコブともなれば聖人の中の聖人である。その墓が光の伝説と共に世に現れたとなれば、それまでの路はまさに天国への道といってよい。聖人ゆかりの聖遺物も同様で仏教の仏舎利(釈迦の遺骨)と同様、聖なる力が期待され信仰対象となった。サンティアゴ大聖堂はヤコブの遺骸が眠る墓である。まさに聖遺物の中の聖遺物といえるだろう。かくしてサンティアゴ・デ・コンポステーラを目指し盛んに巡礼が行われるようになった。
四国遍路との比較 ホタテ貝と同行二人
現在では観光の一部として楽しむ人々も多い巡礼だが、中世の時代は苦行そのものだった。現在のように舗装されているわけでもなく、大変な道のりだったようだ。彼らは杖と荷物、そしてヤコブのシンボルである「ホタテ貝の貝殻」を身に着け決死の旅に出た。ヤコブとホタテ貝の関係は、弟子たちが彼の遺骸をガリシア地方に水路で運んだ際、船の底にホタテ貝が付着していたという伝説に由来する。巡礼者たちは貝殻を握りしめ、ヤコブが守ってくれていると信じてひたすらに前進した。ある者は罪を浄めてもらうため、またある者は愛する人の病を癒すため。神へ続く道は祈り、願いの道であった。よく比較される四国遍路では、遍路笠などに「同行二人」の文字を書きつける。創始者である弘法大師・空海と共にいるという意味である。彼らは雨が降ろうと風が吹こうと、常に大師と共にいる。サンティアゴ巡礼者にとっても貝殻は、聖ヤコブとの同行二人といえるだろう。彼らはヤコブと共に歩くのだ。
また、四国遍路は一巡すると元の地点に戻ることができる。これに対しサンティアゴ巡礼は大聖堂へ一直線である。見方によっては、それぞれが仏教の円環的な世界観(輪廻転生、縁起)と、キリスト教の直線的世界観(天国、神の国)を表しているようにも感じる。
巡礼の真髄 歩く行為に秘められた意味
サンティアゴ巡礼路は殉教した聖ヤコブの痛み、苦しみを共に背負う道のりであり、「ヤコブと共に」彼の思いを追体験することで神に近づく道のりである。四国遍路も空海が辿った道を「空海と共に」旅する道のりである。その目的は様々だが、ゴールよりも歩くという行為そのものが神の愛に接する、救いへの道なのだろう。巡礼をひとつのイベントとして楽しむのも悪いことではないが、本来の宗教的な意味を考えて歩けば、遊び以上の何かが得られるかもしれない。
参考資料
■ホビノ・サンミゲル「四国遍路とサンディアゴ巡礼」『四国遍路を中心とした日本・世界の巡礼の総合的研究 平成20年度報告書』愛媛大学(2009)
■笹尾典代「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路 ―人はなぜ歩き続けるのか-」恵泉女学園大学ホームページ