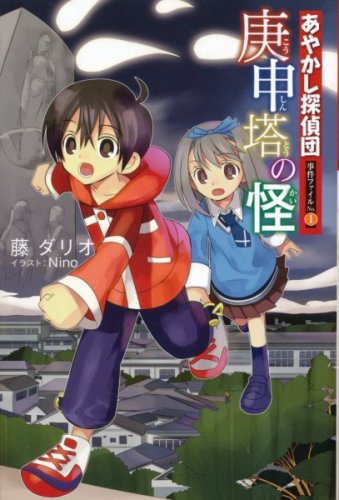日本全国に点在する庚申塚。中国から伝来した庚申信仰は日本においては、神仏習合を経て、祖先崇拝、死者への供養などが混じり独特の形になった。庚申信仰とは何か。葬儀との関係は。

中国道教に起源を持つ「庚申信仰」の基本
庚申信仰は中国の道教に影響を受けた民間信仰である。人間の身体には三尸という虫が住み着いており、60日に1回来る庚申(かのえさる)の日の夜、その人が寝ている間に天に昇り、天帝にその人の悪事を告げてしまうという。天帝はその悪事を記録し罪過の重さによって寿命を決定する。そのため一晩中起きていることで三尸の動きを封じることができる。そこで庚申の夜は朝まで語り明かし延命長寿を願った。これを「庚申待」といい、この集まりを「庚申講」という。
ここままでが中国発の民間信仰としての庚申信仰である。伝来後、そのままの姿でいられないのが日本独特の神仏習合で、庚申信仰も仏教・神道と習合し、庚申講では読経や念仏を唱えるようになった。その流れは三尸を封じるために強力な神を呼び寄せることになる。青面金剛(しょうめんこんごう)である。
仏教色が加わり本尊登場 庚申塔に刻まれた青面金剛と三猿
三尸を封じるための講(集まり)に読経や念仏が加わり仏教色が強くなると、講の中心となる本尊が登場する。不動明王などが知られる密教の忿怒尊である。怒りの形相と凄まじい霊力をもって悪鬼や煩悩を滅ぼす忿怒尊。さらにその忿怒尊は神仏習合によって、「青面金剛」となり庚申講の代表的な本尊となった。六面六臂の怒りの神で、青面金剛は三尸を捕らえ封じる。青面金剛の強力な功徳は、元々の目的である延命から疫病や災厄除けなど、庚申信仰の幅を広げていく。各地で青面金剛を供養する塔「庚申塔」が建てられた。庚申塔には青面金剛や「庚申」の「申」(さる)にちなんだ、見ざる言わざる聞かざるの三猿などの石像が彫られている。現代でも庚申塔は「庚申塚」とも呼ばれ全国各地に点在する。
檀家制度の定着とともに庚申講に加わった死者供養と葬儀仏教
庚申塔には「庚申板碑」というものもある。板碑(いたび)とは石製の供養塔のこと。庚申信仰とは別に中世では、死者への追善供養や、自身の現世での平安、または来世での安寧を祈る逆修(ぎゃくしゅ)供養のために卒塔婆が建てられていた。これを「供養塔婆」という。この供養塔婆が庚申信仰と混合して造られるようになった。
さらに江戸時代になると檀家制度が定着し、民衆の間でも仏式の葬儀が行われるようになる。その慣習は庚申講にも影響を及ぼし、庚申講の際にも死者供養、先祖供養の要素が混じっていった。三尸を封じるために祀られた青面金剛の強力な力は、先祖の冥福や、死者が浄土へ旅立つ道のりを守ってもらうためのものに変化していった。庚申信仰は延命長寿に代表される現世利益のためのものであるが、葬儀仏教化しつつあった仏教色が混合することで、死者供養や先祖供養、つまり葬儀との関係が深くなっていったのである。
庚申信仰は更に神道と習合し猿田彦大神も登場
江戸時代に庚申信仰と仏教の混合が進む一方、神道の側からも猿田彦大神が登場する。三猿と同様、猿田彦の「猿」が庚申の「申」にかけられたようである。猿田彦は天孫降臨の際に天孫・邇邇芸命(ニニギノミコト)の道案内をしたことでしられる。降臨の際の露払いをしたことから、そこから災禍を払う力があるとされた。街道の案内板の役割を担った、いわゆる道祖神と同一視されている。猿田彦を祀る猿田彦神社(福岡県福岡市)では、毎年その年最初の庚申の日に、初庚申大祭が行われる。元々、庚申信仰に猿田彦神道を参入させたのは、儒教を混合した垂加神道の創始者、山崎闇斎だと言われている。この時点で庚申信仰には儒教の要素も混合されていることになる。なお仏教と違い、猿田彦と庚申信仰の混合には死者供養の要素は見あたらない。死を穢れとする神道らしい混合の仕方といえる。
庚申塚に刻まれた多種多様な人々の切なる願いと祈り
庚申塚、庚申塔の碑には由来が刻まれているが、その内容は延命を願うもの、死者の冥福を祈るものなど様々である。中には風雪に晒されほぼ読めないものも多い。足を止めて読む人もいないだろうしその必要もないが、そこには道教、仏教、神道、儒教など東洋の精神文化が複雑に融合した、神仏習合の形を見ることができる。そしての融合には、人々の切なる祈りが込められているのである。