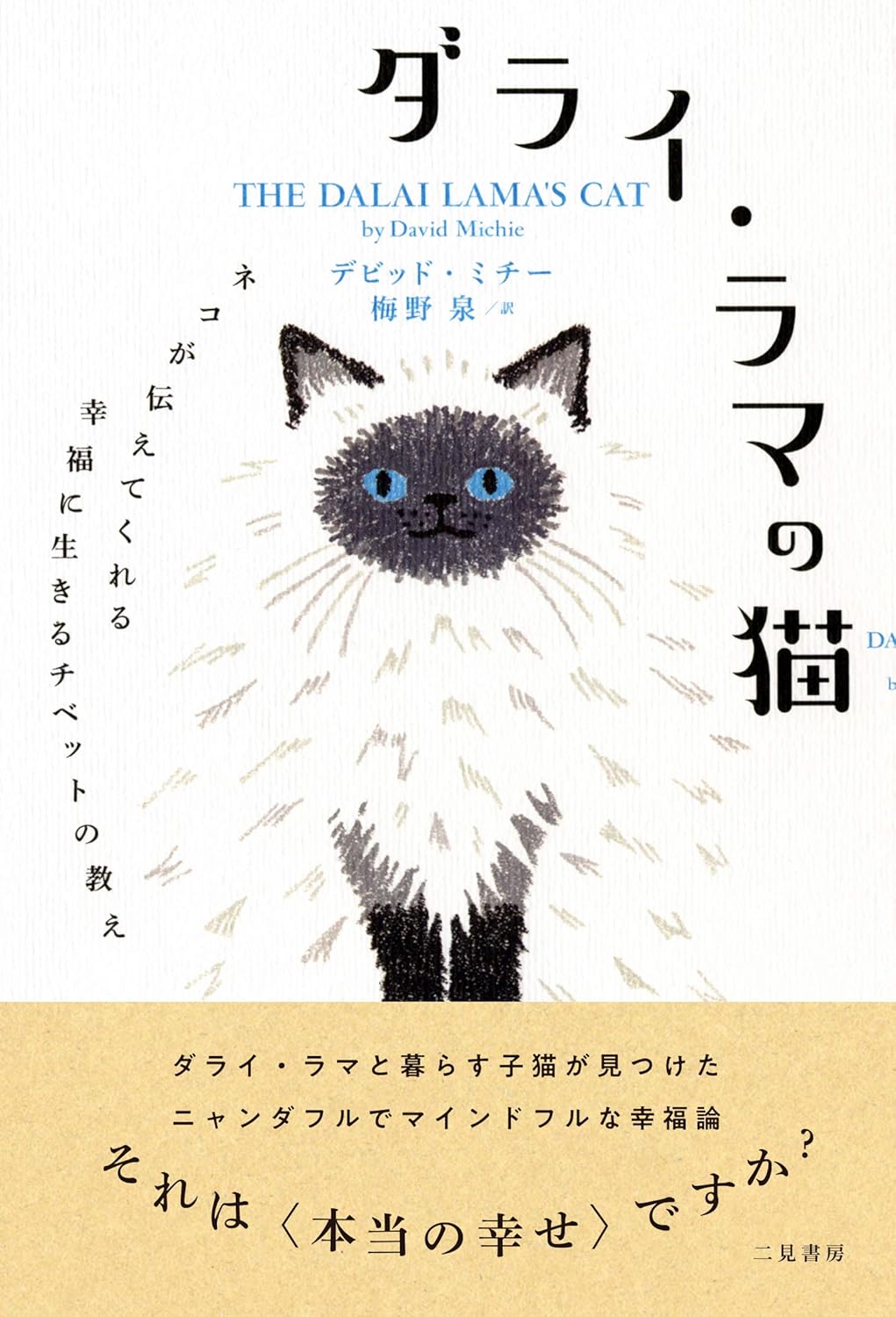輪廻転生を重ね、代々チベット仏教の法王の座を受け継ぐダライ・ラマ。その当代、ダライ・ラマ14世が重要な見解を示した。転生制度の継続である。彼は再びこの世に転生することを宣言した。チベット仏教の転生者「活仏」の存在と輪廻転生の意味を考える。

ダライ・ラマ14世、後継者と転生制度継続を宣言
90歳を迎えたチベット仏教最高指導者、ダライ・ラマ14世法王が後継者について言及した。法王は今生での役目が終わった後、転生して次のダライ・ラマとして生まれ変わることを宣言した。ただし、転生先は現在チベットを支配する中国以外の場所に限るとも明かした。法王はこれまで後継者問題について今生を最後に転生はしないと述べたこともあるが、最終的に転生制度の継続を選んだことになる。これに対して法王並びにチベット亡命政府を分離・独立派と見做し敵視する中国政府は反発。中国側が後述するパンチェン・ラマ11世の時のように新たな「ダライ・ラマ15世」を選出するのは明白である。しかし転生する当代が中国では転生しないと言っている以上、そのような存在は教義上まったく意味がない。14世法王の明確な「転生継続」は今後のチベット問題に大きな影響を及ぼすとみられる。
チベット仏教の最高権威 ダライ・ラマの系譜
チベット仏教の頂点に位置する最高権威が「ダライ・ラマ」である。正確にはチベット仏教には大きく4つの宗派、ゲルク派、ニンマ派、カーギュ派、サーンキャ派がある。この中の最大派閥がゲルク派でダライ・ラマはこの派の長であり、15世紀のダライ・ラマ1世から現代まで転生を続けているとされる。当代の14世法王、テンジン・ギャツォ師は、1933年に逝去したダライ・ラマ13世の転生者とされる。13世の逝去後、転生者の探索隊は4歳の男児を発見した。この男児は13世の遺品を当てるなど様々な証明をして転生者と認定され、ダライ・ラマ14世として即位した。しかし中国のチベット侵攻により脱出を余儀なくされ、ヒマラヤを越えてインドに亡命。その後はインドのチベット亡命政府を拠点に世界を回り、チベットの人権抑圧を訴えるなどすると共に、世界に仏法を説いている。また最先端の科学者たちとの対話を通じて宗教と科学の橋渡しを行っていた。こうした功績が認められ1989年ノーベル平和賞を受賞した。
ダライ・ラマだけではない チベットに数千人存在する「活仏」
輪廻転生するのはダライ・ラマだけではない。この世に降臨する転生者をチベットでは「活仏」(かつぶつ)と呼ぶ。活仏は現在数千人いるという。活仏の1人、リン・リンポチェ7世は、14世法王の個人教師だった、先代リン・リンポチェ6世の生まれ変わりとして、現代チベット仏教界で最高位の活仏の1人である。そうした活仏の中でもダライ・ラマと並ぶ権威とされるのがパンチェン・ラマである。ダライ・ラマに次ぐナンバー2の位置にあり、「ダライ・ラマは太陽、パンチェン・ラマは月」と称されている。そのパンチェン・ラマ10世は亡命したダライ・ラマ14世に替わり、チベットと中国の橋渡しとして活動したが、中国批判やダライ・ラマの称賛を行った数日後に逝去。その後、後継者探しが始まり、当時6歳の少年が発見された。14世法王は彼をパンチェン・ラマ11世として認定したものの、中国政府に捕らえられ消息不明となっている。現在表に出ているパンチェン・ラマ11世は中国政府が選んだ人物である。なお転生者が現れ宗教的な権威となる、転生・活仏制度は、ダライ・ラマ率いる最大派閥のゲルク派ではなくカギュ派から始まった。
活仏と凡夫の違い 自らの意思で転生する「救世主」
このように現代社会においてもチベット文化圏では輪廻転生による転生・活仏制度が一国家の中心に位置する。だが転生するのは活仏だけではない。仏教ではこの世に生きるすべての生命が転生すると説く。この世は、この世への執着に捉えられている凡夫たちの生きる苦しみの世界である。悟りを開き執着を捨て、輪廻の輪から解脱しない限り、我々は永遠に生まれ変わりを繰り返す。嫌でも我々自身が転生者なのだ。
活仏と我々が違うのは、活仏は自分の意思で生まれ変わりを選んでこの世を救うために降臨することである。つまり解脱できる技量を持ちながらあえて衆生と同じ輪廻の輪に留まっているのである。特にダライ・ラマは観音菩薩の生まれ変わりとされている。15世紀のダライ・ラマ1世より遥か昔に遡ると観音菩薩に辿り着くという。観音菩薩はいつでも悟りを開けるにも関わらず、あえて衆生を救うため地上に降りることを選んだ慈悲の仏と説かれている。なおパンチェン・ラマは阿弥陀如来の化身とのこと。如来より菩薩の方が格上だが、活仏たちはなぜ転生するのかと考えた場合、最高位のダライ・ラマが観音菩薩の化身とされるのは頷ける。そして菩薩を如来が守護するのは当然ということになる。
ダライ・ラマ法王は強国の力による支配から免れヒマラヤを越えた。だからこそ世界を股にかける活躍ができたともいえる。平穏なチベットの宮殿に居たなら、そのような展開はなかったのではないか。結果から見れば、この受難の時代に「あえて」転生したと言えなくもない。観音菩薩の化身の名に恥じない存在ではある。
輪廻転生の科学的検証 イアン・スティーヴンソンの研究
ではそもそもな話、輪廻転生は実在するのだろうか。転生に対する科学的な研究も行われている。有名なところではバージニア大学のイアン・スティーヴンソンの研究だろう。こういった話題では必ず出てくるので関心のある方は調べられたい。だが「科学的」研究では、端的に「生まれ変わり」という現象の実在・非実在に留まる。神仏の存在や、前世の「業」が現世に影響するといった宗教、倫理的意味合いはない。つまり物理的な「生まれ変わり」の証明であって、宗教的な「輪廻転生」の証明とはならない。それでも「生まれ変わり」が証明されるなら、人が死後も存続できる可能性が示唆される重要な研究ではある。だが世の中には2度と生まれ変わりたくない人もいるだろう。仏教は生は苦であると説く。「生まれ変わり」が実在するなら、人は永遠に苦しまなければならない存在であるともいえるのだ。その意味では「輪廻」の証明にはなるかもしれない。だが「生まれ変わりの苦しみ」から逃れる術はない。そこで仏教では「解脱」が説かれ、神智学・人智学といった神秘思想では生まれ変わりを魂の進化と捉える。仏教や神秘思想の転生論最大の疑問は「そもそも生まれ変わりなんて存在するのか」である。科学的研究が証明に成功できれば、これら宗教・思想の教えを保証してくれるといってよいだろう。ダライ・ラマ法王は科学者との対話を重ねていた。宗教と科学の対話と研究は、彼の今生での使命のひとつといえるかもしれない。
活仏たちが世界に伝えるメッセージ 生死を超えた救い
宗教は生死を超えた世界観を提供する。無神論国家・中国はダライ・ラマの動向に非常に敏感だ。転生者、その頂点たるダライ・ラマの政治・軍事の力を超える世界観を恐れているのである。
ダライ・ラマは、死後も魂は生きていると断言している。そして自ら転生することでそれを証明してきた。法王、そして活仏たちの転生の意味は、人間の人生は一度きりではないこと。さらに困難状況にあっても、生死を超えた救いの世界があるというメッセージでもある。現代のチベットを学ぶことは単なる政治・社会の問題だけではなく、それらを超える大きな世界に触れる機会でもあるといえるだろう。
参考資料
■BBC NEWS JAPAN「ダライ・ラマ14世、自らの死後に後継者が選ばれると発表 『転生』制度を継続」2025年7月3日配信
■チベット仏教普及協会 ポタラ・カレッジ