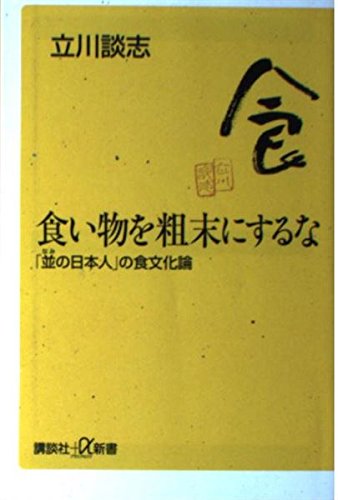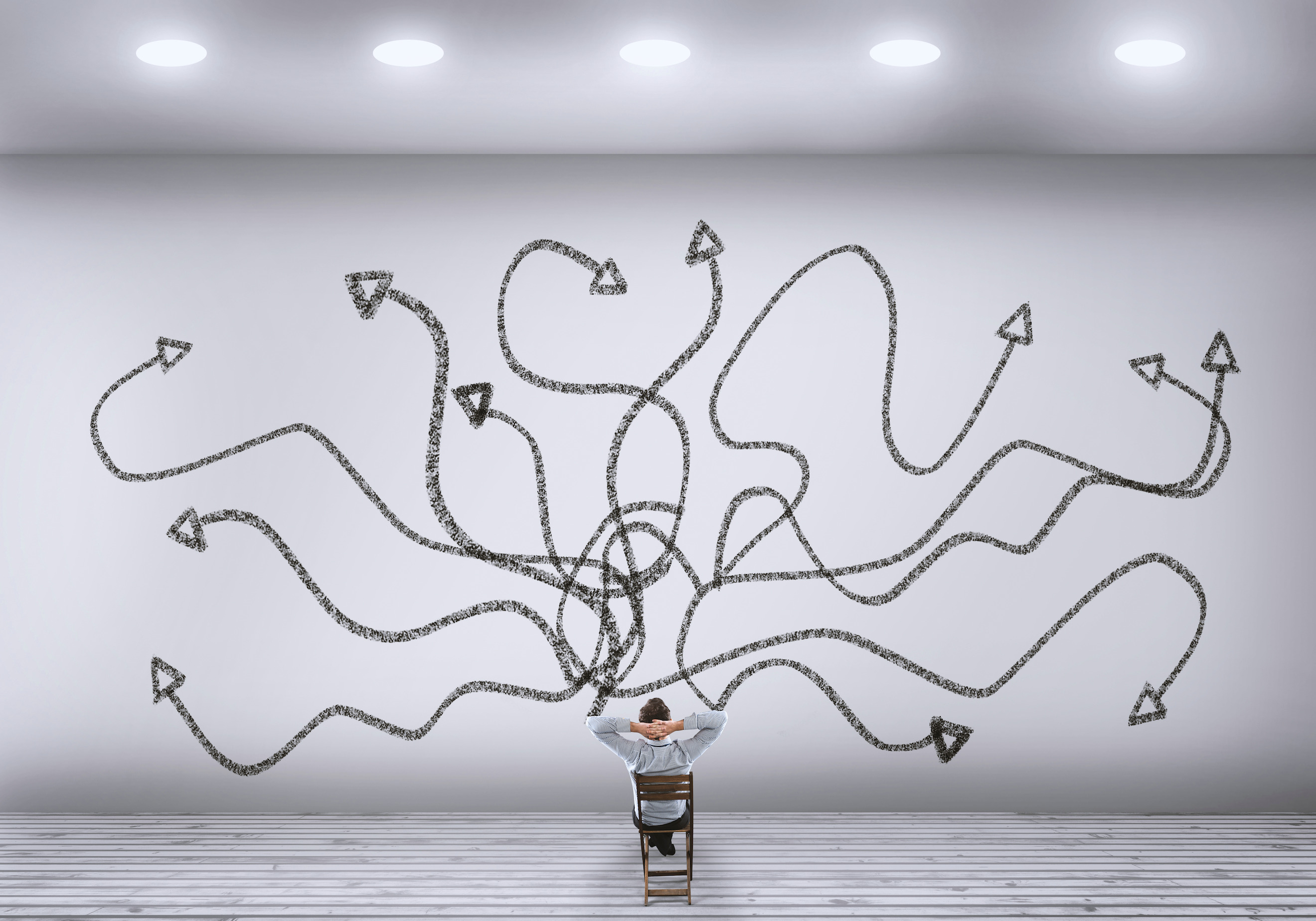目に見えるものがすべてだろうか。私たちはただのモノに線香や花を手向け手を合わせるのだろうか。目には見えなくても大きな存在がある、大切な人がそこにいると考えることは無意味なのだろうか。2つのネット記事に科学時代の「常識」と「非常識」を考える。

食べ物を投げつける人
「食べ物粗末にする系YouTuber」なるものがあるらしく、彼らの動画に批判が殺到している。動画では食べ物を壁に投げつけたり足で踏み潰したりと、どのような育てられ方をしたものか。親の顔を見たいとすら思わない内容である。彼らの言い分は“対価を払った自分の所有物”をどうしようと勝手という理屈だ。ひとつのパンが作られ自分の手に届くのは、自然の恵みや多くの人たちの働きがあってこそだとする、参照記事の指摘に同意である。食べ物を投げつけられるのは、そのような恵みとつながりを想像できず、金銭と交換した目の前にある「モノ」としか考えられないからだ。確かに商品とは消費者が対価を払い所有するために作られる。そこに至るまでの過程など考える実用的な意味はない。しかし意味がないものに意味を見出すのが人間性ではないか。
墓を蹴れる人
他方、ひろゆき氏がインタビューでこのように述べていてこちらも話題となった(註2)。ひろゆき氏は「あなたは「墓石」を蹴ることができますか?」との問いを投げかける。彼によると墓石はただの石の塊。墓石を蹴ってはいけない理由は見つからないとし、さすがに自分の家族の墓石は蹴ることはできないかもとしながらも隣の墓石なら蹴れると述べている。墓石を蹴る行為自体は犯罪なのだが法律の問題ではない。常識に囚われるなという意味の例え話である可能性が強いようだが、例えにしても墓を蹴るなどという言葉を口にする地点で確かに御本人は常識を超えている。彼が件のユーチューバーを知っているのかは不明だが、常識を覆すやり方として称賛するのだろうか。
サンタクロースっているんでしょうか?
毎年クリスマスになると各方面で紹介される逸話がある。1897年アメリカの新聞「ニューヨーク・サン」に8歳の女の子の質問に答える形で掲載された社説である。その質問とは「サンタクロースって、ほんとうに、いるんでしょうか?」。この切実な問いへの記者の答えを要約する。
「サンタクロースは愛することや人への思いやりがあるのと同じくらい確実にいます。サンタクロースを見た人はいません。しかし、それはサンタクロースがいないということにはなりません。この世でもっとも確かなものは目に見えるものではないのです。目に見えないもの、見ることができないものがこの世にはあることを想像することができないだけなのです。信じる気持ちや想像力がカーテンの向こうにある美しく、輝かしいものを見せてくれる のです。そのようなものが人間のつくったでたらめといえるでしょうか。それほど確かな、変わらないものは他にないのです。サンタクロースはいます。1000年後までも、100万年後までも、サンタクロースは子どもたちの心を喜ばせてくれるでしょう」
目に見えないもの、心の大切さを語りかける誠意ある返答である。これを「子供の夢を壊さないための美しい嘘」などと上から目線で解釈しては的外れになる。この社説は目に見えるものしか見ようとしない大人へのメッセージでもある。
西行の「かたじけなさ」
漂白の歌人・西行が伊勢神宮に参拝した際に詠んだとされる有名な歌
「なにごとの おはしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる」
どのような御方がいらっしゃるのかは存じませんが、ただただ、恐れ多く、ありがたい気持ちで一杯になり、涙があふれてしまいます。
真言宗の僧侶でもある西行が神道の総本山・伊勢神宮で感じ入った思いが込められている。目に見えぬ何かがいる。その何かの前で西行は「かたじけなさ」で胸が一杯になった。「かたじけなさ」には、ありがたい、恐れ多いという意味がある。人間ごときにはわからないあまりに大きな存在を前に、西行は畏れと感謝の思いがあふれて落涙した。若い世代がよく使う「ヤバい」は意外と一面の本質を突いている。ただ凄いと客観的に感嘆・感動するのではない。脅威、恐れ・畏れを感じるほどの凄さの表現である。西行はあまりにも大きい何かの前に、無力でちっぽけな自分を自覚し畏れた。それと同時に人知の及ばない何かに私たちは生かされているのだと感謝の思いがあふれたのである。西行の感性には遠く及ばなくてもなんとなしに理解できる人は多いはずだ。しかしそれも少なくなっているのだろう。
食べ物や墓石は単なるモノだと断言する感性は人というより機械に近い。自分で稼いだ金で買ったモノを投げ捨てて何が悪い。人が死ねばただのモノであり、その残骸の入れ物に過ぎない墓を踏みじって(法的にはともかく)何が悪いのだということになる。人の心が脳内の電気反応に過ぎないとする科学的合理的な立場を取るなら、人間は機械であり確かに筋は通っている。
人間らしさという科学時代の「非常識」
現代に生きる我々は神仏や大切な人の霊といった目に見えないものには関心はなく、金銭物資という目に見えるものだけを追い求めてしまう。それこそが科学時代の「常識」である。しかしそれなら進化するAIの方がはるかに優秀だ。目に見えないもの、科学時代の「非常識」なものの存在を感じることこそ人間らしさではないだろうか。
参考資料
■中村妙子訳「サンタクロースっているんでしようか」偕成社(1977)