輪廻転生説には2つのタイプがある。人間と他の生物を同様に見るタイプと、人間のみを分けるタイプである。転生がもし本当にあるとしたら、人間は人間以外の生物にも生まれ変わるのか。人間は人間にしか生まれ変わらないのか。
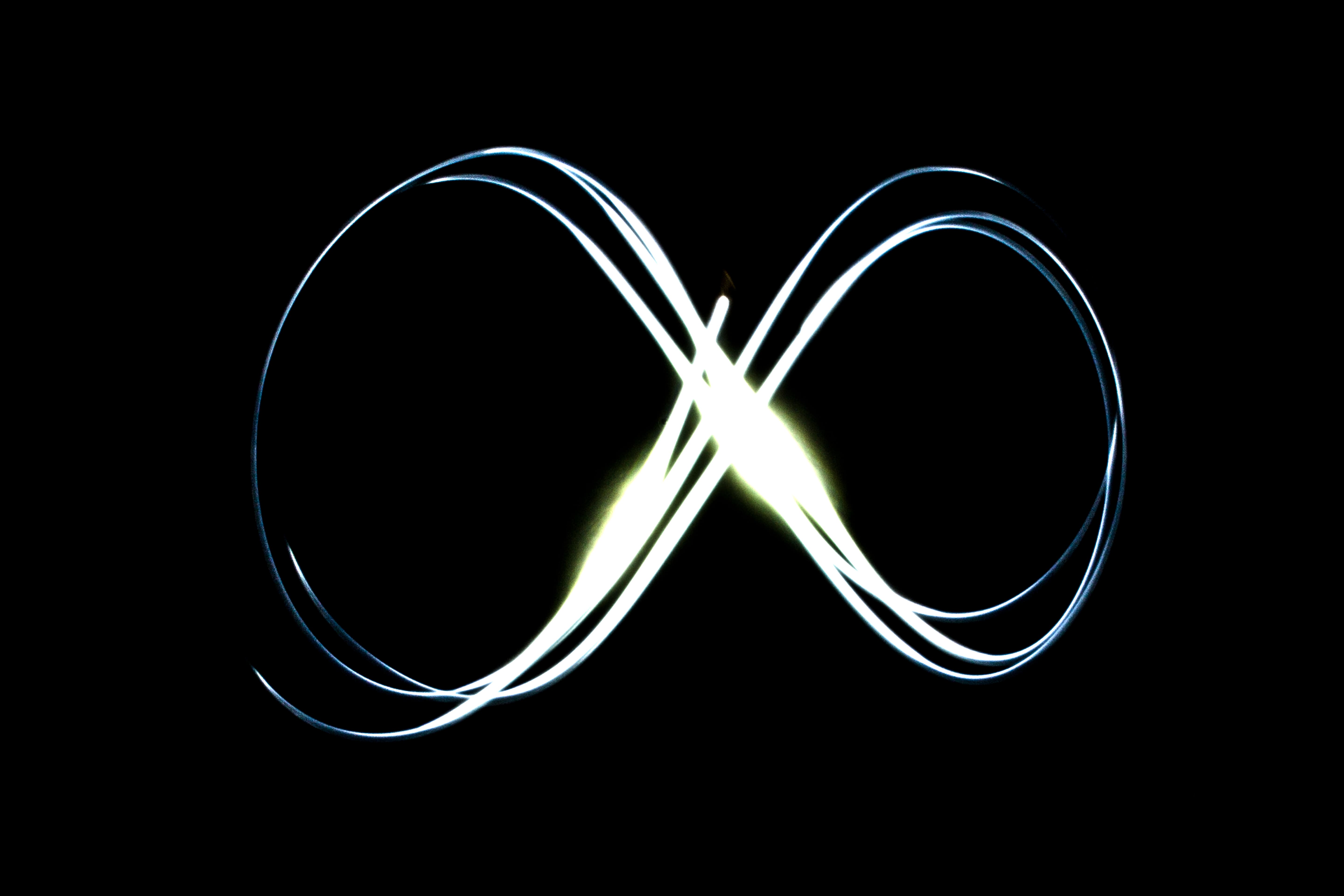
西洋の輪廻転生
人は死んだあと生まれ変わるという思想は世界的に普遍なものである。古代ギリシャではピタゴラスが転生説を説いた。後に転生を否定するキリスト教がヨーロッパを席巻した後も、転生を説くカタリ派が出現し、カトリック教会から異端とされ弾圧された。聖書には人間は「神の似姿」であり他の動物に勝る特別の存在だと説かれている。このキリスト教的世界観が人間中心主義となり、人間は他の生物を含む自然を支配・制御できる存在としての自覚を生む。これが皮肉にもキリスト教を停滞させた自然科学の発展につながった。
仏教の六道輪廻
東洋では古代インド哲学からヒンドゥー教の流れにおいて、輪廻転生は重要な教えだった。人間は死後、生前に積んだ「業」により、人間以外の動物に生まれ変わることもある。ヒンドゥー教を批判する形で出現した仏教でも輪廻説が取り入れられた。仏教では無我を説くので、一体何が生まれ変わるのかという疑問が現代でも議論されてはいるが、一般的には輪廻転生は仏教用語として認識されているといってよい。現代では自然保護、動物愛護の意識が育ち、人間優位のキリスト教的価値観への反省から、人間も動物も、生きとし生けるものすべての命は平等であるとする仏教的な思想が注目されている。
しかし、その一方で仏教は、天・人・修羅・餓鬼・畜生・地獄の6つの世界を円環する「六道輪廻」があるとし、このうち「餓鬼」「畜生」「地獄」を「三悪道」と呼んでいる。このうち動物に生まれ変わる世界は「畜生道」である。動物は本能に支配されている。生きる目的は種の保存のみ。命を繋ぐと言えば美しい表現だが、弱肉強食の厳しい環境は人間には凄惨にさえ見えることがある。「火の鳥 鳳凰編」で我王という罪人が「生まれ変わっても人間でいたい!」と叫ぶ場面がある。これこそ我々の本音ではないか。
仏教では人間に生まれ、仏法に出会える可能性は非常に低いとされる。「雑阿含経」では釈迦がこのような例え話をしている。「大海の底に一匹の亀がいる。その亀は百年に一度、息を吸いに波の上に浮かび上がってくる。その大海に一本の浮木が流れていて、その木の真ん中に穴が一つ空いている。 亀がちょうどこの浮木の穴から頭を出す」。釈迦によると人間に生まれる確率はこの例えよりもさらに低いという。
仏教では「悟り」を得ることで解脱し、輪廻から解放されることを目指す。輪廻は苦しみの連鎖であり解脱して脱出しない限り苦しみは続いていく。その中でも動物に転生することは、再び人間に転生することよりもさらに苦しいものだと見ていたのである。
ルドルフ・シュタイナーの転生説
インド思想では輪廻転生は終わりのない循環的なものであった。これに対して、近代西洋神秘主義の嚆矢となった「神智学」や、そして神智学から独立したルドルフ・シュタイナー(1861〜1925)の「人智学」などの思想は全く異なる。人間の動物への生まれ変わりを否定し、より高いレベルへの魂の進化論を説いている。ここではシュタイナーの転生説を概観する。
シュタイナーの思想で重要なものに「自我」(ich/イッヒ)がある。「自我」は輪廻転生を重ねる「本体」でもある。古巣の神智学から思想を受け継いだシュタイナーは物体を鉱物・植物・動物・人間に分け、それらの構成要素として肉体(物体)、エーテル体、アストラル体、自我体の4層を説く。鉱物は物体のみ。植物には生命そのもののエーテル体。動物には感情を司るアストラル体までが存在し、理性・知性を有する自我体を持つのは人間のみである。つまり、鉱物=物質、植物=物質+生命、動物=物質+生命+感情、人間=物質+生命+感情+自我ということになる。この階層論はそれなりに納得できる。確かに人間と動物、動物と植物、植物と鉱物の間には違いがあるのは明白だ。つまり人間と動物の魂は別のものということになる。別のものなのだから、人間が動物に生まれ変わることはなくその逆もない。自我まで到達している人間はアストラル体までしか有していない動物より進化している。輪廻転生が進化の過程なら当然動物への転生はあり得ないことになる。
人間は死後、自我、アストラル体、エーテル体と分離していき、最後に抜け殻となった物質である肉体が滅ぶという。では動物は死後どうなるのか。シュタイナーは、動物の魂は人間のような個的なものではなく、集団としての魂であるとした。これを集合魂(群魂)という。個々の動物の魂は例えば犬は犬の猫は猫の集合魂に帰っていく。人間の魂が動物と異なるのは一人一人が個性化していることである。そして人間の魂は前世の課題を消化し、次のステージへ向かう。
シュタイナーの転生説は人間に都合のいい考えだと思われる向きもあるだろう。だがそもそも輪廻転生や魂・霊的な存在自体、自然科学的な事実は何も無い。エーテル体以上は物質体を超えた構成要素である。輪廻転生なる物質を超えた世界が存在し、転生する主体があること前提にするなら、エーテル体、アストラル体の欠如などの差が、そのまま反映されるとしても矛盾はない。
人間中心主義?
一見すると人間も動物も同じ生命という考え方は平等であるようにも見えるが、それは物体・物質だけを見た唯物論的な視点でもある。確かに霊や魂といった不可視の存在を無視すれば、人間も動物も同じ生物に過ぎない。現代における平等な命とは、目に見える動いている姿のみを指して言っているのだ。輪廻転生という宗教的概観を語る時には視点が足りない。
だが、その上で神智学・人智学が人間は人間にしか生まれ変わらないとするのは、やはり傲慢ではないのか。結局キリスト教的人間優位主義に戻っただけでないのか。ここはフラットに考えてみたい。確かに動物には好・悪、快・不快などの感情はあっても、自我、知性、理性といった要素はどう見てもなさそうである。魂も持たない機械として扱うことには抵抗があるにしても、一方で家畜を食物として摂取することも厭わないのは心底平等とは思っていないからできるのではないか。その点、シュタイナーは動物にも人間とは異なる形だが魂はあるとしている。唯物論的な生命平等主義ではない。
独特の存在
良くも悪くも人間は自然から逸脱している。神の計画か自然のバグか、特別とは言わなくても、独特の存在であることは間違いない。物質を超えた世界が存在する場合、人間と動物の間に何らかの差異があってもご都合主義とばかりはいえないのではないか。そしてシュタイナー説に従う限り、我々は死を恐れることはない。
シュタイナー(神智学)の転生説は歴史の必然かもしれない。輪廻転生という古代の死生観。仏教の生命平等と、キリスト教による人間と動物の分離。自然科学(唯物論)が発見した進化論。歴史の中で生まれた死生観・生命論のそれぞれの欠点を克服し統合した思想といえるだろう。もちろん大前提である物質を超えた不可視の存在・現象を認めるかどうかは各々の判断である。
参考資料
■ルドルフ・シュタイナー著/高橋巖訳「神秘学概論」ちくま学芸文庫(2007)
■ルドルフ・シュタイナー著/高橋巖訳「シュタイナーのカルマ論」春秋社(1996)
■ルドルフ・シュタイナー著/西川隆範訳「神智学の門前にて」イザラ書房(1991)











































