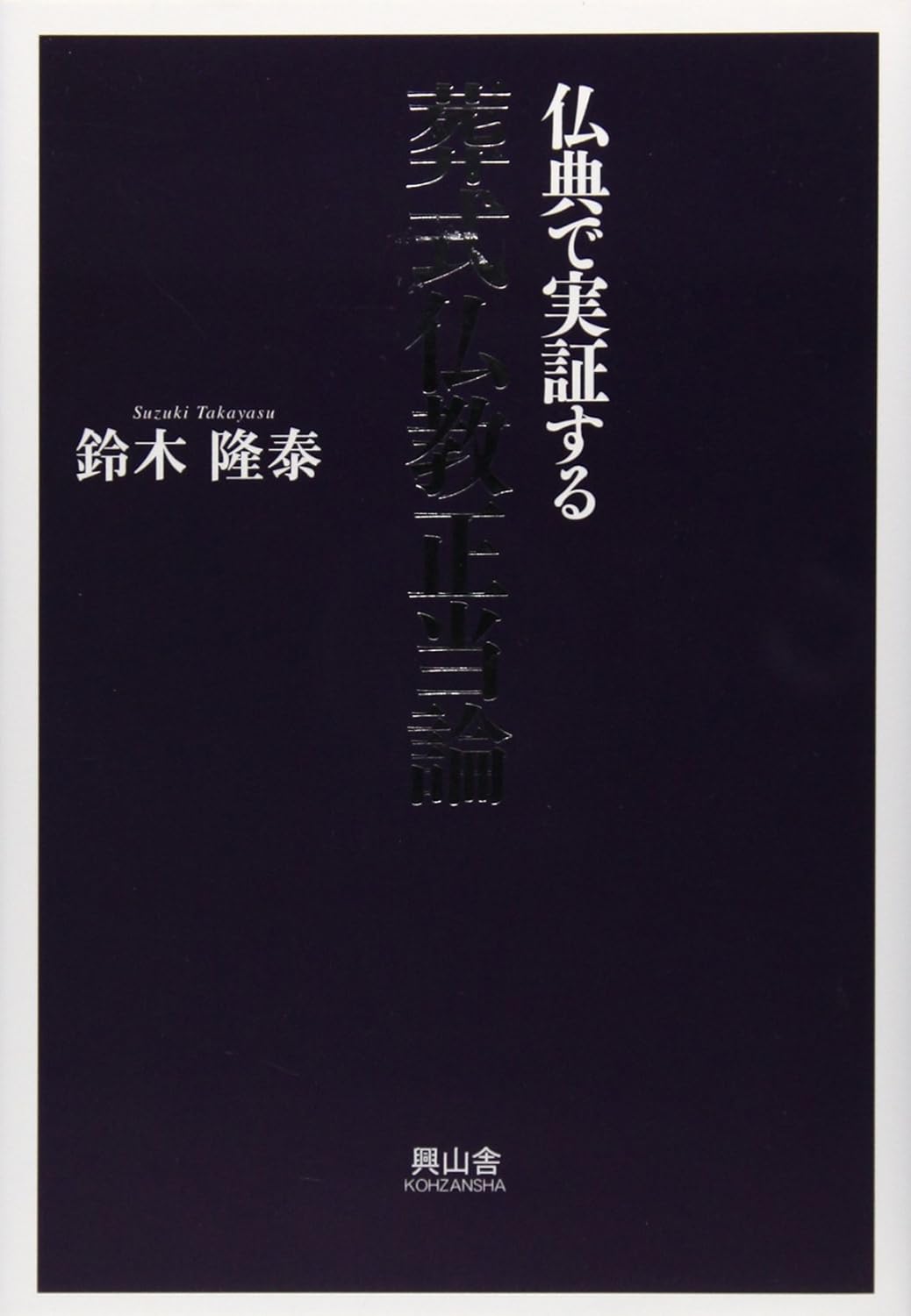僧侶不要論が強まっているように思われる。生臭坊主、坊主丸儲けと僧侶に対する揶揄は昔からあったが、今日ほどその権威が揺らいでいる時代もない。葬儀が簡素化される中で僧侶の役割はなくなってしまうのか。葬式と僧侶についてを考える。

ニセ僧侶の出没
「ニセ僧侶」が出没しているという。上野東照宮で僧衣を着たアジア系外国人が、修理のためだと外国人観光客の方からお金を騙し取る事件があった。一万円騙し取りステッカーと数珠を渡したという。公式ホームページによると、警察に届け出ており、現在は境内に偽僧侶は現れていないとのこと。しかしネットで検索すると「ニセ僧侶」は日本の各地に出現して外国人観光客に二束三文のグッズを売りさばいていることがわかった。悪質な詐欺行為であり、警察には迅速な対応を求めたいものだ。ところがその一方で、ネットでは「何をもってニセというのか。そもそも僧侶自体詐欺みたいなものだ」との意見も多く見られた。そうした意見の背景には僧侶に対する不満、批判がある。
僧侶不要論の背景
これらの意見の背景には僧侶に対する不満、批判がある。墓じまい、葬式離れの昨今、いわゆる「葬式仏教」に対する冷ややかな目は強くなるばかりである。「ニセ」と言うからには本物の僧侶がいることになるが、本物とニセ者の違いは何か。僧侶になるには真言宗なり浄土宗なりの各宗派の養成学校で学び、一定期間の本山で研修を終了して一応は僧籍に入ることになる。件のニセ僧侶は僧籍もなく仏教の素養すらない文字通りの「ニセ僧侶」だが、宗派から認定された正規の僧侶による犯罪行為や不道徳な振る舞いは珍しくない。僧籍こそあっても彼らもまた宗教者にあるまじき「ニセ僧侶」であると言える。僧籍にあり、人徳もある僧侶なら本物といえるかもしれないが、尊敬に値する僧侶が何人いるだろうか。また、よく生臭坊主としてよく指摘される肉食妻帯については日本仏教独自の展開だと考えるが、多くの僧侶がそれに甘えて世俗にどっぷり浸かるようになってしまったのは確かである。
神職より厳しい僧侶への目
これらに比べると筆者の主観ではあるが、神社・神職に対しては比較的寛容な気もする。もちろん商売としてのお守りや御朱印などへの批判もあるにはあるが、僧侶よりはかなり穏やかな印象を受ける。神社が機能するのはお宮参り、七五三、結婚式などのお祝い事が多く「陽」の印象があるからではないだろうか。一方、寺院・僧侶の出番はなんといっても葬式である。人の死という「陰」に関わる印象だ。神式の葬儀もあれば、仏式の結婚式もある。厄除けなどのご利益を売りにしている寺も多い。密教や禅の人気も相変わらずである。それでも一般的には神社が「陽」寺院が「陰」の認識で間違いはないと言っていい。お祝い事に対しては多少の出費も仕方なしという気分になるが、葬式はただでさえ心身共に疲労しているところに高額な戒名、香典と、こちらが落ち込んでいる時、ここぞとばかりに財布を狙ってくるように思わせてしまう。神職に関連する不祥事が報じられることもあるが、堕落の象徴のように指摘されるのは僧侶の方だ。葬式における僧侶の必要性が薄まっている今日ではなおさらである。葬式仏教に対して厳しい目を向けていた、宗教評論家ひろさちや氏(1936〜2022)の著書『栄西を生きる 佼成出版社 (2022)』は、葬式の専門家であればちゃんと死体の始末からやれ。自分では何もせず、死体の処理は葬儀社にまかせて、ただお経を読むだけで専門家といえるのかと手厳しく批判している。これはさすがに酷であるし葬儀社の仕事を奪うわけにもいかないだろうが、後述するように「死穢」に寄り添うことが葬式仏教の始まりなら本質を突いている。
悩みに寄り添う
ここまで良いところがない現代の葬式僧侶だが、基本的に僧侶が行い神職がやらない仕事がある。人生相談である。僧侶は人生の悩みに寄り添うカウンセラーとしての面がある。悩み相談の電話や相談ブースを設けている寺院は少なくない。僧侶が運営する「坊主バー」なども存在する。祭りでもないのに宗教者が酒場を運営するのはやり過ぎな気もするが、酒の席でしか話せないこともある。これに対し神社はお宮参りや結婚式に加え、地鎮祭や各種祈願など、個人より全体的な祈祷などを行う傾向が強い。交通安全や合格祈願もその人独自の事情というより、誰しもが望む一般的な願望である。個人が個の悩みを神職に直接相談する場面はあまり見られないと思われる。個人的な悩みを打ち明けられるという意味では神社・神職より寺院・僧侶の方がより近い存在といえる。僧侶は悩めるひとりひとりに「寄り添う」存在であるべきだろう。本来、葬式仏教とは苦しむ民に寄り添うことにあった。病者や遺体は穢れた存在だった。穢れを嫌う神職、国家公認の僧侶らが忌避する中で、彼らに寄り添う僧たちが鎌倉時代に出現した。この史実は何度でも伝えなくてはならない。その先駆者が法然(1133〜1212)である。知恩院の「法然上人絵伝」には、四天王寺の境内で病者たちに粥を施す法然が描かれている。その顔は慈悲に溢れており、葬式仏教の理念は法然が描かれた一枚の絵に尽きると言えるだろう。四天王寺には薬局・病院に該当する施薬院、療病院。また、社会福祉施設・悲田院が設置されていたことで知られる。
僧侶がすべきこと それは寄り添うこと
出家者(ひろ氏言うところのホームレス)であることを止めた日本仏教の僧侶には、どうしても生活がつきまとう。葬式が貴重な収入源なのは理解できる。しかし、葬式の場で僧侶が打ちひしがれる遺族に寄り添う場面を見たことは個人的には無い。法事でも意味もわからない退屈な読経と決まった法話で終わることが多い。もちろん熱心な僧侶もいるが、葬式を生計を立てるための「仕事 」として事務的に行うだけでは「坊さんはいらない」の声は今後も増えていく。葬式仏教の原点である「寄り添う」ことを考えて頂きたい。