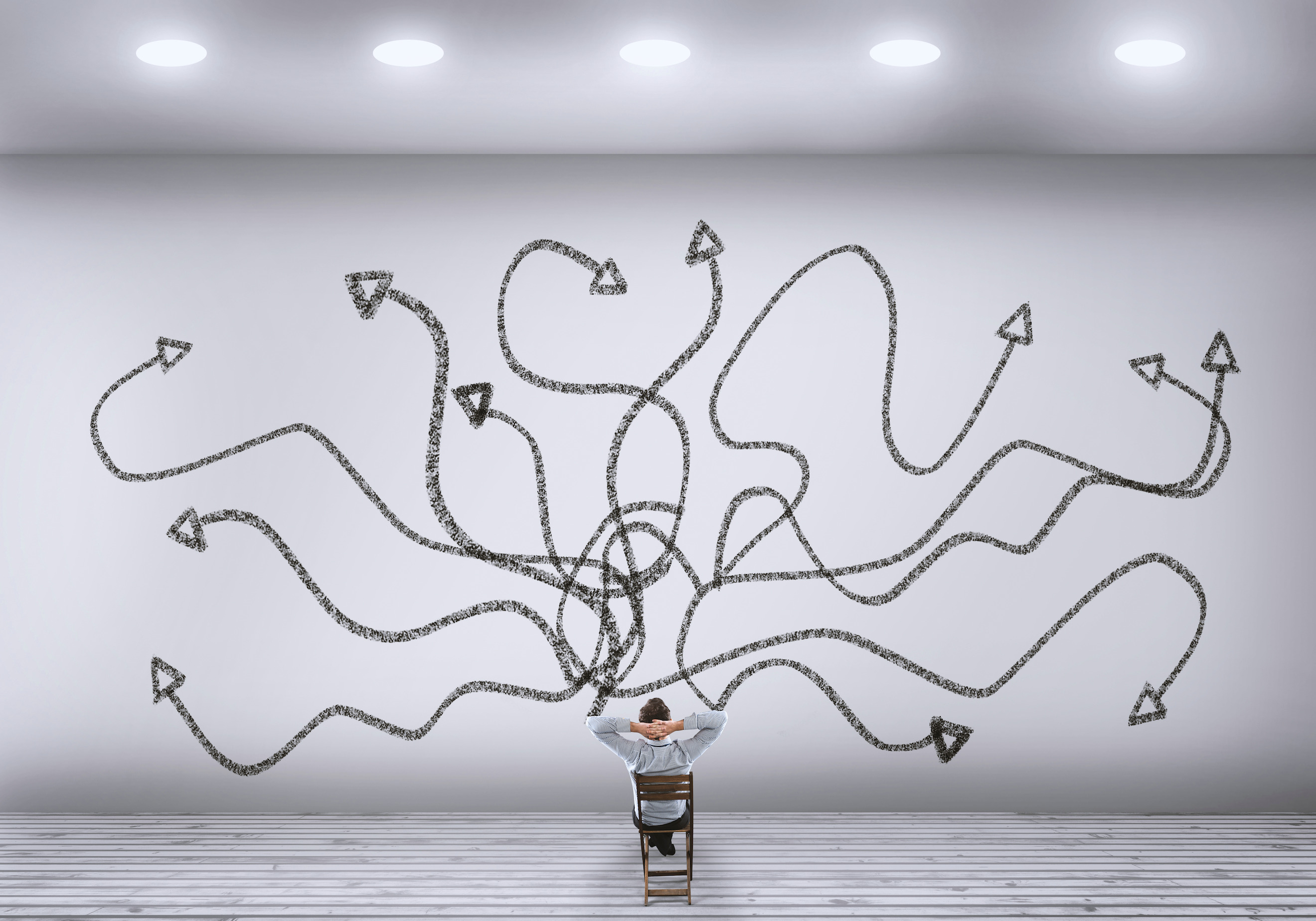カタカナ英語の「パーフェクト」の意味であり、欠点がなく、すぐれてよいこと。完全無欠を意味する「完璧」の「璧(へき)」とは、そもそも一体何なのだろうか。「璧」とは軟玉(ネフライト)やガラスでできた、平たい円形の「玉(ぎょく)」のことだが、厳密には、中央に孔(あな)があり、周辺の幅は孔の径の2倍ものを言う。穀物の粒のように見えるもの(穀粒紋)や、渦巻状の模様(渦巻紋)が表面に施されている。
璧の起源と日本への伝来時期
主に華南地域から発生し、黄河下流域の山東、中流域、上流域の西北地域まで広がっていった。日本には璧は弥生時代に伝来し、例えば福岡県の内陸部に位置する朝倉郡筑前町(ちくぜんまち)の峯(みね)遺跡から2個のガラス製の璧が出土している。特に戦国時代から前漢時代においては、璧には紋様に加え、龍などの神獣も彫られるようになっていった。それは璧が遺体の防腐、死者の魂を天界に導かせる、邪気を遠ざけるための道具だと見なされるようになっていったことを示しているという説もある。それを裏づけるように、当時の高位の者を埋葬したとされる墳墓から、遺体を守るように配置された、40個にも及ぶ大量の璧が発見されたこともあったという。
壁の意味とその名前の由来
古代中国においては、「辟邪(へきじゃ)」と呼ばれる、「邪」を退ける伝説の神獣の存在が信じられていた。「辟」という漢字には「除く」「退ける」という意味がある。当初は形が「正しくないもの」「斜めになっている」物事を表し、それから「よこしま」「悪い」ことへと意味が発展していった「邪」、すなわち、不吉・凶事・災難・流行病などを「退ける」「玉」ということで、中央に穴が儲けられた軟玉やガラスでできた細工物が「璧」と名づけられたのだろうか。
壁はお守りやお清めの効果をもたらすと考えられていた
科学技術の発展を大いに享受しているはずの我々が、現代もなお、「邪」を「退ける」ものとして、寺社で授与されたお守りを肌身離さず身につけたり、お葬式に参列した後にお清めの塩を体に振ったりすることと似たようなものだろう。いつの時代でも人間は、避けることがままならない場合も多々ある「邪」「禍事」を恐れ、完全に避けられないことがあるとわかっていても、それをできる限り避けたいと思っていることの証だろう。
最後に…
現代の日本においては、死後の遺体は火葬される。そしてその骨は骨壺に収められ、狭い墓石の下に埋納されることが当たり前になっている。そうした中、我々は、古代中国の高位の人々のように、広々とした空間の中で、遺体が焼かれることなく、大量の璧などの副葬品とともに埋葬されたいものだろうか。死んでしまったら、どんな宝物であっても、自分の手にすることは叶わないとわかっているから、そんなものはいらないと思うか。それとも、「完璧」の言葉通り、少しの欠けも歪みも傷もない璧と共に、永久に眠り続けたいと思うのか。
当時と今とでは、人が生きている時間は、比べものにならないぐらい長い状況だが、「死にたくない」「一日でも生きていたい」と思う気持ちそのものは、ほとんど変わらないはずだ。そうした中、自分の富や名誉、栄耀栄華の日々を文字通り、「手放さない」死に方を選びたくなるものだろうか。