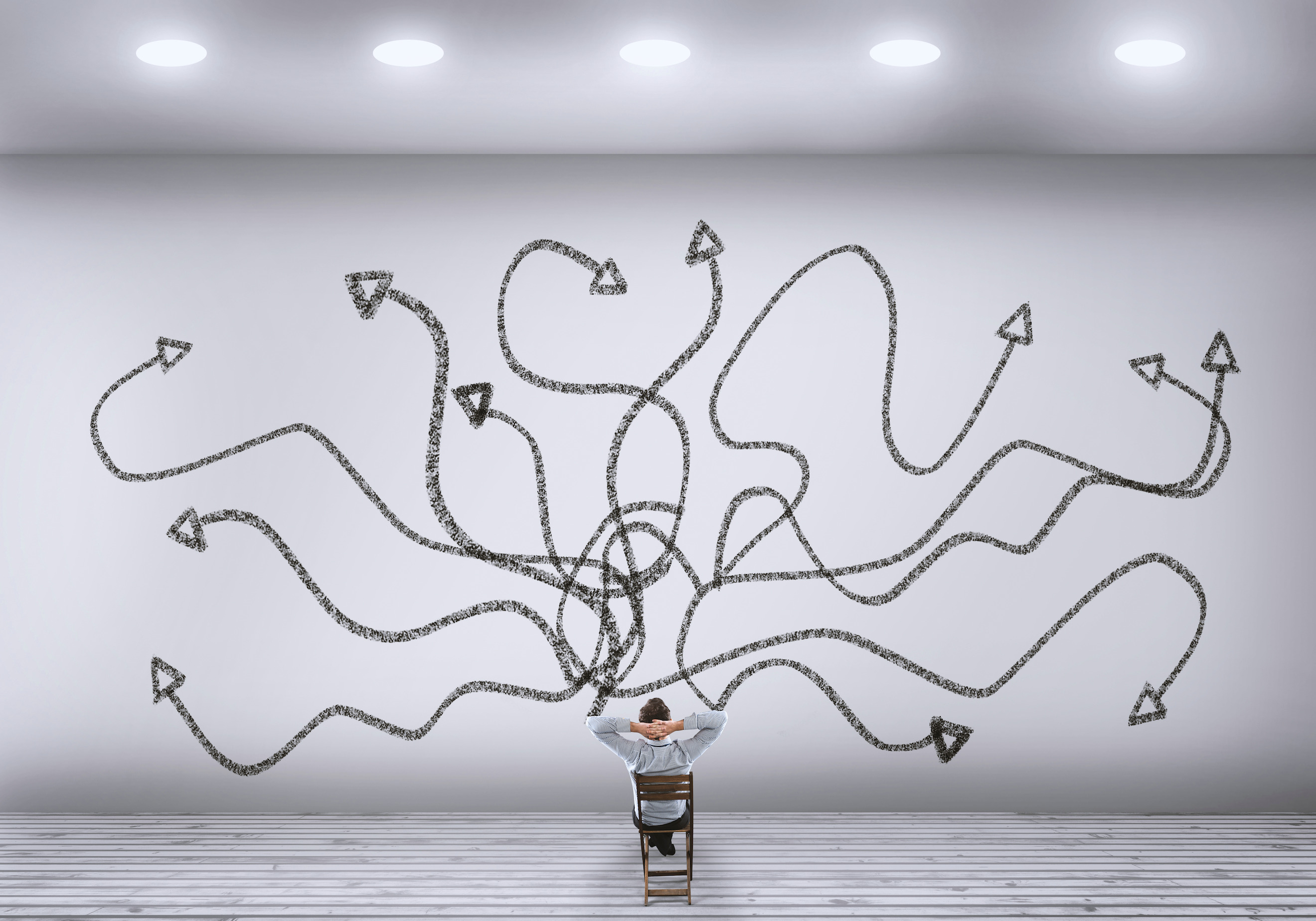「日本人は遺体や遺骨、特に遺骨にこだわる傾向がある」とよく言われる。しかしながら、その遺骨を納める骨壺のデザインの多くは、至ってシンプルで装飾性が少ない。
この理由は、そもそも火葬が庶民層で一般化したのが戦後という、比較的最近になってからであることと関係があるだろう。もっとも、最近はもっと個性的なデザインの骨壺が出てきてはいるが。
複数人の遺骨を納めていたためサイズが大きい!
ところで、沖縄では「日本」ではなく独立した琉球王国であった時代から、いわゆる洗骨・改葬の風習があった。そのため、本土でまだ故人の遺骨を骨壺に納める習俗が非一般的であった時代から、沖縄文化圏では故人の遺骨に触れ、骨壺に納める習俗が発達していたのである。
その時代からの伝統的な骨壺「厨子甕(ずしがめ、方音はジーシガーミと呼ぶ)」は独特である。まずサイズが大きいことが挙げられるが、これは一つには、火葬にしないことが前提とされるため遺骨が灰状にならず、原形を留めていることを想定しているからである。また、一族の複数人の遺骨が1個の骨壺に納められることが前提とされることも、大きなサイズの理由の一つである。
特徴あるデザイン!
また、見た目のデザインもインパクトがある。
まず多いタイプのデザインとしては、屋根に「シャチホコ」が載った、「絵本に描かれた竜宮城」のような形のものがある。このタイプの骨壺には、様々な色の釉薬が使われ、カラーバリエーションが多い。特に藍色が好まれているようである。
今もこのデザインの骨壺は、伝統的な「壺屋焼」で作られている。なお、沖縄以外の地域から来た観光客にも、「庭に飾るのに良い」として買われることがあるという。
他にも、壺型やもう少しシンプルな屋敷型など、様々な形の骨壺が伝統技法で作られている。皆、カラーバリエーションが多く、手が込んでいる。
近年は、本土と同様の骨壷が普及してきている
近年は、火葬の普及により本土同様の埋葬法が多くなってきている。そのため、原則として一人分の、灰状の遺骨を納めることを想定した本土でよく利用されている骨壺が普及してきている。
ただ、そうしたタイプの骨壺でも、現代の本土で一般的なシンプルタイプだけでなく、個性的なデザインの骨壺が多く作られている。例えば壺型骨壺の小さなサイズのものであったり、あるいはカラフルな琉球ガラスで作られた骨壺などがあるようだ。