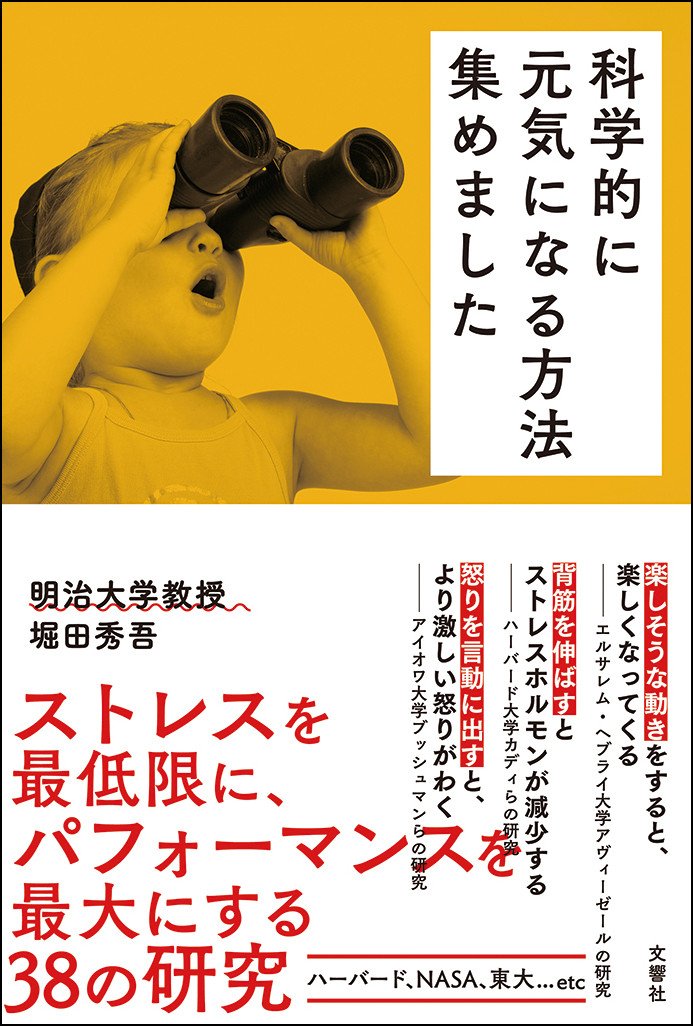愛する人との別れほど辛い事はない。そしてそれは逃れようがない、誰しも降りかかる悲しみである。なぜ人はそのような苦しみを持ってしまうのか。そこから救われる道はあるのだろうか。

四苦八苦の一つ「愛別離苦」:現代のグリーフに通じる根源的な悲しみ
「四苦八苦」という言葉は元々仏教の教えから来ている。人間が生きる上で避けられない根源的な苦しみを分類したもので、「四苦」とは生(しょう)・老・病・死を指す。釈迦は太子の頃、王城の東西南北の四つの門から郊外に出ると、それぞれの門の外で老人、病人、死者に出会った。釈迦はこれらの光景を目の当たりにし、人が生きることの苦しみを知った。そして4つ目の門で修行者(出家者)と出会い、出家を決意したという。名高い「四門出遊」の伝説である。この「四苦」に加えて、怨憎会苦(おんぞうえく/憎む者と会う苦しみ)、求不得苦(ぐふとっく/求めるものが得られない苦しみ)、五蘊盛苦(ごうんじょうく/心身を形成する五つの要素から生じる苦しみ)。そして、親、兄弟、夫婦など、大切に思っている人と、生き別れや死別によって別れなければならない苦しみ、愛別離苦。この四つを加え、「四苦八苦」となった。中でも愛別離苦は現代のグリーフ(悲嘆)に通じる概念である。
無常ゆえに避けられない別れ:自らの苦しみを上回る愛別離苦
愛別離苦に限らず四苦八苦すべての原因は「無常」にある。仏教では根本的な法として、諸行無常、諸法無我を説く。諸行無常とは万物は常に変化し、永続的なものはない。諸法無我は同じ理由で実体とされるものは存在しないという考え方である。つまり形あるものはいつか滅び、出会った者も、いつか別れが来る。病も死も人間の智慧や力では避けられない世の理なのである。その中でも愛別離苦は最も耐えがたい苦の有り様ではないだろうか。老い、病気、そして死は耐え難い苦しみである。だが、わが子や恋人、家族など大切な人との別れは、自らの苦しみを上回るものがある。例えば普通の親であれば、わが子の命と引き換えに、自らの命を差し出すことなど容易だろう。また、自らの死に直面してもそこに守るべき者がいるなら、むしろ死の恐怖そのものより、その者の今後を案じることで、悲嘆に陥るのではないだろうか。だが世が無常である限り、これを避けることはできない。
苦しみの原因は「執着」:愛を否定しない仏教と聖帝サウザーの問い
諸行は無常でありいつかは失ってしまうのに、私たちは様々なものに執着する。失いたくない、離したくないと思う。だから苦しい。それが愛情であれ、名誉、資産であれ、大きければ大きいほど失うことを恐れる。漢の高祖・劉邦は器の巨大な人物だった。しかし皇帝の座につき天下人となってからは猜疑心の塊となり、自分を支えてくれた功臣たちの多くを粛清した。劉邦の晩年は、手にした強大な権力をいつ、誰が奪いにくるのか怯える日々だった。金も権力も持っていなかったが、自由で友人たちに囲まれ日々笑い合った若き日の方が幸せだったのかもしれない。ここで漫画「北斗の拳」の聖帝サウザーの名ゼリフが浮かぶ。「愛ゆえに人は苦しむ。こんなに苦しいのなら、愛などいらぬ」。最初から持たなければ苦しまなくて済むではないか。仏教の出家は悟りを得るためにすべてを捨てることから始まる。
なお、釈迦は愛そのものは否定しない。釈迦が捨てるべきとしたのは執着としての愛であり、他者の幸せを願う慈悲の心は尊ばれる。とはいえ、それは理想であるし、慈悲の心を持ちながらもやはり悲しいことには違いない。王子だった釈迦自身は国や家族を捨てて出家した。すべてを捨てて修行をすれば、悟りを得て楽になる(解脱)のかもしれない。だがそれは選ばれた一部の聖人だけではないだろうか。
親鸞の応え:それでも悲しむ凡人を阿弥陀仏は決して見捨てない
釈迦が教えた愛別離苦の原因と救いの方法に高僧名僧はどう応えたか。本稿では親鸞について考えてみたい。親鸞は人間の八苦の中でも愛別離苦を「もつとも切なり」としている。釈迦のような聖人にはなれない凡人に対して、浄土仏教は阿弥陀仏が用意してくれた極楽浄土は大切な人との再会が約束されている場所であると説く。これにより死別は永遠の別れではなく、先に行った人とまた会える一時的な別れであるとした。だがその上で親鸞はさらに「それでもやはり」と続ける。
「ともに浄土の再会をうたがひなしと期すとも、をくれさきだつ一旦のかなしみ、まどへる凡夫として、なんぞこれなからむ」(口伝鈔)
大切な人とは死後も極楽浄土で再会することに間違いはない、と信じてはいるものの、一度はこの世とあの世に別れることに、凡人たる自分はやはり悲しまずにはいられないというのだ。
また「歎異抄」でも、極楽往生を信じたいが不安が消えないと悩む弟子・唯円の問いに自分も同じだと答えている。そしてそのような煩悩だらけの凡人だからこそ、阿弥陀仏は放って置かないのだという。このように親鸞は徹底して凡人の側に立った仏教者であった。
釈迦、イエス、ソクラテスら聖人たちは生死を超える真理を説いた。それでもその死に際し、いずれの弟子たちも深い悲嘆に陥った。彼らは一体、師から何を学んだのか。やはり悟りは困難なのだろう。だから親鸞は言う。人知を尽くしても愛別離苦を前に悲嘆を逃れることはできないと。そんなどうしようもない凡人だからこそ、阿弥陀仏にすがるしか道はない。救いや癒しや悟りを求めて必死にすがり、それでも救われない人間を阿弥陀仏は決して見捨てない。だから、妙な表現だが、安心して(?)悲しむだけ悲しめばよいのである。悲嘆とは阿弥陀仏にすべてを委ねる「他力」への道が開かれたともいえるのだ。
悲嘆にくれる姿こそ仏の心:愛別離苦が救いと再会への道を開く
釈迦は愛別離苦の原因は、この世のすべては無常であるのに、愛するものに執着してしまうことだと教えた。そして親鸞はその執着を捨てられない凡人だからこそ救われると応じた。
本願寺で禁書扱いされていた歎異抄を事実上世に出した暁烏敏(1877〜1967 )は、真の悟りとは、人と別れて涙もこぼさないような人にはない。名残惜しまれて涙が流れ、切々たる愛の燃えているのが仏の心であると語っている。
愛別離苦とは、悲嘆にくれるほど愛した人と出会えたということでもある。その別れに悲しむ姿は、仏の心そのもの、つまり仏が寄り添っている証であり、その先には浄土での再会が待っているのである。
参考資料
■唯円 著/千葉乗隆 訳注「新版 歎異抄」」角川ソフィア文庫(2013)
■暁烏敏「わが歎異鈔 上・中・下」潮文社(1994)
■鍋島直樹「親鸞における愛別離苦への姿勢」『世界仏教文化研究論叢』60号 世界仏教文化研究センター(2022)
■拙稿 「病床に伏し常に死と隣合わせだった正岡子規と僧侶・清沢満之」