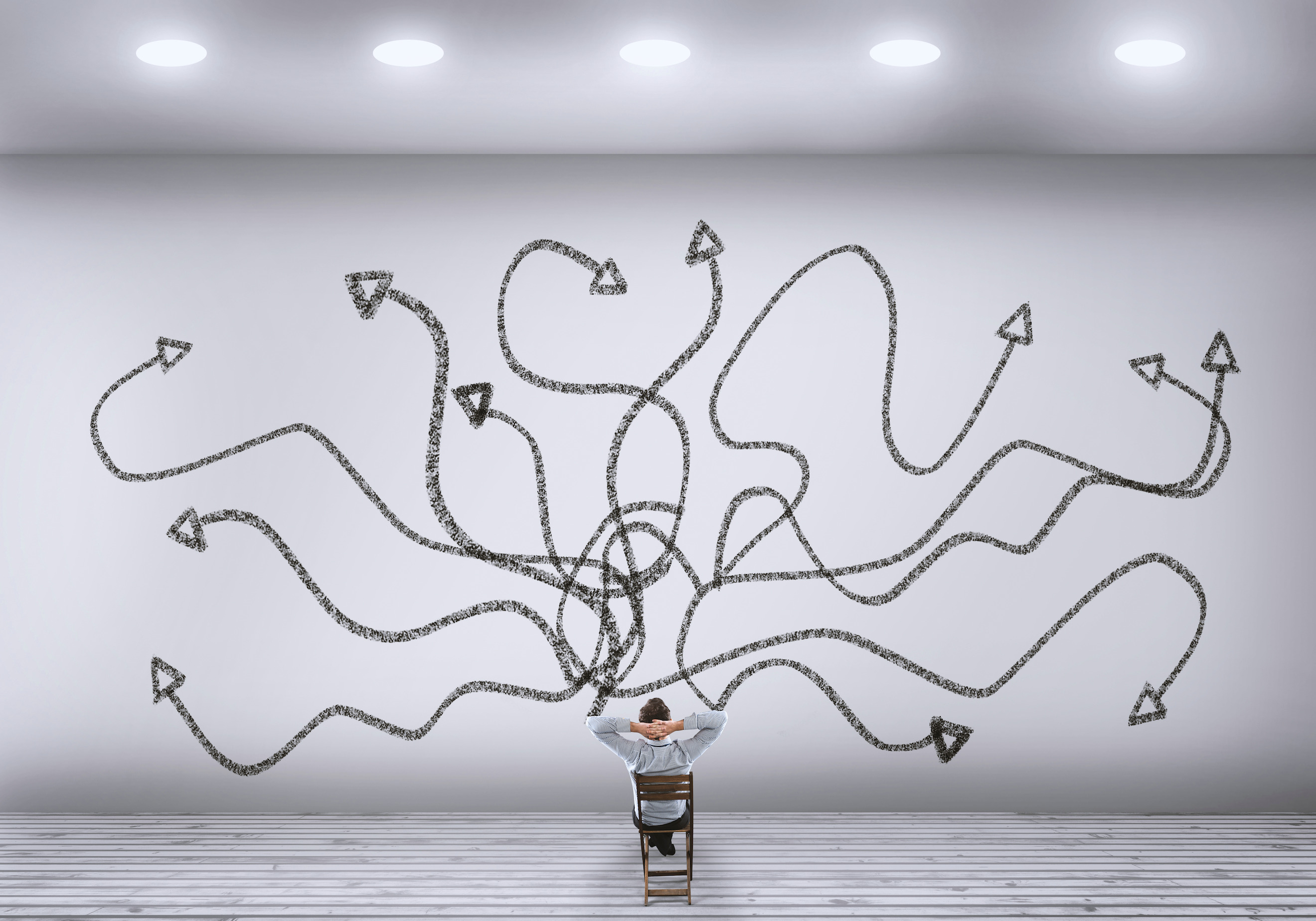「神」に向かって手を合わせるという所作は世界各地に見られる。手を合わせるとは単なる作法ではない。心身を整え、場を浄め、超越的存在に呼応するを身体表現である。今回は神道の「拍手」、仏教の「合掌」、キリスト教の「祈りの手」を取り上げ、それぞれの意味や起源を概観する。

神道の柏手
東京神社庁の説明によると、神社や神棚に参拝するとき、両方の手のひらを打ち合わせて鳴らす所作を「拍手(かしわで)」という。「柏手」とも書くが、拍(はく)の字が「柏(かしわ)」の字と混同されて用いられたことから生じた呼称とも言われている。中国の史書「魏志倭人伝」に倭人の風習として、貴人に対し手を打ちひざまづいて拝礼をする「跪拝(きはい)」をしていたことが記されていることから、当時は人にも拍手をしていたことがわかる。神に対しても人に対しても敬う気持ちの表れである。
拍手には二拝二拍手一拝のときに打つ「短拍手(みじかて)」のほか、八つ打ってさらにその終わりに短拍手を一つ打つ「八開手(やひらて)」、直会(なおらい)で盃を受けるときに一つ打つ「礼手(らいしゅ)」などがあり、出雲大社の「四拍手(しはくしゅ)」が知られている。
いずれにせよ神前で手を打ち鳴らすことで、神々と呼応し心身を清める「禊・祓い」の意味をもつ。自然を神として崇めるプリミティブな宗教である神道では、拍手や祝詞を通じて自然の霊性に働きかけるのである。実際にやってみるとわかるが、姿勢を正して拍手をし、そのまま合掌をすると心身が引き締まる感覚がある。拍手は心身が新しく生まれ変わるアクティブな心持ちを与えてくれる効果があると思われる。
元々神道は「常若」の思想がある。気枯れとも書くという「ケガレ」を遠ざけ、常に若々しく前向きで明朗なパワーを重視しており、20年ごとに造り替える伊勢神宮の式年遷宮はその象徴といえるだろう。日常でも喜ばしいことや楽しいこと、人を励ますときなどには、拍手(かしわで)ならぬ、拍手(はくしゅ)をする。ポジティブな感情が拍手を促すのだろう。
一方で、神道の葬儀である神葬祭の際には、音をたてずに打つ「忍手(しのびて)」を行う。葬儀の場で、生命力の象徴である拍手を派手に打ち鳴らすわけにはいかない。そこで忍手を介して死者や神々と呼応し場を浄化する。
さらに呪術的な所作になると「天の逆手(あまのさかて)」がある。日本神話や伊勢物語などに登場する、手の甲を逆にして手を打つ、呪いの所作である。拍手にはこうした二面性があるが、正負いずれの方向にせよ、行為としては積極的な面がみられる。
仏教の合掌
仏教における合掌は両掌を胸前で合わせる礼法で、拍手とは違い音を鳴らさず静かに手を合わせる。古代インドのバラモン教以来の敬礼形式に由来するとされ、仏教においては、仏・菩薩・師・衆生への尊敬と一体化を表す所作である。元々インドでは右は清浄、左は不浄とされており、合掌は清浄や不浄といった分別を超えた境地を意味する。仏教ではこれが転じて右手を悟り(仏)、左手は迷い(衆生)を象徴し、それを合わせることは「仏と衆生は不二」を体現する。日本では仏像のポーズや礼拝作法として定着し、信徒の祈りにも広く用いられた。また、瞑想や心を落ち着かせるときなどに用いられることが多い。
合掌にも拍手と同じく様々な形がある。最もポピュラーないわゆる「合掌」は「堅実心合掌(けんじつしんがっしょう)」という。浄土宗や浄土真宗のようなシンプルな宗派では堅実心合掌が用いられ、密教系では堅実心合掌から掌に空間を作る「虚心合掌(こしん合掌)」や、交互に指を組み合わせる「金剛合掌」などの「十二合掌」があり、「印」に近いものがある。
神道の拍手は音を立てて神に呼びかける能動的、動態的な行為であるのに対して、仏教の合掌は音を立てず静かに行う、静態的、内省的な精神が表れている。仏教が本来、外に神々を求める宗教ではなく、内なる世界に深く沈み込み、悟りに至る宗教であることがわかる。
一般的には、手を合わせる場面とは、苦しいときや困ったとき、必死の願いをするときなどがあるだろう。そうしたとき人はひたすら手を合わせ救いを求める。理由や目的はどうあれ、手を合わせ念じている間だけは純粋な時間である。葬儀や法事の際に死者に手を合わせる行為は、純粋な心を手向けることに他ならない。
キリスト教の「祈りの手」
キリスト教では「手を組んで祈る」という所作が一般的である。両手の指を組み合わせて胸の前または顔の前に置く。拍手、合掌と同様、神への畏敬の念や、服従といった精神を身体で表すものである。この所作は王侯貴族や領主に対して家臣、民衆が行う所作でもあり、「自分の力を差し出し、主に委ねる」象徴であった。この「主」が「主(God)」になると、キリスト教徒の「祈りの手」になる。自己の無力を認め、超越的存在にすべてを委ねる絶対的服従の誓いが祈りの手だといえる。
だが、「祈りの手」は本来聖書的ではなく、初期のキリスト教徒(1〜4世紀ほど)は祈りの手をしていなかったようである。初期のキリスト教美術では、両腕を左右に広げ、掌を上に向ける「オラント」と呼ばれる姿勢で祈る人々が描かれている。死者を弔う祈りの姿勢ともされ、旧約聖書にも由来する、神への服従や嘆願、感謝、賛美などの姿勢である(詩篇28篇2節、テモテ人への手紙2章8節など)。現在のような形になったのは中世以降であるようだが、オラントの両腕を広げる所作は、神に自己のすべてを捧げる形であると同時に、神からの恵みを受け入れる形であるようにも見える。これに対し「祈りの手」はひたすら神に服従を誓っているかのようで、一層神への信仰が深まった形と思われる。煉獄で浄めの炎に焼かれている死者への「とりなし」を求めるといった切なる願いには、オラントのようなオープンな所作よりも必然的に「祈りの手」のような形になるのではないだろうか。
それぞれの意味
神主の資格を持つタレントの狩野英孝氏が「神社あるある」として、「神社のお寺の違いがわからない 」と話していた。こうした分野に特に関心がない限り、あえてその違いを知る機会は確かに少ない。筆者も寺院で柏手を打つ人を見たことがある。これも神仏が習合した日本の宗教形態の現れといえるかもしれないが、やはりそれぞれの意味は知っておきたい。手を合わせるという、たったそれだけの所作に神仏や死者への深い祈りが込められているのである。
参考資料
■東京神社庁ホームページ
■「聖書(新共同訳)」日本聖書協会(1996)
■矢向正人「天の逆手 : 古事記の国譲りに現われた手拍(てう)ちの検討」『芸術工学研究』31巻 九州大学(2019)