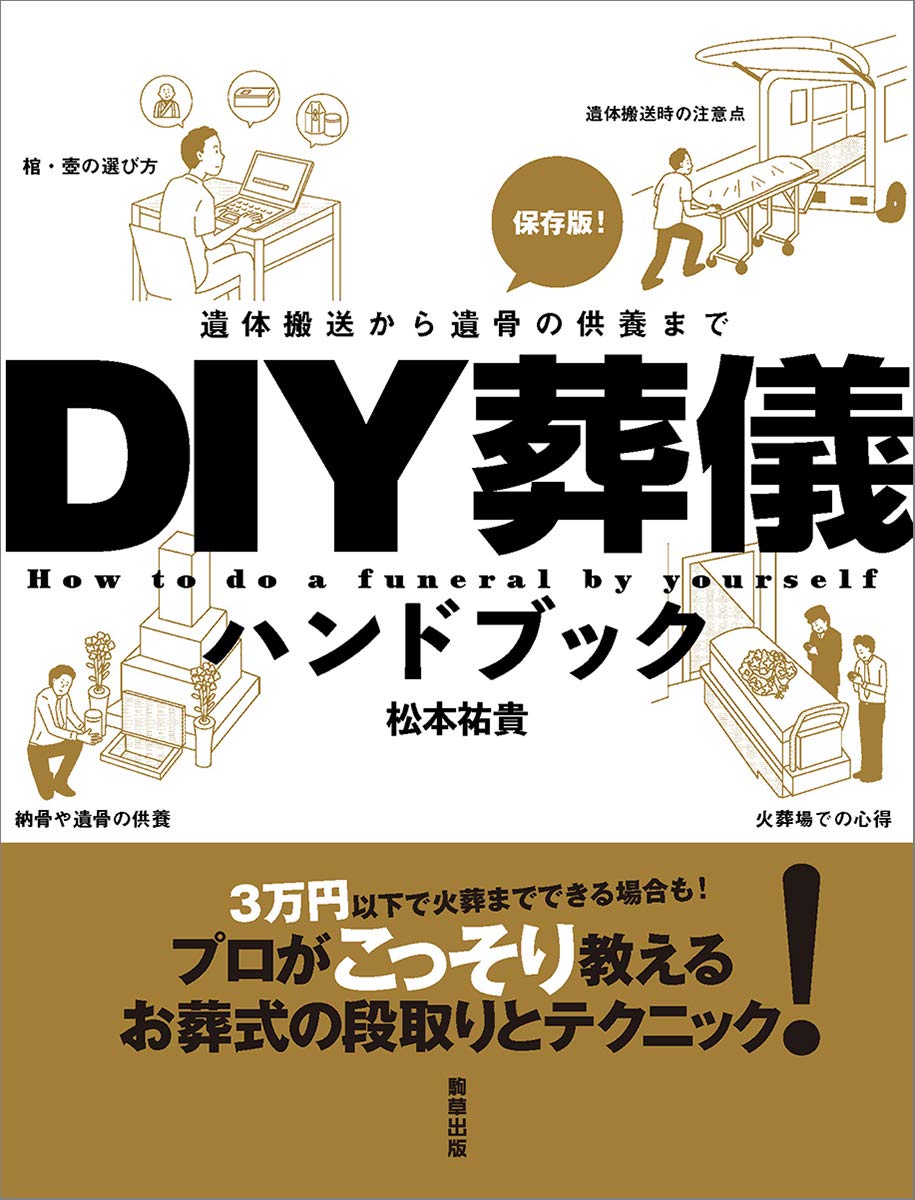葬儀の歴史は古いが、現代行われている伝統的な仏式葬儀、いわゆる「お葬式」の体裁を整えたのは曹洞宗であるといえる。だが曹洞宗は禅の伝統を伝える「禅宗」の一方の雄である。禅は本来、形式的ものを否定する傾向がある。それが「葬式仏教」の誹りを受けかねない、葬送儀礼の嚆矢となったのはなぜだったのか。

求道者の道元と禅の厳格な出発点
曹洞宗は宋で禅を学んだ道元(1200〜1253)が開いた宗派である。いわゆる鎌倉新仏教のひとつで禅の伝統を今に伝える。道元は非常にストイックな人物で、彼が開いた永平寺は北越の厳しい環境にあり、その戒律の厳しさは知られるところである。一方の禅宗、臨済禅が師から与えられる「公案」を解く、いわゆる禅問答のような動的な行を修めるのに対し、道元はただ坐ることを求める「只管打坐」を説いた。そこには現世利益のような要素はない。仏道をひたすら極めるための坐禅あるのみである。道元の示す禅の道は厳しく、その哲学は難解で、とても民衆が実践できるものではなかった。
現世利益を求めた民衆へ門戸開放した曹洞宗
永平寺三世・徹通義介(てっつうぎかい/1219〜1309)は、禅に密教の儀礼などを取り入れ、民衆にも門を開き大衆化を図った。このため、道元から続く純粋な禅の維持を主張した保守派との対立を呼び、退任、再任を経て結局永平寺を出て大乗寺に入った。その大乗寺を継ぎ、義介の改革路線をさらに拡大したのが曹洞宗中興の祖と言われる、瑩山紹瑾(けいざんじょうきん/1268〜1325)である。密教化と大衆化、そして大衆化に伴う葬送儀礼の一般化はほぼ一致する。密教の加持祈祷こそは民衆が求める現世利益を提供するものだからだ。瑩山は曹洞宗に密教的な要素を加えることで民衆への布教を推進した。道元が厳格な禅の修行(只管打坐)を重視したのに対し、義介・瑩山が重視したのは、より幅広い民衆への布教であった。そのために民間信仰や文化に適応する柔軟な姿勢を見せた。難解で厳格な禅をそのまま説くのではなく、病気平癒や豊作祈願など、民衆の現実的な願いに応える儀式として、護摩焚きや加持祈祷などの密教的儀式を積極的に取り入れた。民衆は切実な現世利益の提供に集まった。その結果、曹洞宗=禅宗は民衆に受け入れられやすくなり布教が拡大した。ただし、曹洞宗全体が密教化したわけではなく、あくまで民衆への門戸解放が目的であった。
こうした改革により民衆に広く布教した瑩山は、曹洞宗を単立宗派としては国内最大の末寺数を誇る大教団に成長させた。曹洞宗は道元を「高祖」、瑩山を「太祖」として、仏壇には両祖が並んで祀られる。瑩山の改革はその後、さらに弟子の峨山韶碩(がざんじょうせき/1276〜1366)が引き継ぎ、追善供養など葬送儀礼の一般化、制度化を進めた。現在広く行われている仏式葬儀の基礎はこうして築かれ、他宗派もこれに倣った。
授戒・引導という葬儀の主要儀式と禅の教えの矛盾
曹洞宗の葬儀の代表的な儀式が授戒と引導である。授戒は死者を仏の弟子にするための儀式で、仏弟子の証である新しい名前、戒名と、仏弟子としてのルール、戒律を授ける。引導は仏弟子となった死者を仏の世界へ導くために法語を読んだり読経を行う。これらはこの世で悟りを開けなかったので、仏の世界で修行をするための儀式である。
だがこのような形式化された儀式と、禅の教えは一見、矛盾しているように見える。禅の究極は悟りを得て生死を超えること。葬儀の形式が整い、焼香や、戒名などの細かい儀礼・儀式が増えるほど、本来の禅的な世界からは遠くなっていく。だが禅における生死を超えるとは生死を否定することではない。禅の解釈における葬儀は、生死を見つめ直すための修行の場。死ぬということを見つめ、生きているということを見つめる場なのである。
山から民へ
禅や禅僧というと、深山幽谷に籠りひたすら修行をして悟りを得るといったイメージがある。それに比べると瑩山たちの改革は布教のために妥協したようにもみえる。しかし山に籠って坐禅をするような生活には他者との交わりがない。他者との関わりがなければ慈悲も感謝も救いもない。瑩山たちは、祈祷や葬儀を通じて、死者にも生者にも禅の世界、仏の教えを説く道を開いたのである。